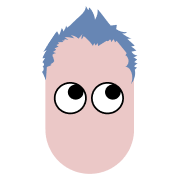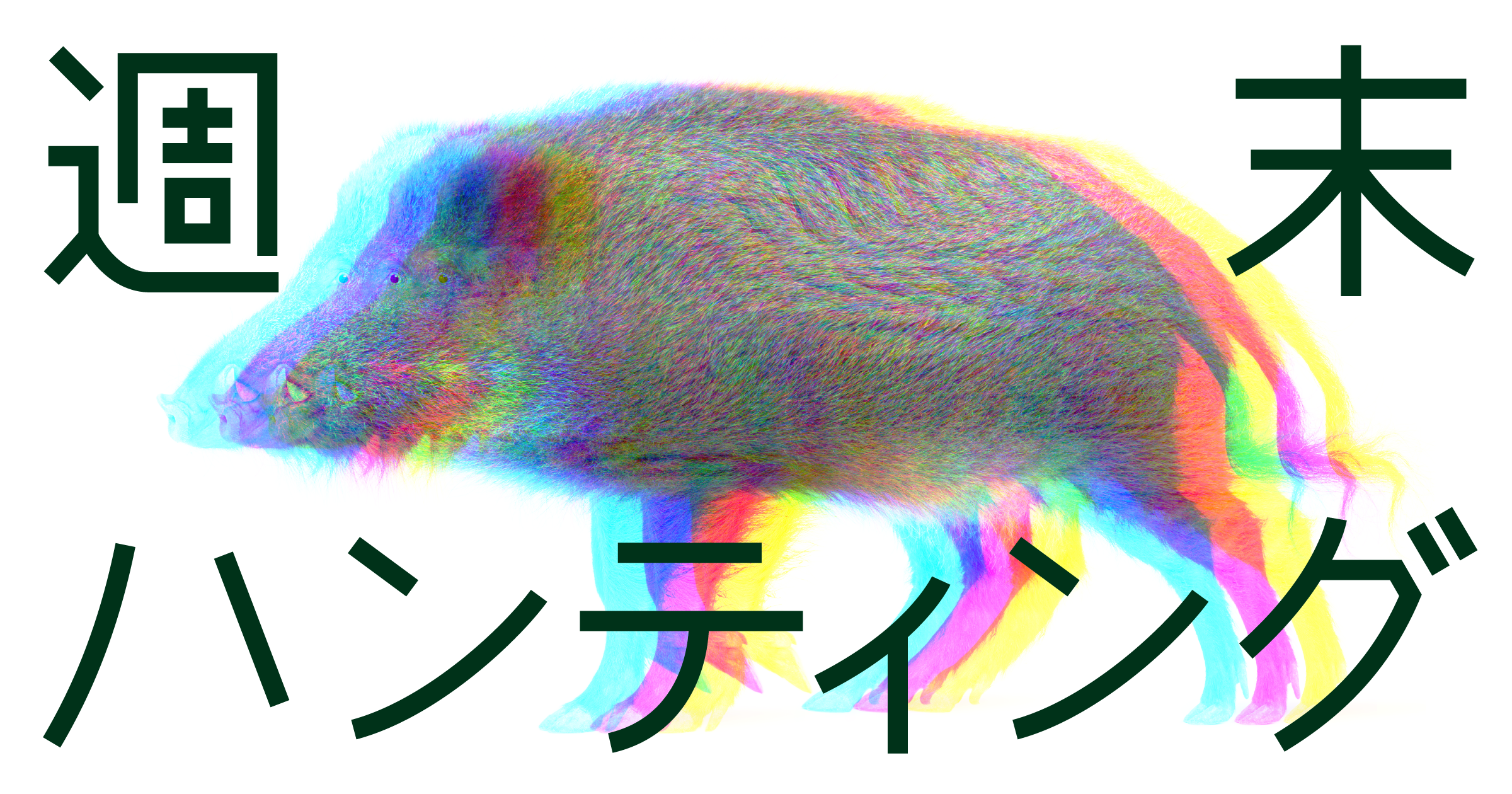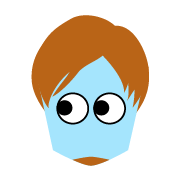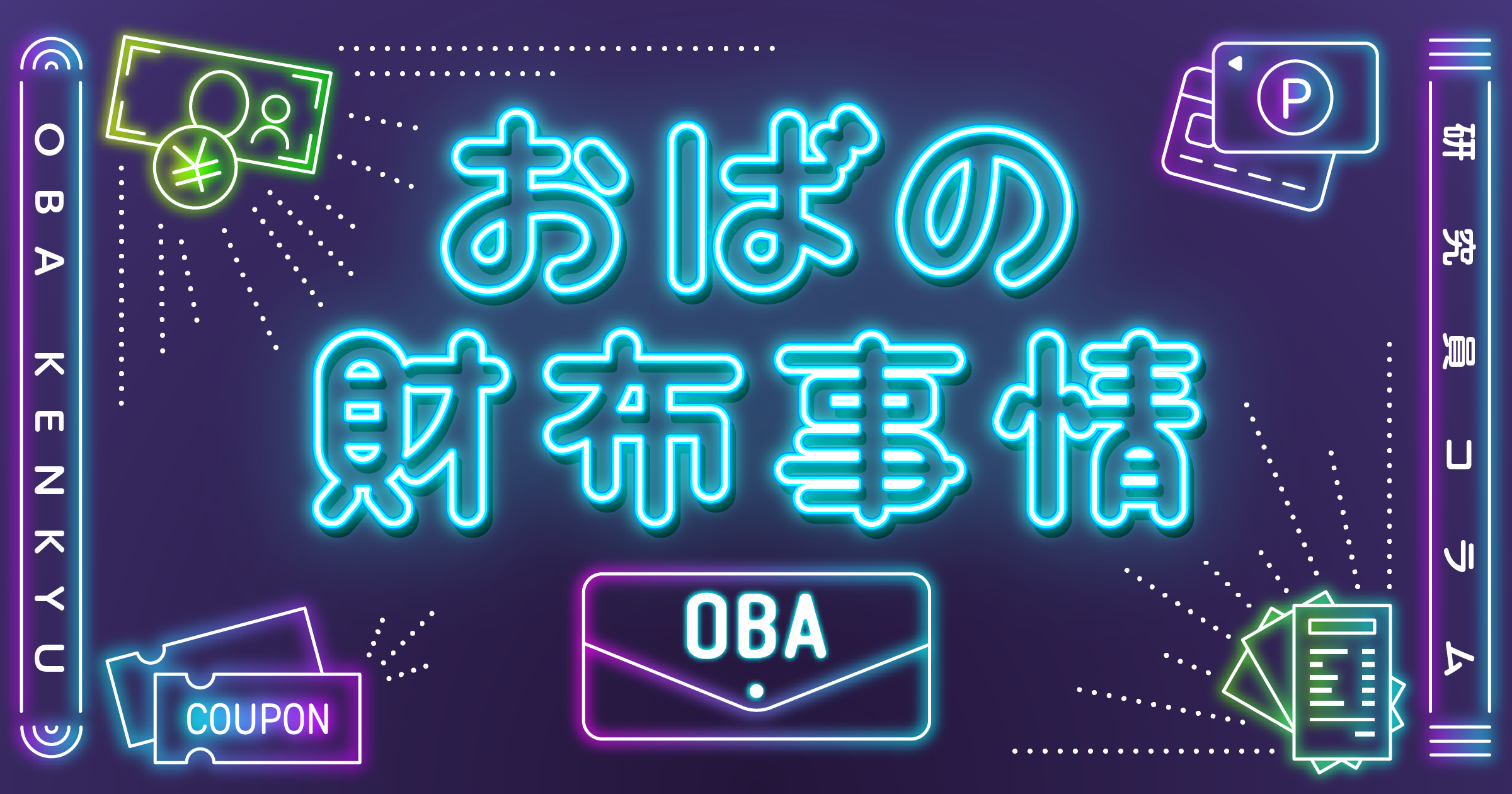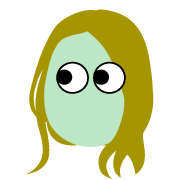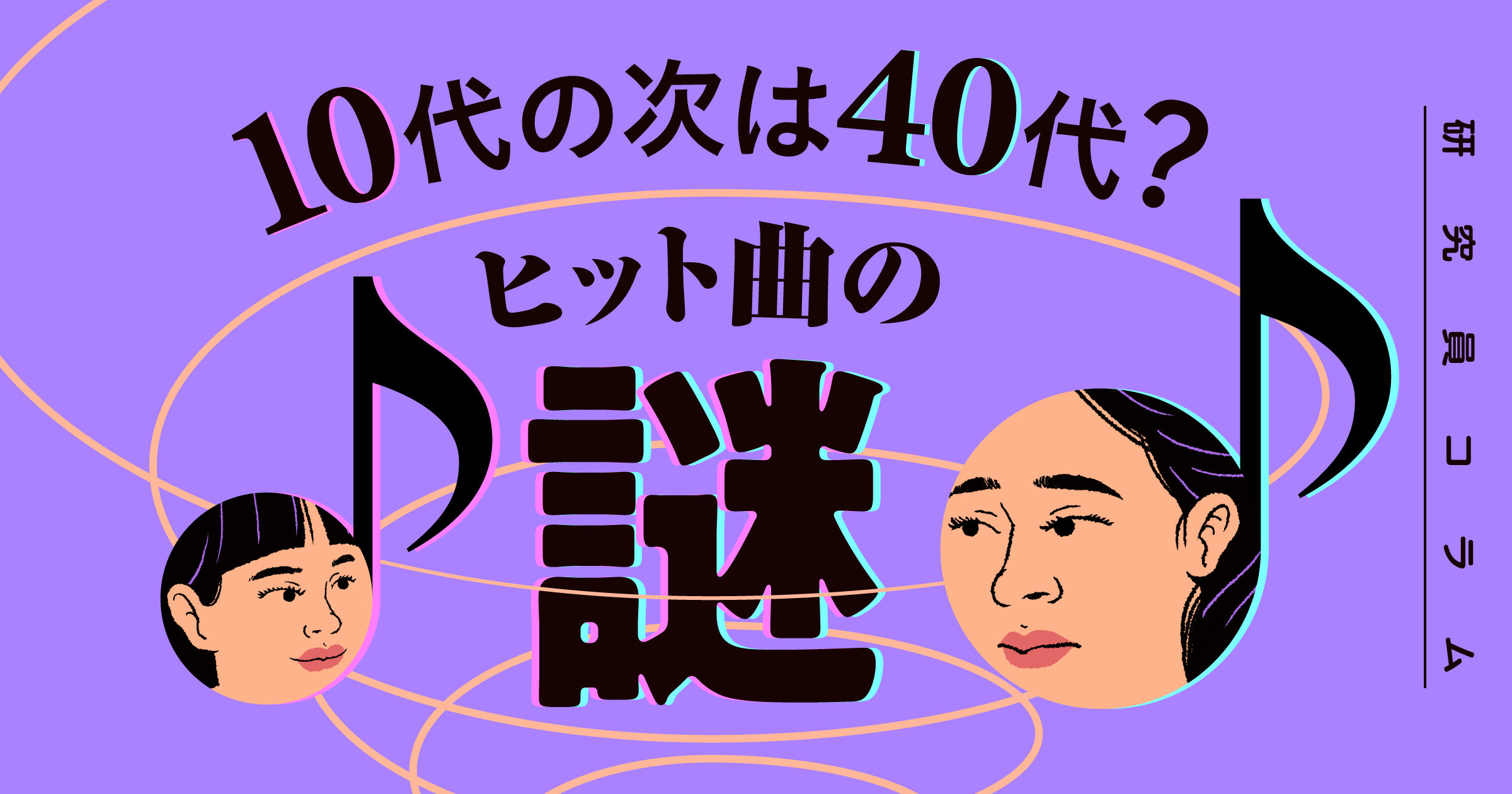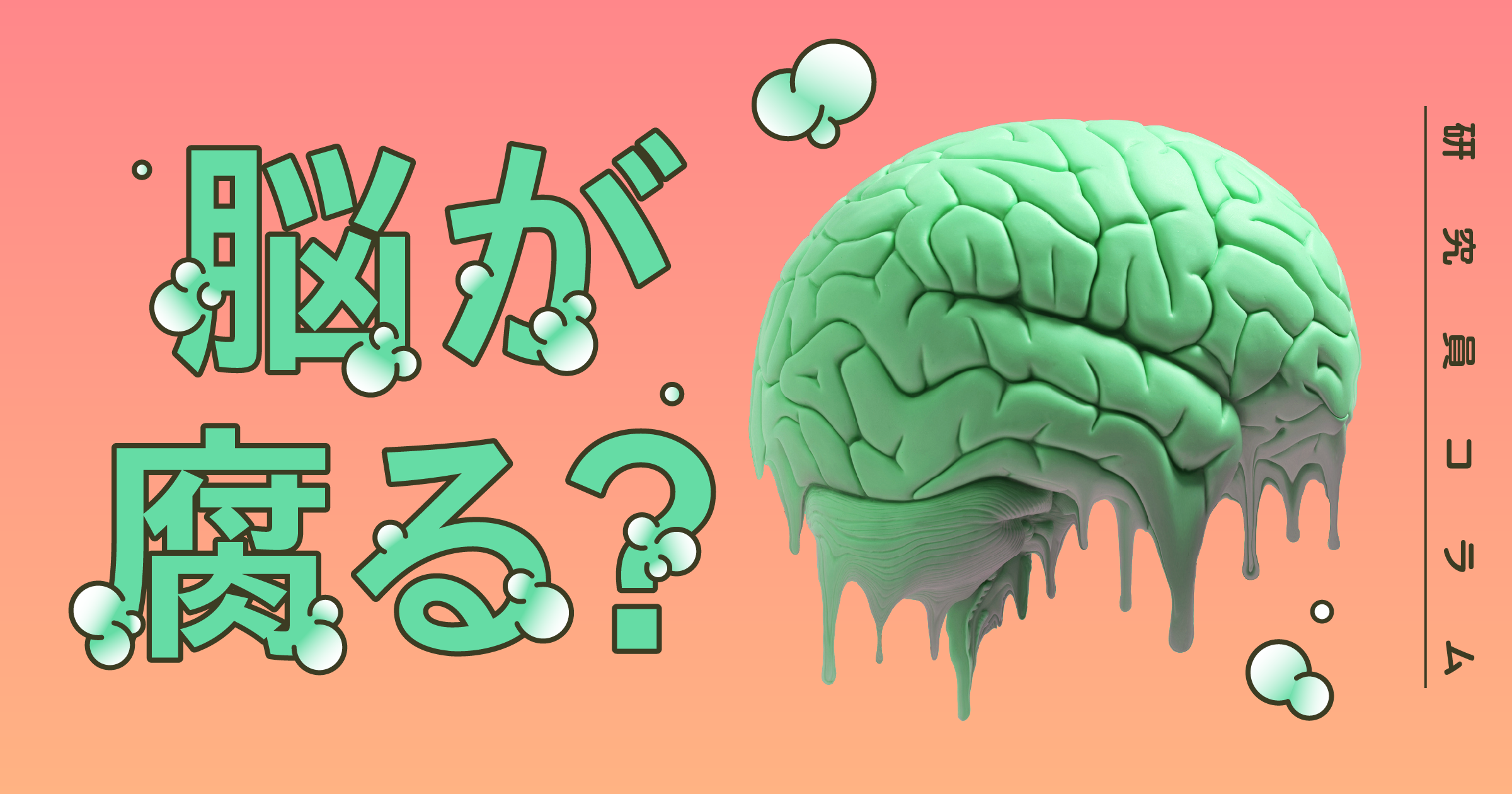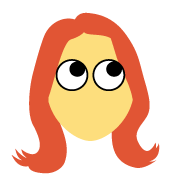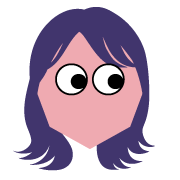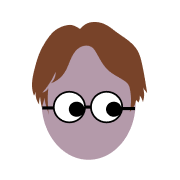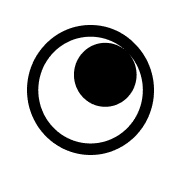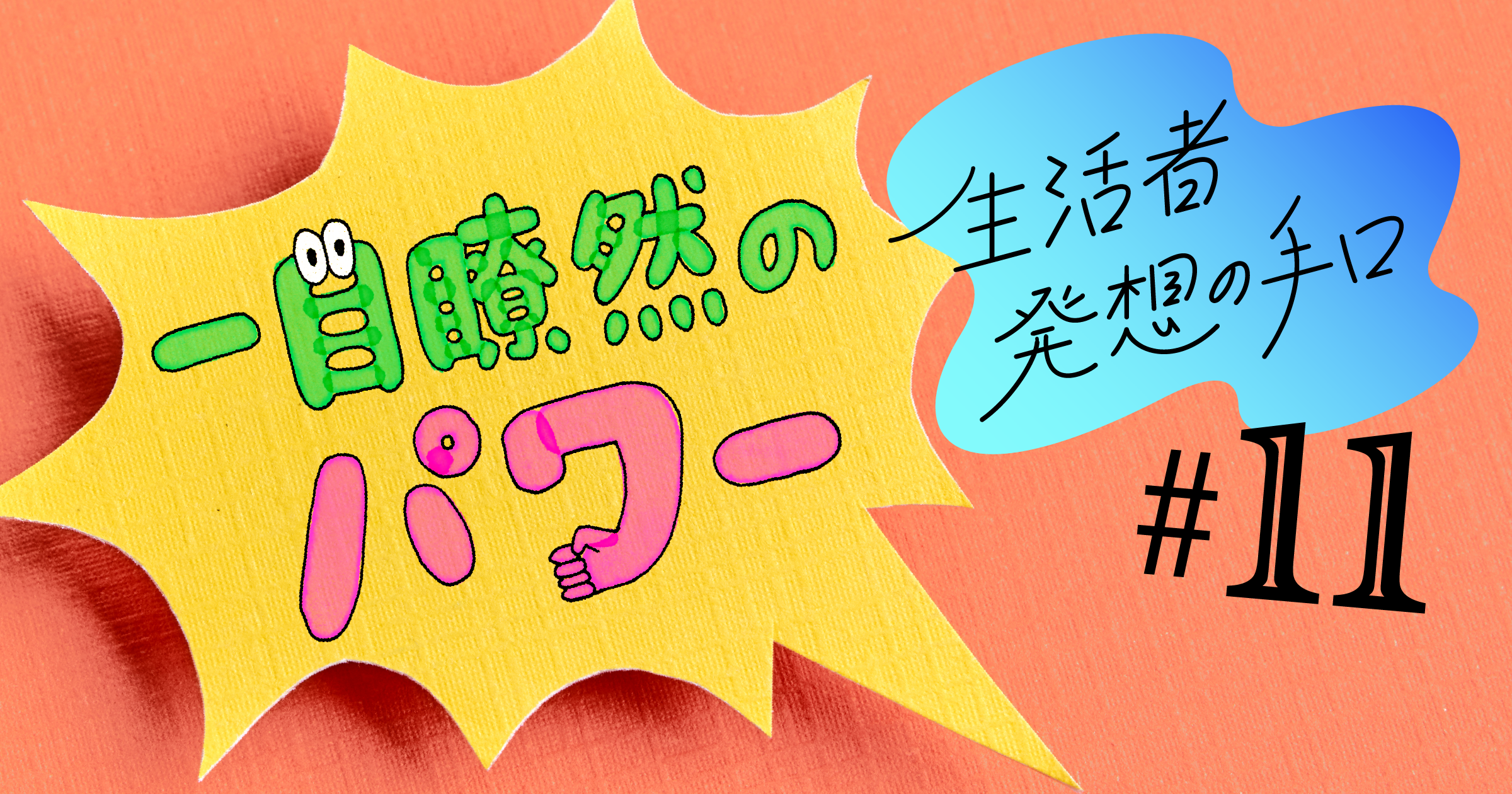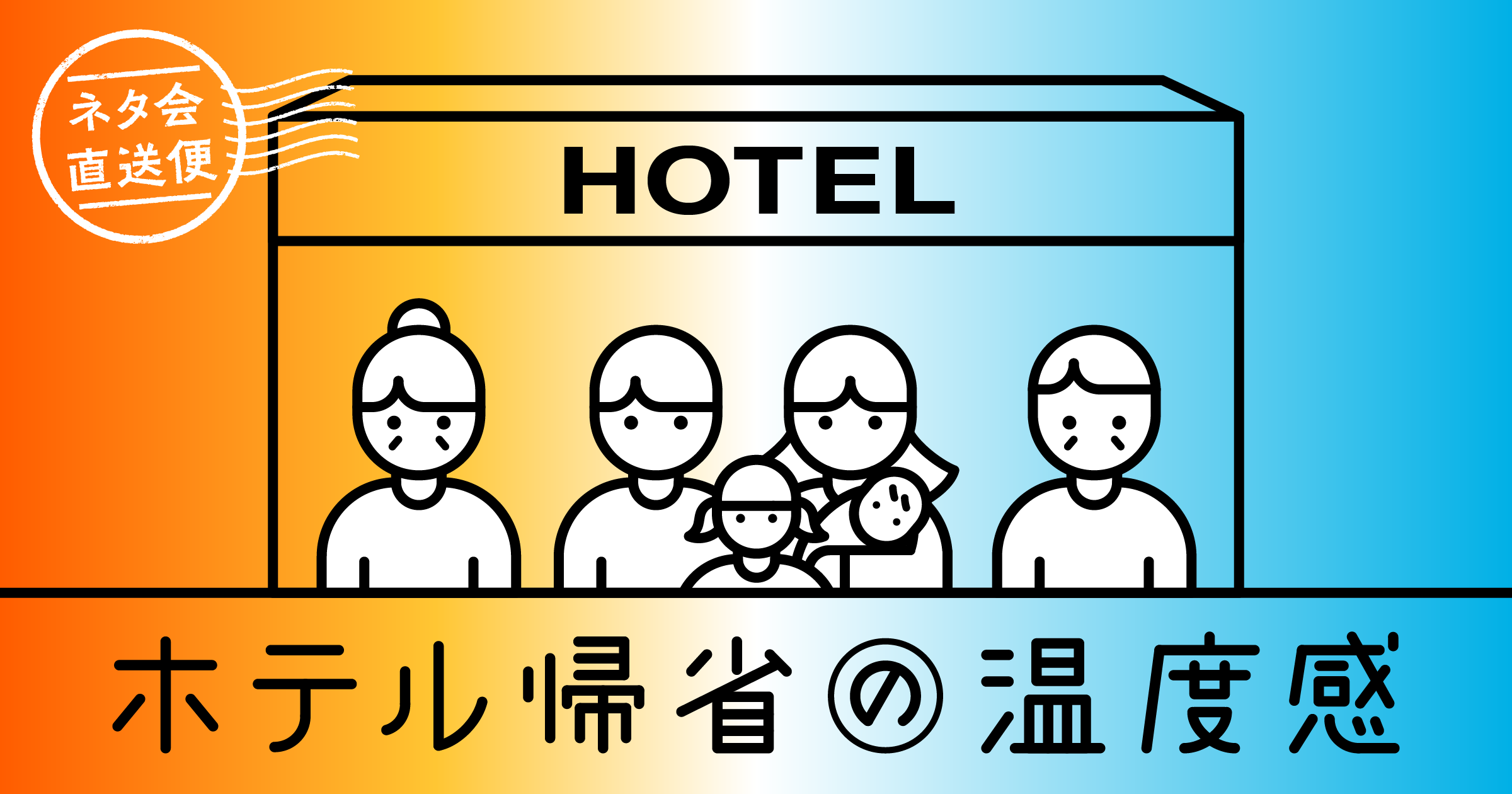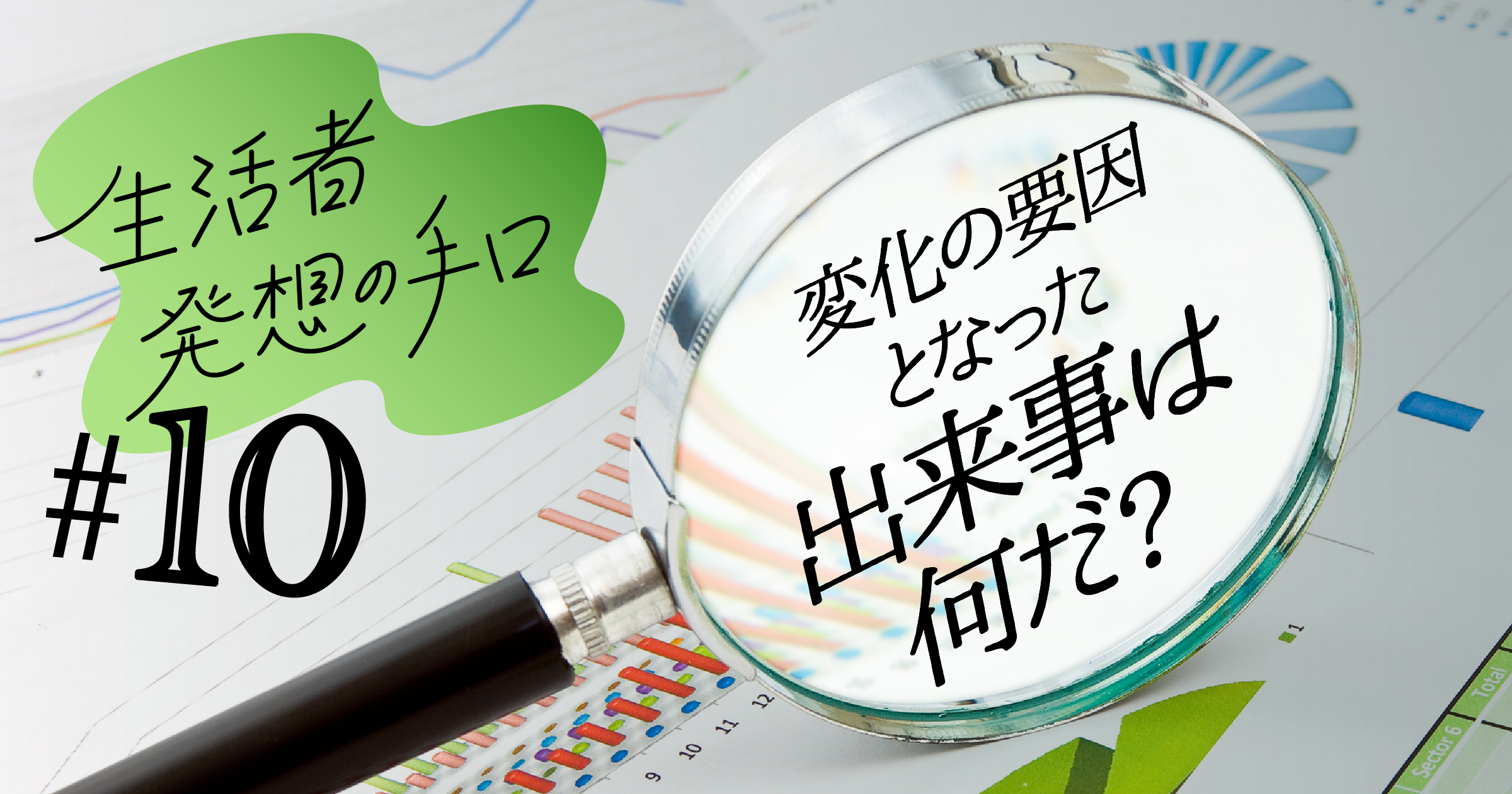部外者ほど「学会」へ行こう ちょっと知的な週末のススメ
2025.11.19
『月刊 生活総研』で編集長を務めております研究員の高橋です。この4月から大学院の修士課程に通っているのですが、先日、人生で初めての学会発表(口頭発表)に挑戦しました。参加したのは、日本社会心理学会。テーマは、昨年生活総研がサマーセミナーで発表した「若者30年変化」を軸に構築した、「Z世代における母子親密化と 『マザコン』の再定義」です。学会では、1994年と2024年の定量調査を比較して、子どもから「メンターママ」化した母親への信頼度が上がり、今やZ世代女性の3人に1人が「自分はマザコンだ」と認識している背景などの分析結果を発表しました。
その翌週は、社会情報学会にもこちらは特に何も発表せず学会にも入会せずに、「聞くだけ」という立場で部外者として参加してみました。私は文系学部出身ということもあってか学会という世界はずっと縁遠かったのですが、実は発表しなくても学会ってすごく面白い。いくつか興味深かった発表をかいつまんでご紹介しましょう。
社会心理学会のポスターセッションで出会った酒井拓人さんの研究(2025)は、メールやLINEなどの文末に「三点リーダー(…)」がついている場合に送り手の印象に与える影響について。若い世代にとって、文末に句点(。)がついていると「圧が強い」と感じる、という現象が報じられ「マルハラ」という言葉も生まれましたが、この研究は大学生を対象に「句点なし」「句点あり」「三点リーダー」の文章を比較して定量調査したものです。意外にも、句点の有無は送り手の印象に影響はほぼなく、「三点リーダーがついているとネガティブな効果がある」とのこと。「マルハラは存在しないのかも?」「むしろ三点リーダーが危険?」という気になる結果が明らかになっていました。
同じく社会心理学会での神野雄さん・川野邉そよさんの研究(2025)は、LINEにおける絵文字の使用(多さ)について。絵文字を使いすぎる「おじさん・おばさん構文」という言葉が報じられ、ヒヤリとした人もいるかもしれません。この研究では大学生を対象に定量調査を行い、「送り手がどのような場合でも絵文字を1個使用した場合」が常に好印象であると述べています。多用は良くないのかもしれませんが、「絵文字0よりは1つ使ったほうがいい」というデータにはちょっと安心した方もいるのではないでしょうか。
これらは社会心理学会の発表なので、マーケティングやコミュニケーションに携わる方には興味を持ちやすいテーマだったかもしれません。ただこれはごくごく一例で、世の中には、こうした身近なテーマを真剣に解明しようとしている研究者がたくさんいるのです。見たり聞いたり、発表者と話すだけでも十分な知的エンターテインメント。学会の参加費は数千円です。ご興味がわいたら、頭の体操がてら気軽に参加してみてはいかがでしょうか。