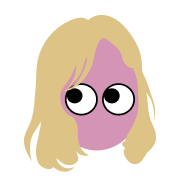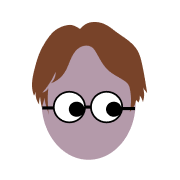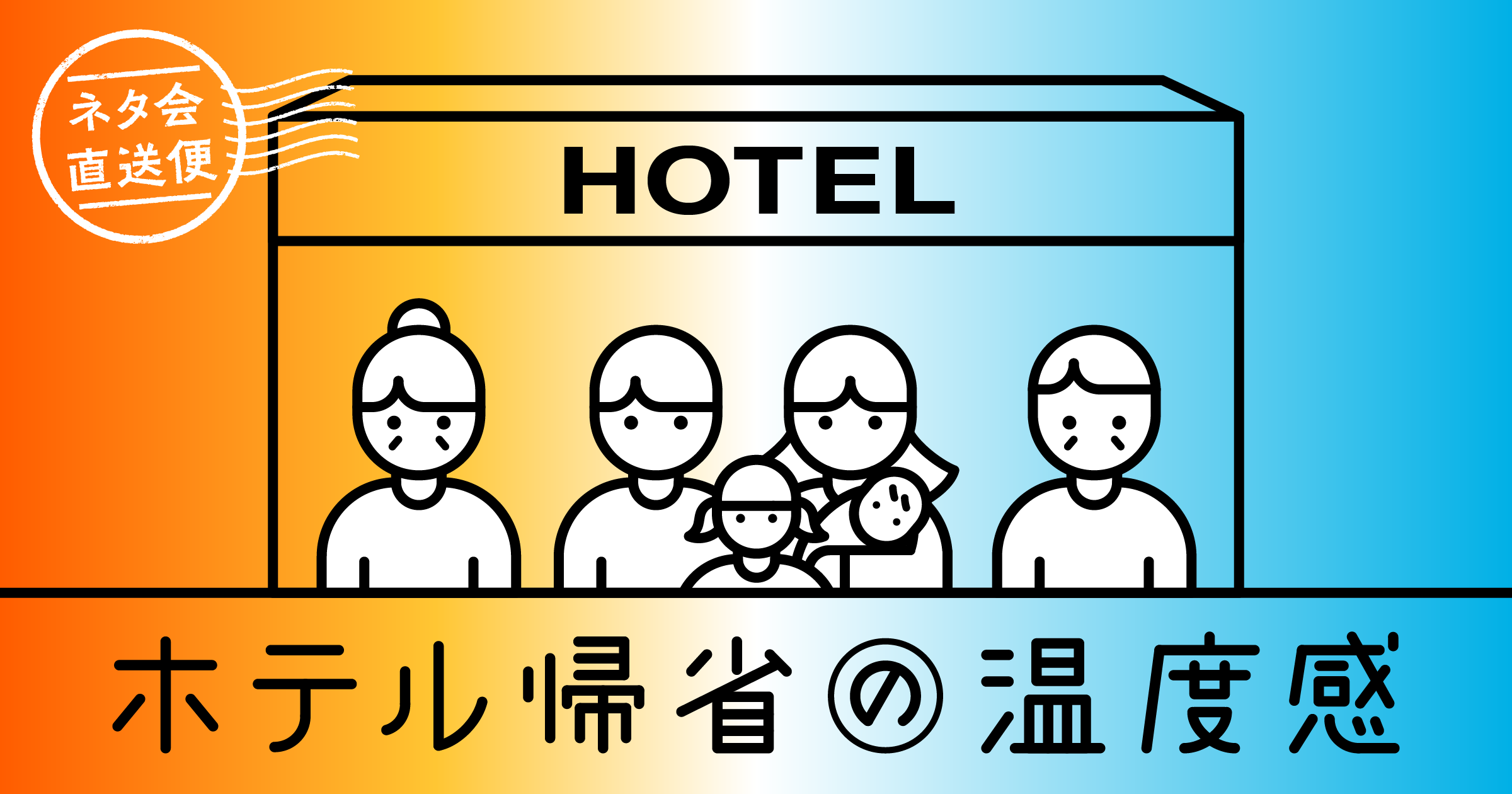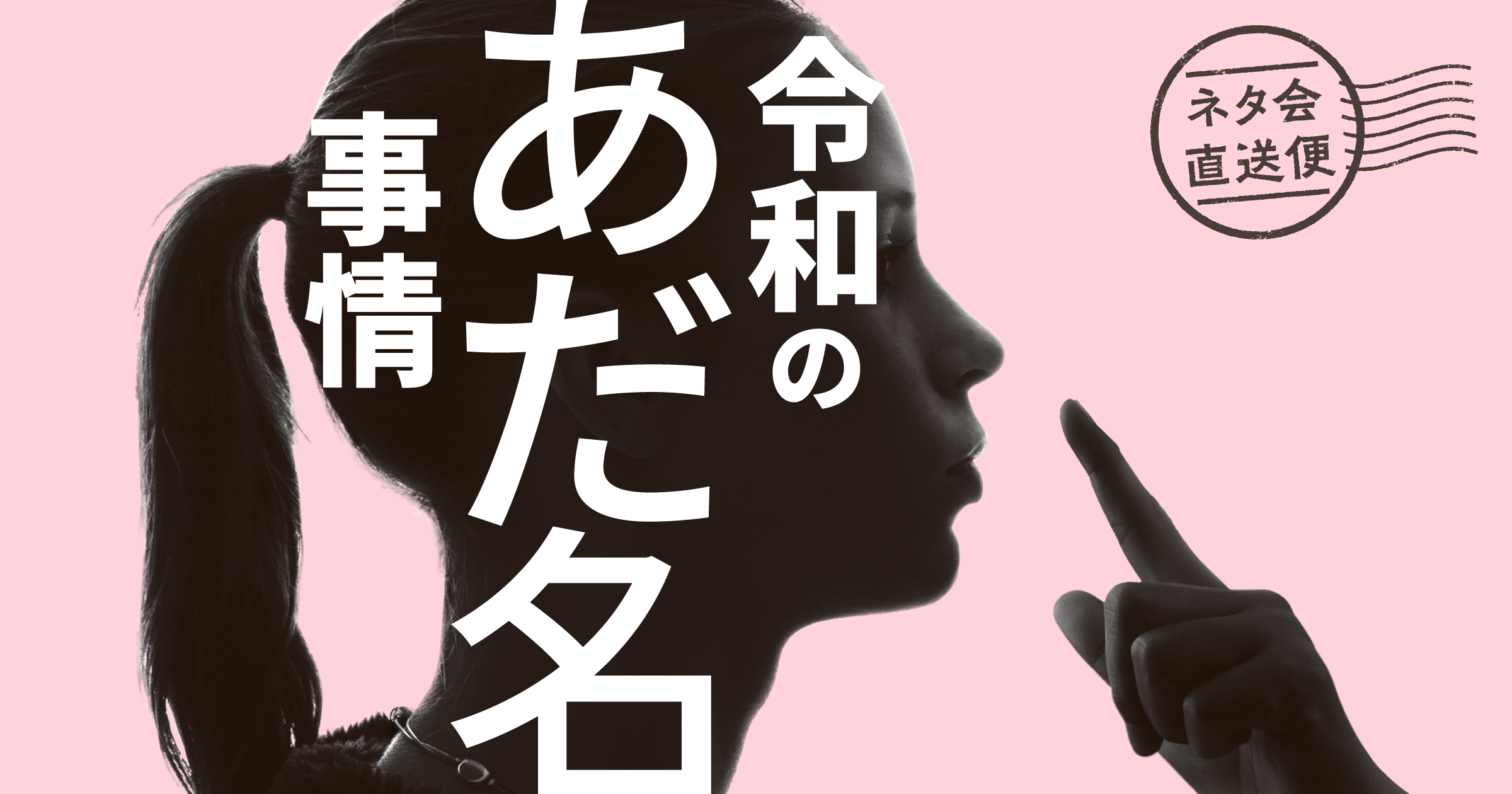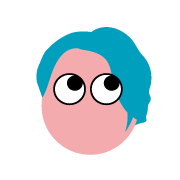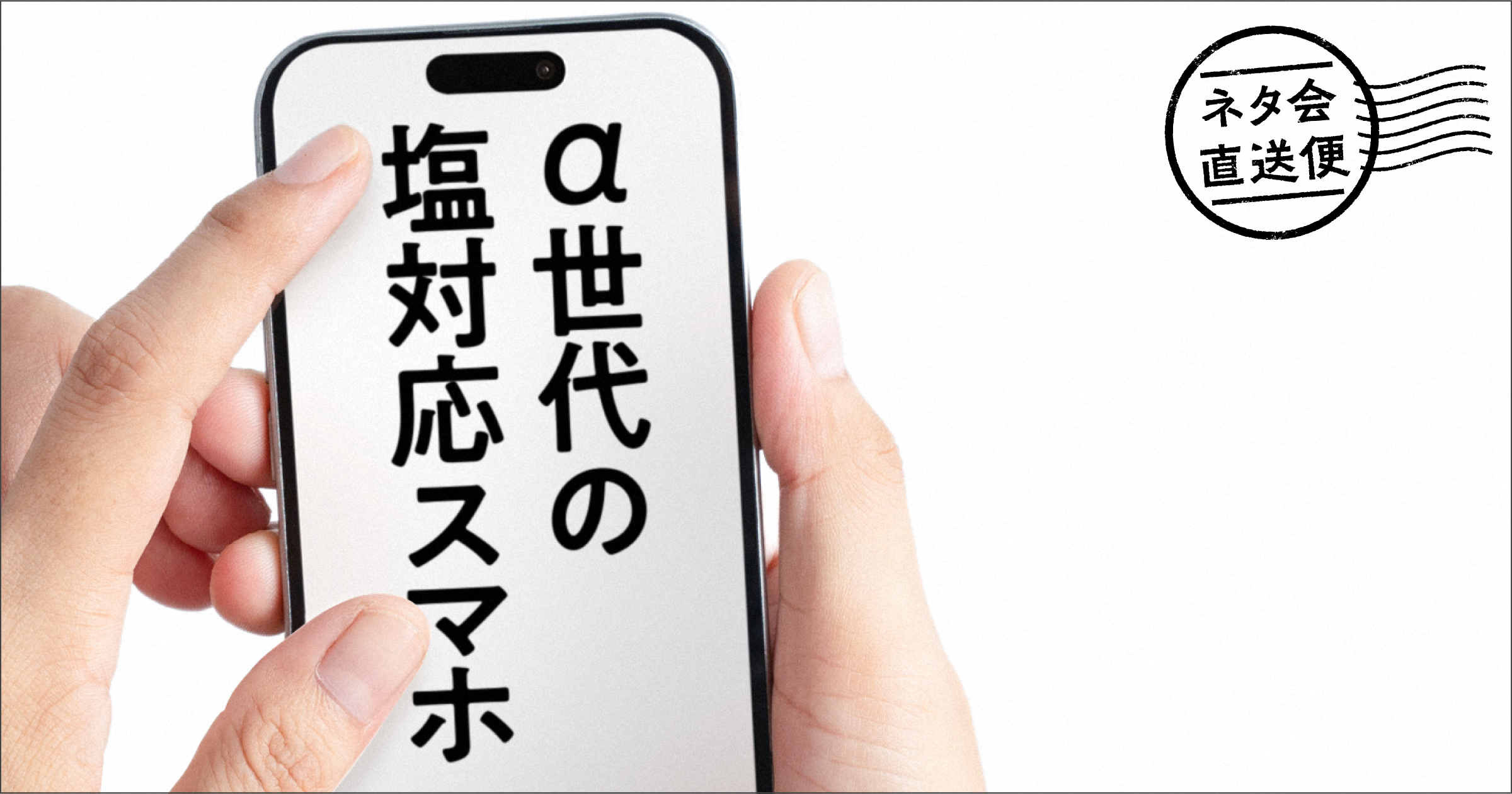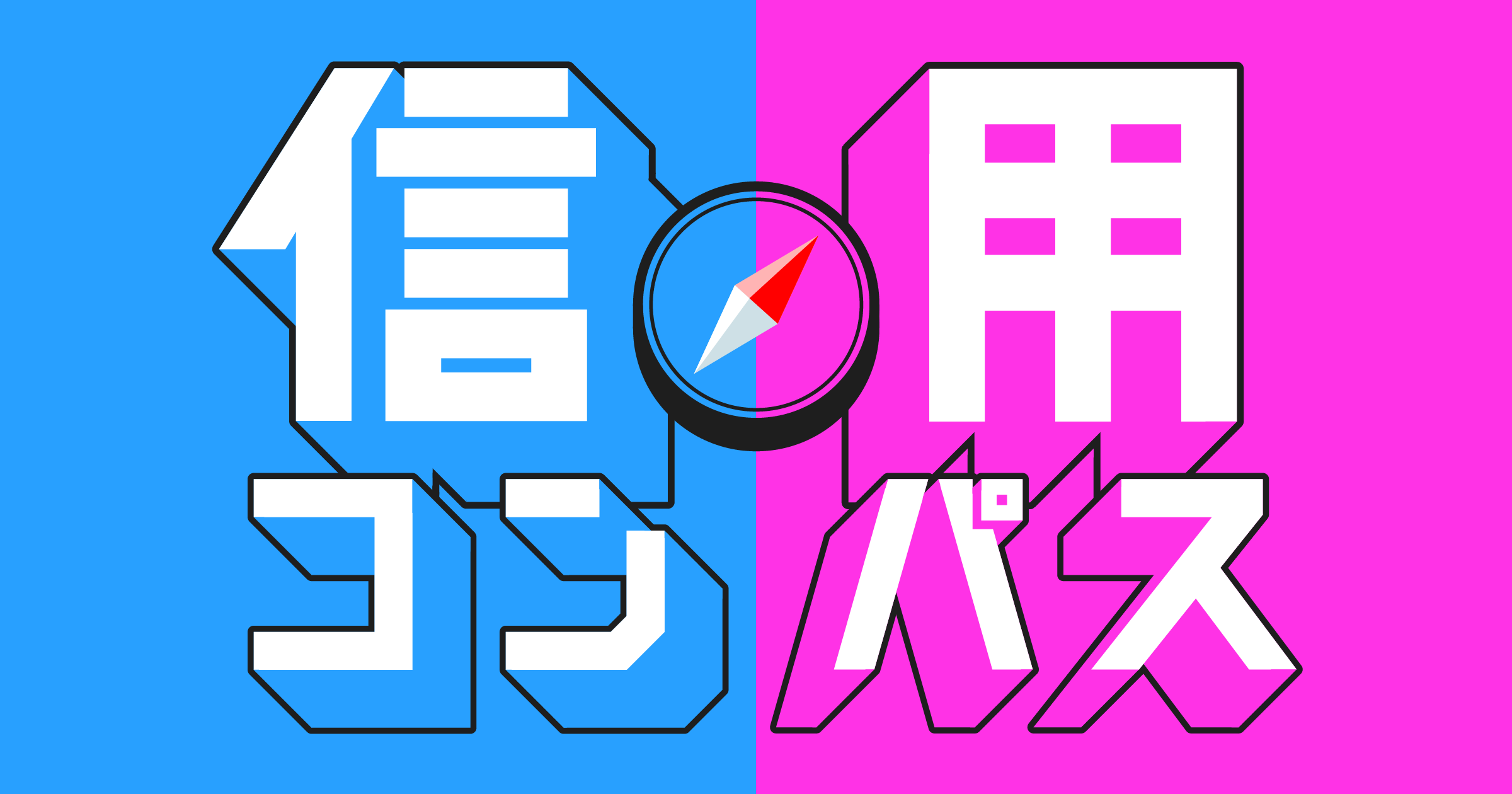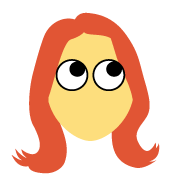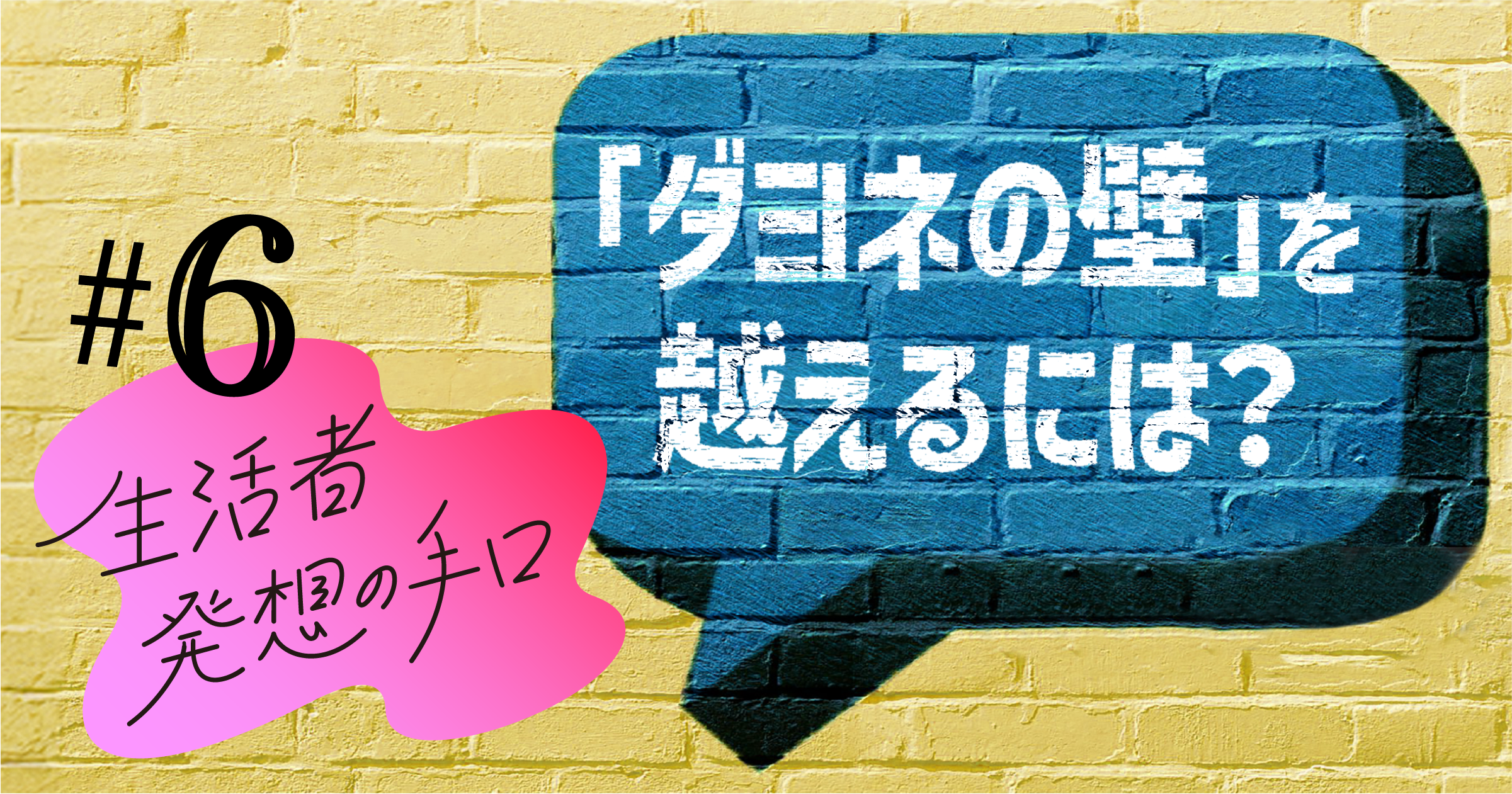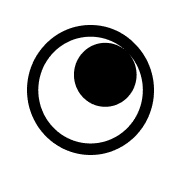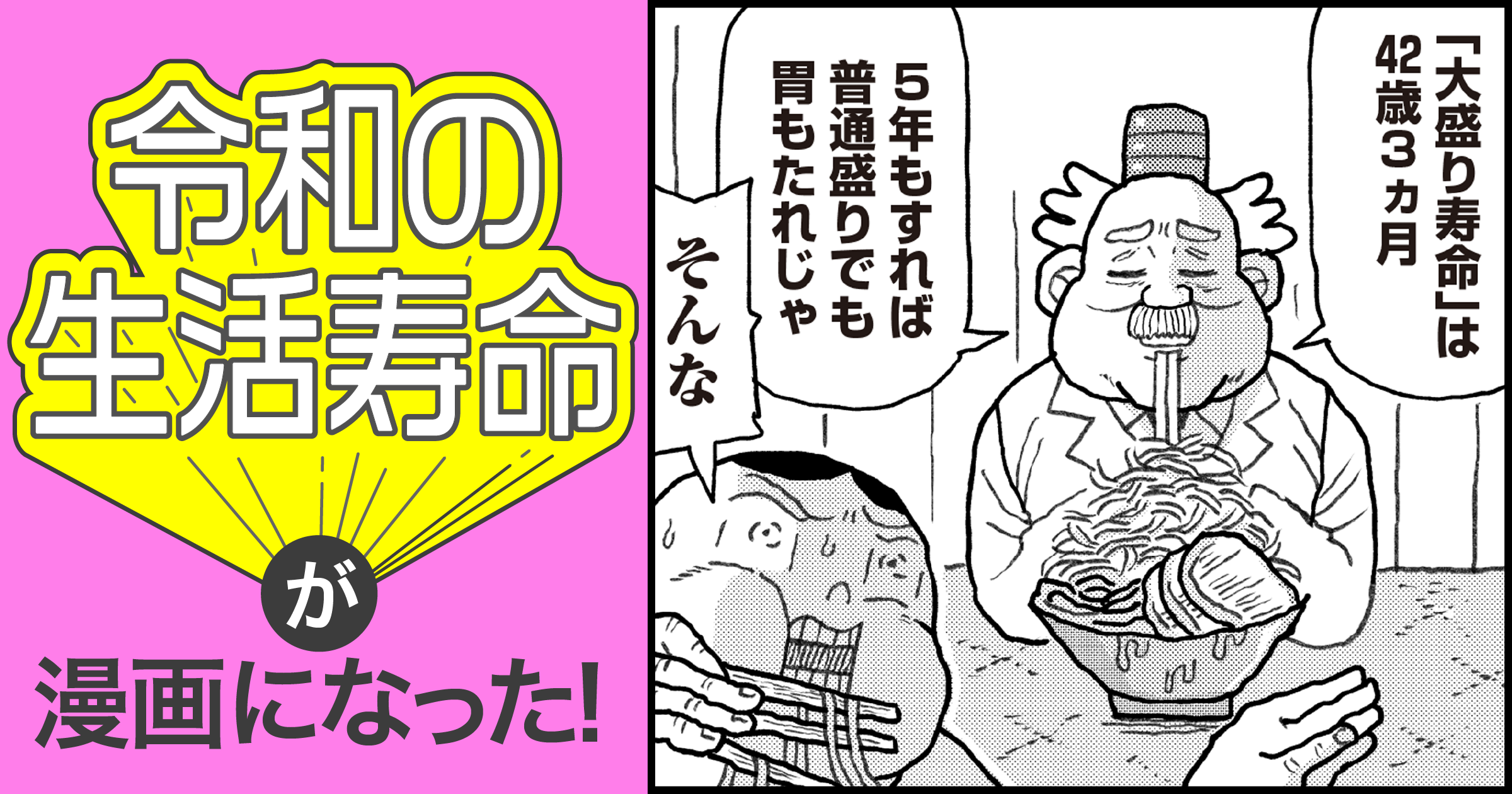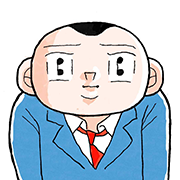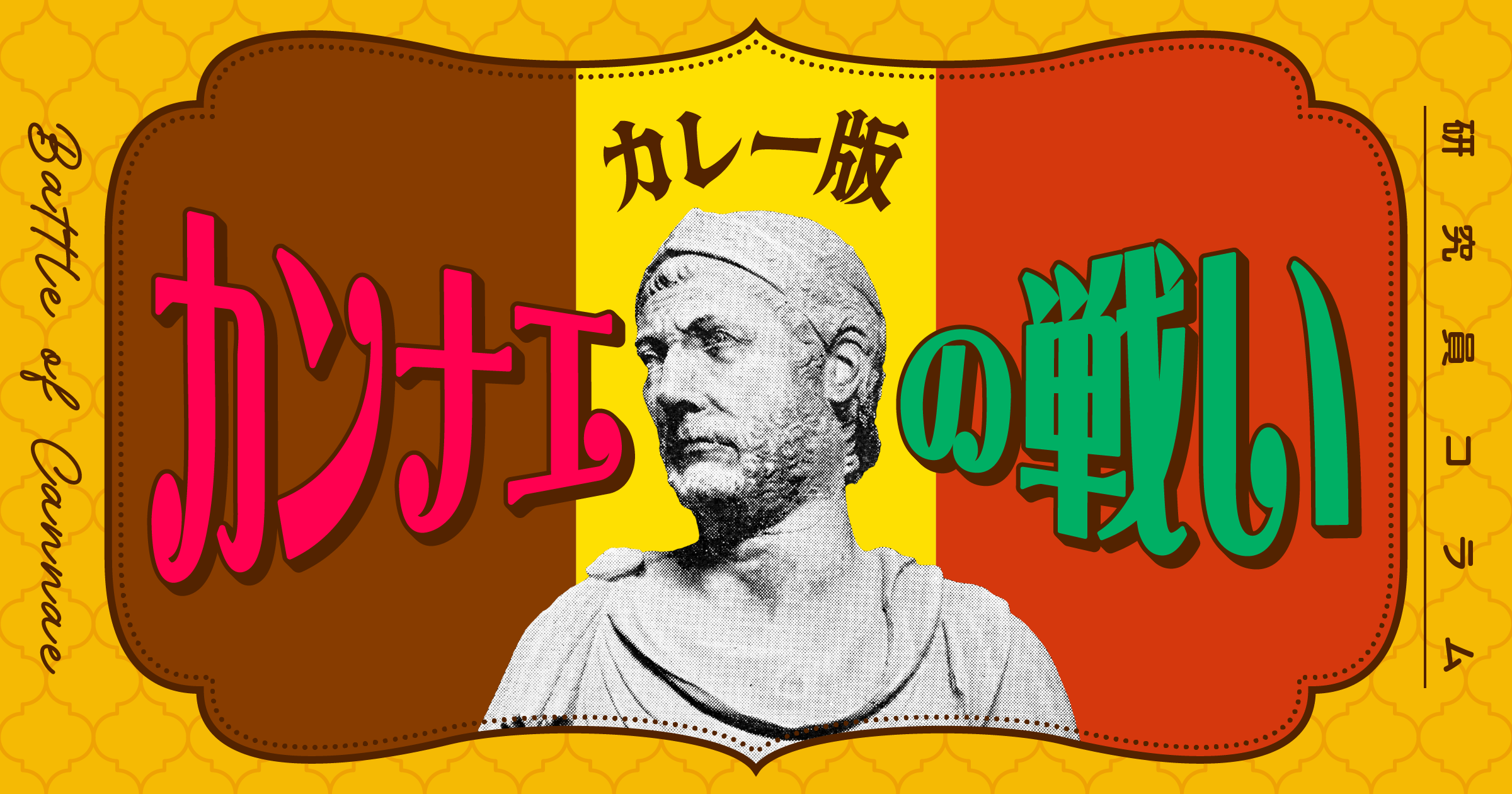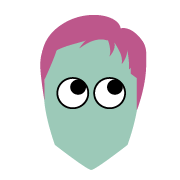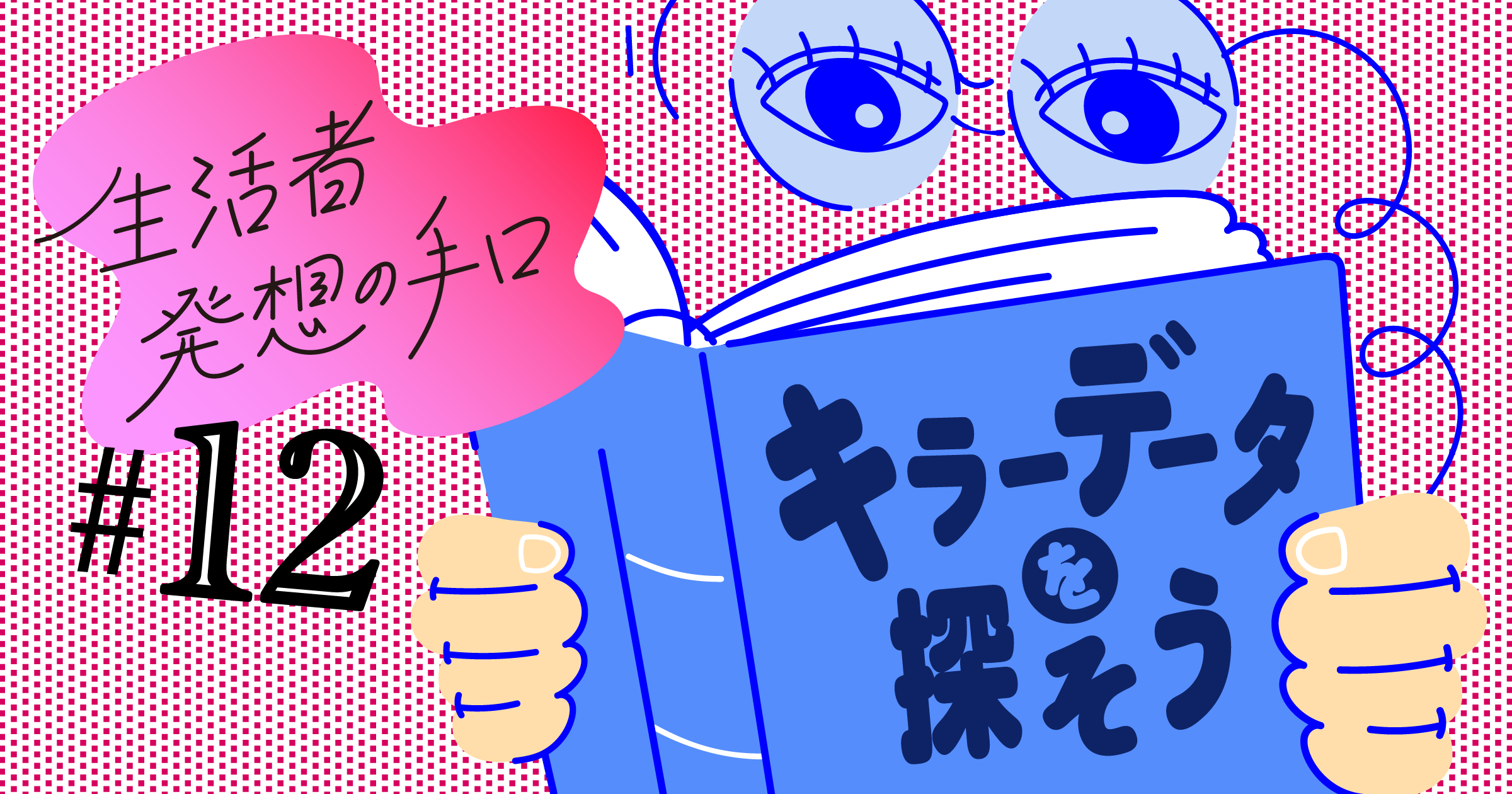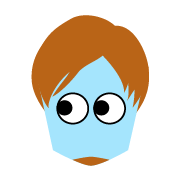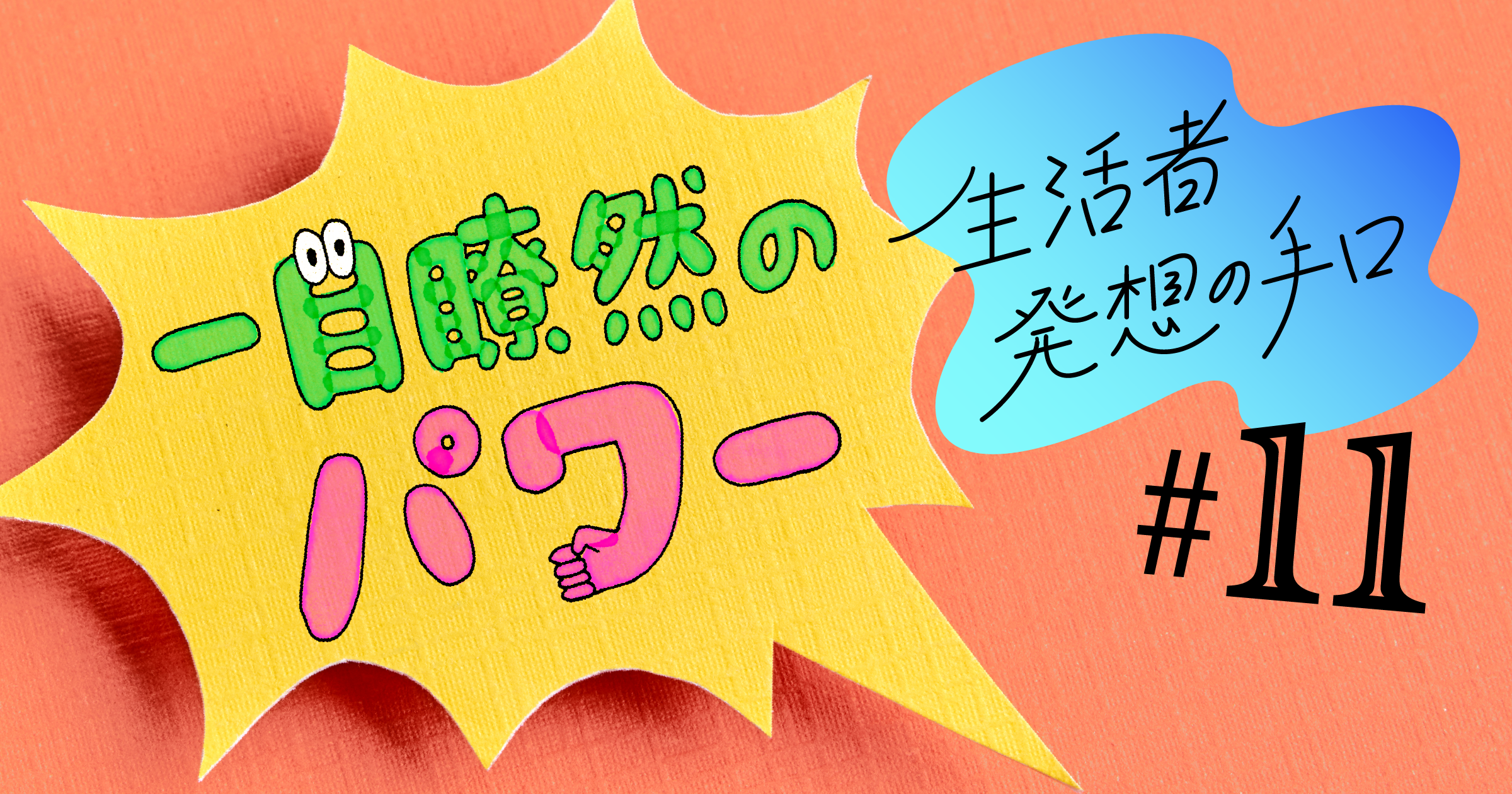南の島で出会った「ツノ」のある家 その秘密とは
2025.11.19

生活総研の研究員兼アートディレクターの鎌田です。
ここ数年、有休を取ってひとりでふらっと国内を旅しています。ひとり旅は自由です。予定を急に変えても誰にもとがめられず、お腹が空けば好きなときに好きなものを食べられます。無意識のうちに周りに気を遣わせてしまうらしい僕にとっては、このスタイルがいちばん性に合っています。なにより、誰とも折り合いをつけることなく、ただカメラに景色を収める孤独感が心地よいのです。
つい先日も石垣島へ行ってきました。行き先を確認もせず路線バスに飛び乗り、聞いたことのない停留所で降りたらあとはいつも通りにカメラ片手にひたすら街なかを歩き倒します。「タウンウォッチング」といえば聞こえはいいですが、実態はただの迷子です。その迷子の成果が「ツノの生えた家」でした。
建物の屋上から柱が数本、ぴょこんと突き出ています。ほんの少しだけ変わった佇まいで、視界の端をサッとかすめます。建設中でしょうか? でも家自体はかなり年季が入っています。資金が尽きて二階の建設を断念? どうにも気になり、意識してあたりを見渡すと、同じように柱を突き出した家や、外壁の一部をハリボテの柱に見立てているような家もありました。気になって仕方がないものの、その場では正体をつかめず、小さな違和感はいったん持ち帰ることにしました。
帰宅後さっそく調べたところ、わかったのは以下の三点です。呼び名、由来、そして今の事情。あのツノを持つ家は「ツノダシ住宅」というらしく、ツノの正式名は不明ながら「希望のツノ」「希望の柱」といった呼び名があるそうです。今は予算的に無理だけど、いつか階を増やして家を大きくしたい、あるいは自分では叶わずとも子どもが増築してくれますように……そんな願いを験担ぎとして柱だけ先に造っておくという風習が、戦後の鉄筋コンクリート住宅を中心に広がったそうです。なるほど、つまりツノは未完成のしるしではなく、未来への合図なのでした。とはいえ、持ち家率の低下や家族構成の変化で新たに造られることはほぼなく、さらに建築基準法の改正により、現在あるツノを実際の柱として使うこともできなくなっているようです。外壁を柱に見立てた「希望のツノもどき」は、今や純粋な意匠だそうで、風習も少しずつ姿を変えているようです。ツノはツノのまま、意味だけが少しずつ更新され、縁起物として残っているのです。見た目は未完ですが、内実は願いが詰まった完成形です。建物に宿る感情は、声高ではないぶん、なお深そうです。
感情を表現していくことへのリスクが高い現在においても、建物に思いをそっと託す沖縄の人たちの感情の表し方は、参考になるのではないでしょうか。
「ネタ会」とは?
生活総研では毎月1回、研究員が身のまわりで見つけた生活者についての発見や世の中への気づきを共有する「ネタ会」を開催しています。粒違いの研究員が収集してきた採れたての兆しをご覧ください。