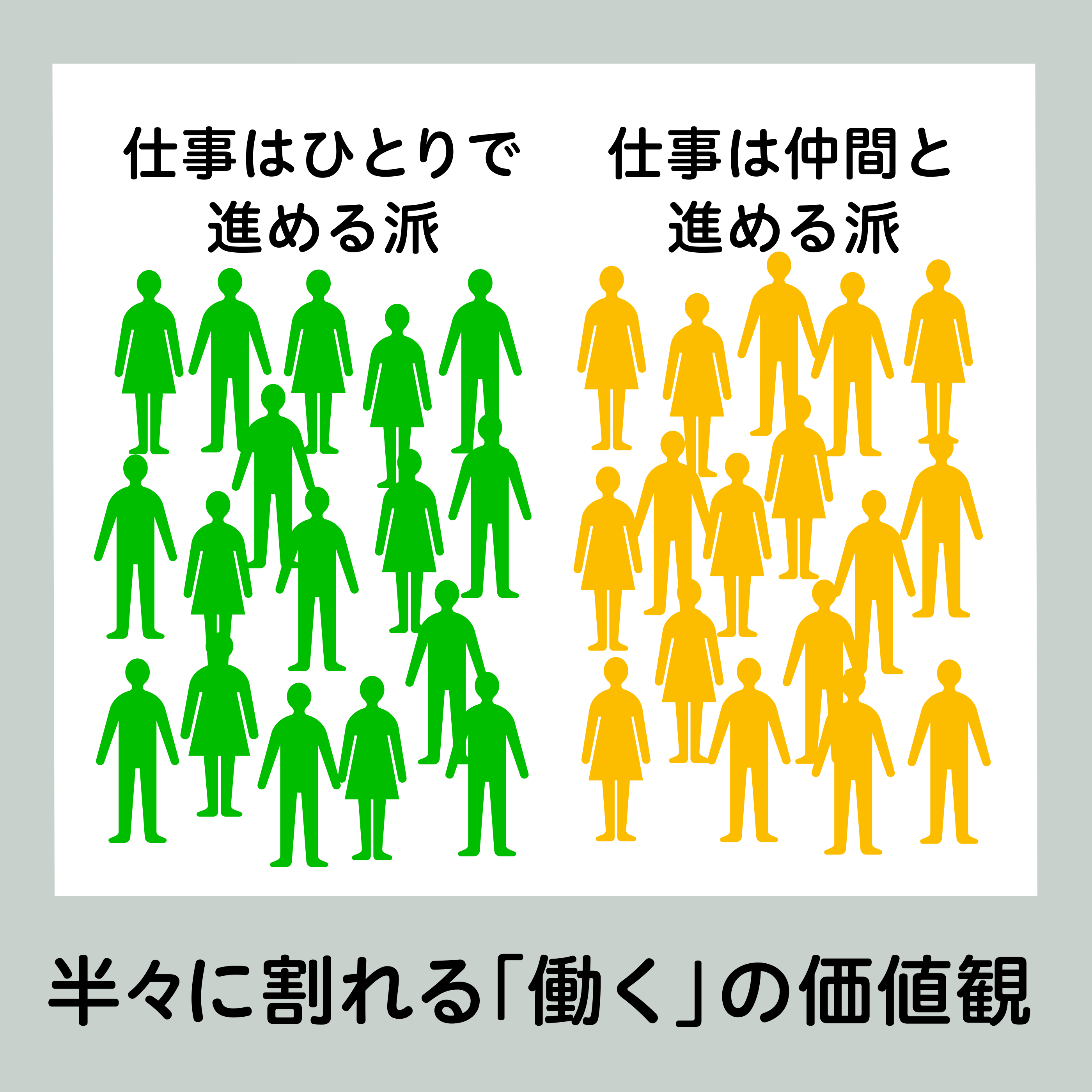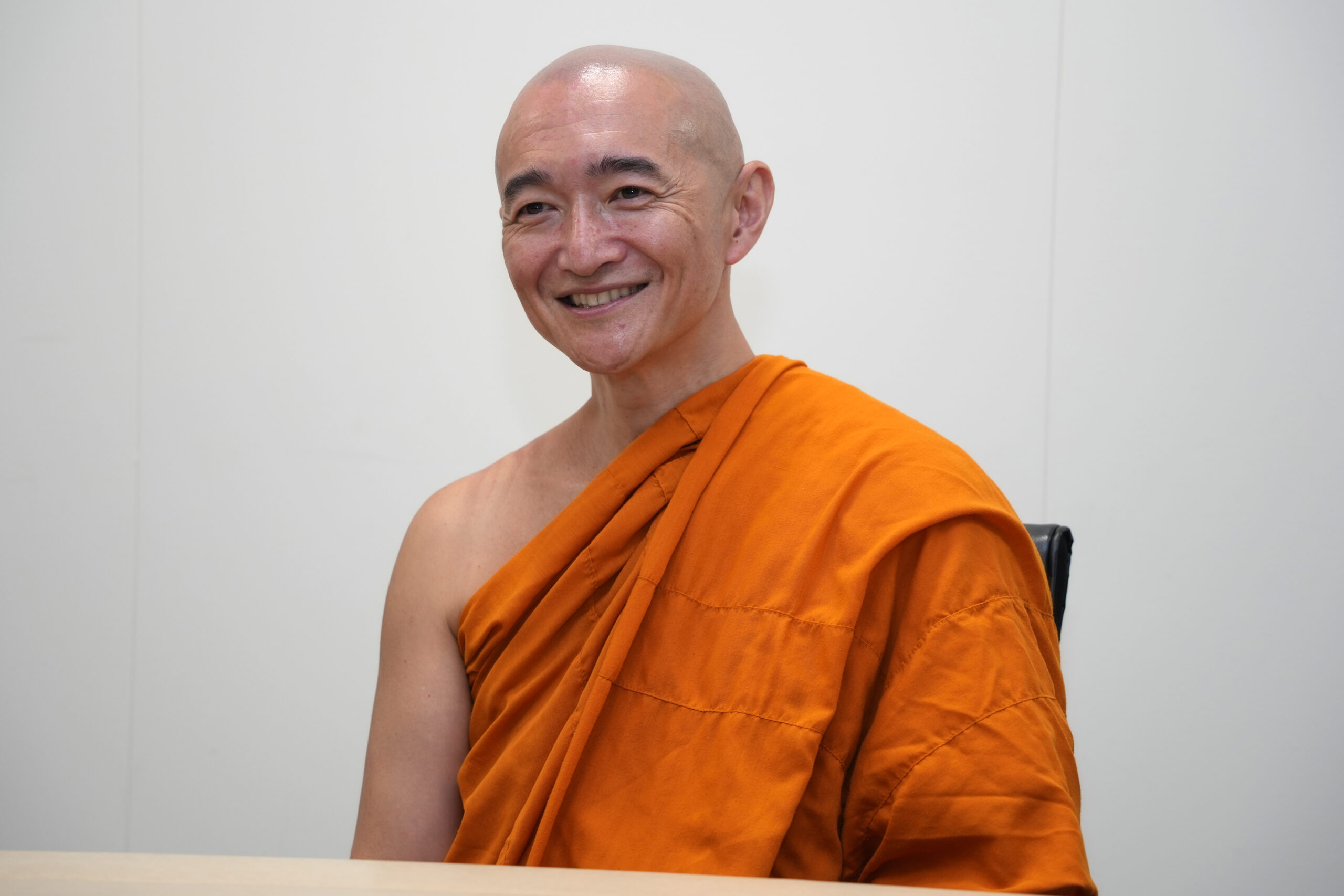自分で編集とカフェを始めて


会社での仕事を通じて、後の自分を準備した時期
お二人の現在の活動と、これまでの来歴を紹介していただけますか。
ケンゴ:二人とも新卒で同じ教育関係の企業に就職し、社内結婚しました。僕の独立と妻の転職で東京に住む意味が薄れたので8~9年前に逗子に移住し、同じタイミングで土曜日だけ間借りしてコーヒー屋さんを始めて、昨年自分たちのお店を持ちました。現在は夫婦で設立した会社で、編集・デザイン事業と飲食店の運営・開業支援事業の二本柱で活動しています。
マホ:私は大学で教育について学んでいたので、新卒で入社した会社でも、多感な小学生の教育に関わることになり、すごく意義を感じていました。マーケティングや営業などいろんな部署があるなかで、もの作りや手を動かすことが好きだったので編集の部署を志望したところ1年目から配属され、希望とやる気に満ちあふれていました。
入社後は、ミスが続いてしまって自分自身のテンションも下がり、仕事のモチベーションを維持するのが難しくなってしまった時期がありました。けれどもそんな私を見た別の上司が異動の機会を作ってくれたので、私も信頼できる上司に出会えたありがたみを感じ、仕事のやる気を少しずつ取り戻すことができました。
3~4年目くらいの時に社内公募があった新設部署に応募したところ、一番若手として参加することができ、そこでの仕事が私にとってひとつの転機になりました。それまで私は紙媒体の編集の仕事をしていましたが、応募したのは子ども向けのデジタル教材をつくる部署で、私は子ども向けの書籍を発行している出版社さんに企画を持ち込む営業チームに配属されたんです。
そこでの仕事を通して、他社との提携関係の結び方や、自分たちのやりたいことを通すための駆け引きを学ぶことができましたし、まだ3~4年目の若手のプレゼンを老舗出版社の方々に聞いてもらえたことで、度胸もつきました。そういった仕事を苦ではなく楽しくできたことで、「自分の適性はこっちにあるかも」と気づくことができました。
新規部署での仕事を経験した後で、マホさんは異業種に転職されました。きっかけはなんだったんですか?
マホ:会社に不満はありませんでしたし、仕事へのモチベーションも高かったのでネガティブ退職ではないんです。
もともと私は、学生時代から飲食やお店の運営に憧れを持っていました。彼とは25歳の時に社内結婚しているんですが、彼もコーヒーが好きだったり以前喫茶店で働いていたりして、「将来はそういう場を持ちたいよね」という話をしていました。
けれども当時の会社は業種が違うので、その先10~20年と勤めてもその夢に交差することはない。それに「自分の年次ならこれ以上ないだろう」という十分な経験をさせていただいたこともあり、飲食業という夢に近づくためにそれまでと180度違う、カフェやレストランのプロデュースをするベンチャー企業に転職しました。
大企業の編集や営業からベンチャーの飲食プロデュースへの転職は、畑違いもいいところです。カルチャーの違いもありましたし、ベースの知識がないから周りの話についていけないこともあり、最初は苦労しました。
ただ、当時あった焦りはどちらかというとポジティブなもので、「必死になって学んで、追いつかなきゃ」とか「全然勝手が違うけど、とにかくやるしかない」みたいなモードでしたし、友人・知人がまったくいない世界に飛び込みましたが、だんだん仲間も増えて楽しくなっていきました。
その会社に入社した時に、社長に「ゆっくり育ててほしいか、生き急いでいるか、どっちだ」と聞かれて、私は「自分の店舗を持ちたい」という目標があって転職しているので、「生き急いでます。3年ぐらいだと思ってます」にお伝えしました。そうしたら本当にあらゆる仕事を振ってもらって、がむしゃらに働いてその会社は3年で退職しました。
カフェから生まれる、仕事と繋がりの好循環
ケンゴ:僕のほうは、入社して3年目くらいで退職を意識しはじめました。ひと通りの仕事を経験して会社でできることがなんとなく分かった一方で、「会社の名前がなくなったときに何者でもない自分」を感じるようになり、「もっと自分自身の力をつけていきたい」という思いが強くなったんです。そして28歳で独立して編集・デザインの仕事をするようになりました。
同じ頃、東京での暮らしにいろいろ思うところがあり、離島などを含めて移住を検討しはじめました。湘南エリアは、それまでの生活や仕事の延長線上で欲しい暮らしが手に入る環境で、そのなかでも逗子に移住したのはご縁があった、肌が合ったとしか言いようがないですね。
移住先の逗子で週に一度のカフェを始めたのは、どんな理由があったんですか?
ケンゴ:東京にいた時にもすごく忙しい一週間を送っていましたが、土曜日に町のコーヒー屋で夫婦で過ごす時間がいい励みになっていました。その時間があるからこそ、仕事と生活のサイクルを安定して回せている気がしていたんです。「そういう場所を自分たちでつくれたら、町の反応や、自分たちのキャリアの上で面白いことが起こるかな?」と思って、逗子に移住した29歳のタイミングで土曜日だけのコーヒー屋を始めました。
コーヒー屋はミニマムのコストで人が集まれる場所で、だからこそ東京にいた頃の自分たちも週一で行けていました。海外の事例を見てもカフェから文化や人のつながりが生まれていますが、これがレストランだとムーブメントが生まれにくいかもしれない。そういった、「飲食ではない部分」の価値に惹かれていたのだと思います。それでも原点には、僕自身アナログな感じがすごく好きで、その一環としてコーヒーが好きなことがあると思います。
「自分たちの場所をつくって表現していきたい」とは東京にいたときにも思っていましたが、それができる場所や人との出会いがなかなかありませんでした。東京ではコーヒー屋が飽和している状況だったのに対して、逗子は今でこそコーヒー屋がたくさんある街になりましたが、僕たちが移住した頃は駅前の大型チェーン店らいしかなかった。そんな逗子の環境に可能性しか感じなかったので、「ここでやってみたい」と思いました。
逗子に移住してコーヒー屋を始め、かつ自分たちの看板で編集の業務も請けるようになったことで、以前の会社の名前がないところで仕事を始めて「いよいよ自分の人生が始まった」という楽しさがありましたね。ぼーっとしていたら潰れてしまうような弱小企業ですが、「日本は恵まれているから死ぬこともないし、なんとかなるんじゃないかな」とはずっと思っていました。
当初コーヒー屋は、繋がりを得る目的もあって「スポーツジムに1~2万円会費を払う」みたいな感覚で家賃を払って、土曜日の昼間だけ営業する形で始めたんですが、すぐに大きな反響がありました。ですからずっと「もっと拡大したいな」と思っていましたが、なかなか良い店舗が見つからずに6年近く経ち、昨年ようやく常設のお店を持つことができました。
お二人にとってカフェは「編集業のためのネットワーク作り」という位置づけになるのでしょうか?
ケンゴ:自分たちは両方本業のつもりでやっていいて、コーヒーもそれ一本で認められたいと思っています。
一方、お店と編集業のいい循環みたいなものもあります。お店に来てくれる人が雰囲気を気に入って話しかけてくれて、そこからデザインや編集の仕事に繋がったり、逆に編集の仕事で出会った人が店に来てくれてさらに繋がりが深まったり。そういうことが生まれていたので、間借りしていた時期も面白いバランスで仕事できていた感じがします。地域のコーヒーフェスを主催させていただくなど企画屋としてのイメージもどんどん育っていき、イベント業務を委託してもらう仕事もこの6年間で増えてきました。
逗子に移住して、「この町の一員である」という感覚が生まれた
お二人が移住して8年以上経ちましたが、改めて、逗子はどんな魅力がある町ですか?
ケンゴ:海が好きなので前から時々来ていたことが、逗子との関わりの始まりだったと思います。もしかしたら東京から一番近い海かもしれませんね。
チェーン店が少なくて昔のお店が残っていることも魅力でした。東京ではどの駅の景色も結構似てしまっているように感じますが、逗子には古さや独自性を感じました。駅を降りた瞬間に感じる、柔らかい海の風みたいな感覚もすごく好きでした。逗子は湘南の中でも特にコンパクトな街で、駅から海までの距離がすごく近いんです。こぢんまりした柔らかい街の雰囲気が好きでしたね。
人間関係でいうと、同世代ですごい仲良くなるようなことが本当に起こりやすくて、仕事の話をせずに飲食店とかで出会うことが多いです。
僕たちが会社員時代に都内に住んでいた頃は、純粋な町の友達がひとりもいなかったし、「この町の一員である」みたいな自覚も正直あまりなく、ただ暮らしているだけでした。けれどもこちらに来てからは「町の一員」という感覚があり、町を歩いていると挨拶したり、時には一緒に海に行ったり飲みに行ったりできるような人がいるので、「豊かだな」と感じます。
逗子には「この環境を選んで住んでいる」という人が多く、そこの共感が根底にあって住民同士の繋がりが生まれやすいようにも思います。「職場から近い都内の駅になんとなく住む」感覚ではなく、「少し視点をずらして自然のある町に住み、暮らしをもっと良くしていきたい」みたいな感覚がないと住んでいないんじゃないかと思います。住むことにひとつハードルがあることで仲良くなりやすい、みたいな面があるのかもしれません。
マホ:私は逗子に移住した後も会社でも週5フルタイムでがっつり働きながら、自分たちの表現として土曜日だけコーヒー屋を始めました。
それからすぐのタイミングで、自分たち夫婦の会社でやっている編集・企画・場づくりの仕事と、コーヒー屋という商いをしている視点をかけ合わせて、町を盛り上げて景色を作っていきたいという思いが湧き上がってきたんです。
そもそもこの町にはいろいろと活動している人が多いんです。例えば10年以上続いている「逗子海岸映画祭」という風物詩があったり、それ以外にも定期的に小さいイベントや活動が盛んだったり。
そういった、自分たちよりひと回り、ふた回り上の人たちが中心でやっているイベントや活動が町の素敵な景色になっていたけれど、自分たちの世代の活動にはまだこれといったものがないように感じました。そこで「自分たちも町のひとつの景色・文化に育つような活動を始めたい」と思うようになり、彼の話にもありましたが、駅前の神社を会場にコーヒーのイベントを主催しました。このイベントは1日3000人の集客にも繋がり、その後も隔年で続いています。
目の前にいる人のために、等身大で嘘のない仕事をしたい
2024年には間借りではない常設のカフェがオープンしました。仕事や生活に変化はありましたか。
ケンゴ:この時代はやっぱり「人が集まる場」があると強い気がします。お店を見てもらうことで飲食系のコンサルの事業に繋がったり、本棚を置いて、見てもらうことで編集に関わる価値を感じてもらったりと、会社としてのポートフォリオ・ブランディングの機能をお店に集約していきたいと思っています。
とは言え、開店して数ヶ月経った今もまだやり方を模索中で、無理をしてお店と編集の両方を回している感じです。大変といえば大変ですが、今は僕たち二人ではできないことを支えてくれる人たちが沢山いますから、もっと事業を拡大して、スタッフも増やすことで安定させていきたいですね。
マホ:彼は結構先々のことを考えながら動いているんですが、私は正直目の前のことに集中するタイプです。「遊ぶ時間も全力、働く時間も全力」というのが最近の傾向で、全力同士を混ぜているから余白がなくなっている感じもします。だから仲間をさらに増やして適材適所のことをお願いして、自分の時間を作っていくことも必要ですね。今の120%の働き方を10年は続けられないと思うので、「10年続く理想の働き方」を模索しています。
移住と独立を経た、現在のお二人の仕事に対する価値観を聞かせてください。
ケンゴ:サラリーマンの頃にやっていた仕事では、お客さんの顔が見えないことに違和感がありました。マーケティングでも教材制作でも、誰に対して作っているのかがずっと掴みにくかったんです。
いまは、「仕事とは、目の前の人と物だけを対象にする、手触りのあるものだ」とか「お店を開けたときに来てくれる人のために仕事をしたい」みたいに思っています。会社員時代と対比になっている部分があるかもしれませんね。僕は自分のことを知らない大多数に対する仕事よりも、お互いに関係性がある人たちへの仕事のほうが、ミニマルかもしれないけれど単純に楽しいし、やりがいを感じます。
それに僕たちは「ミッション・ビジョン・バリュー」みたいなところからは離れていて、「社会を変えたい」みたいな意識があまりないんですよね。
マホ:たしかに。結果としてそこに繋がるのはいいけれど。
等身大で暮らしながら60~70歳まで働き続けると考えたときには、暮らしていることがそのまま商いに繋がっていく形になったら理想だと思っています。
もちろん、いまやっているカフェもお客様を迎え入れる尊い場所ですが、将来的に自分たちのフェーズが変わっていくのに合わせた場の持ち方として、例えば宿をやって、「朝起きたらゲストがいて、交流していく」みたいな暮らしと融合した仕事が成立したら理想かもしれない、みたいなことを夫婦で話しています。
ケンゴ:メディアにしても、本とか、会話とか、レコードのような、時間をかけて情報を触れるもののほうが自分たちには合っているので、情報を消化することに疲れてしまわないところで生きていきたい。お店と編集・企画の両方の仕事をやってみて、お店で頂ける600円のほうが大きな仕事をしてもらう60万円より価値があるような気もしています。そういう綺麗ごとばかりじゃ生きていけないですけれど。
アナログなものを大切にして、ローカルな場所に身を置いて、変に背伸びをせず、等身大で嘘なく仕事をしていきたいです。