育てるデジタル、信じるアナログ
両利き化する生活者
デジタル化が進む中で、アナログ的価値を再評価する兆しを分析。双方に価値を見出し両利き化させる生活者の姿を発表。


「育てるデジタル」「信じるアナログ」を企業はどう活かすべきか。「両利き化」した生活者に対する新しいコミュニケーションや購買体験のヒントを構想してみます。
本研究のウェビナーで提示した「育てるデジタル」「信じるアナログ」という生活者の新しい欲求は、多くの聴講者様から「腑に落ちた」「共感した」との声をいただきました。一方で、「これをどうビジネスに活かせばよいか」という問いも多く寄せられました。ここでは、その研究知見を具体的なアクションにつなげるための、業界別の発想例をご紹介します。
サイトに意図的に「バグ」や「文字化け」を発生させ、クリックすると開発者の言い訳めいたストーリーと共に、まったく予期せぬ商品ページに飛ばされる仕掛け。例えば、「担当者が猫にキーボードを踏まれてしまい……」というテキストと共に猫型癒やしグッズの特集につながるなど。効率的な検索やレコメンドに疲れた生活者に対し、エラーすらも楽しめる遊び心と「#ムダを堪能したい」という欲求を満たす、予定不調和な出会いをデザインします。


届けられた食材を使った料理写真や感想をユーザーが投稿すると、その内容がAIによって解析され、次に届く商品の物語や食材や調味料が微妙に変化するサブスクリプション。例えば「辛口の感想」が多ければ次は「リベンジさせてください」という挑戦的な物語が届き、「意外なアレンジ」が投稿されれば生産者がそれにインスパイアされた番外編が届くなど。生活者を物語の受け手から、物語と商品自体を変化させる参加者へと変え、「#正解を迷いたい」という欲求を刺激します。


同じ場所を、異なる季節や時間帯に繰り返し訪れることを促すアプリです。ユーザーが特定の「定点」を登録すると、訪れるたびに同じ画角での写真や、そのときの感情メモ、周囲の音などを記録できます。アプリはそれらの記録を重ね合わせ、時間や季節の移ろいをタイムラプスのように見せたり、自分の感情を振り返れるようにします。体験に繰り返し向き合うことで「情報を自分の中で熟成させ、新たな解釈を生む」という「#感情を深めたい」欲求に応え、再訪によいタイミングを通知し旅の体験を深めます。


顧客参加型のリメイク工房で、あえて「失敗」や「不完全さ」をデザインとして取り入れる。顧客が初めてのミシン作業で歪んでしまったステッチや、誤ってつけてしまった染料のシミなどを、プロの職人が「それも味です」と肯定し、むしろその部分を活かすデザインを施します。完成品には、その失敗の物語を記した小さなタグを付ける。完璧ではない、自分だけの「#想いを刻印したい」という体験が、唯一無二の愛着を生みます。


顧客の「忘れてしまった大切な記憶」というテーマで調香するサービス。カウンセリングを通じて、顧客自身も忘れていたような幼少期の風景や感情の断片(「雨上がりの土の匂い」「祖母の化粧台の香り」)を一緒に探り当て、それを香りで再現します。これは、自分でも気づかなかった自己を発見する体験であり、「#出会いを運命にしたい」という欲求を、自分自身の内面との出会いへと昇華させます。


ファンが「その曲を聴いて思い浮かべた風景」や「曲が生まれたきっかけの場所だと(勝手に)解釈した場所」の写真を投稿し、それを集めて公式の「楽曲巡礼マップ」をデジタルとアナログ(ZINEなど)で制作。アーティストが提供した正解ではなく、ファンの解釈や熱量が集まって新たな「聖地」が生まれていくプロセスを共有します。ファン同士が互いの解釈を共有し合うことで、「#味方の純度を高めたい」という欲求を、コミュニティのひろがりへとつなげます。

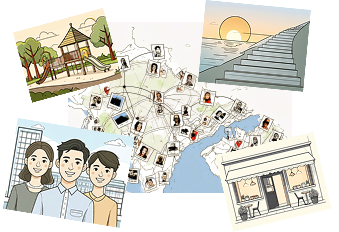
「育てるデジタル」「信じるアナログ」という新しい生活者の欲求は、これからのビジネスにどのような視点をもたらすのでしょうか。メディアと購買、それぞれの専門家の声からヒントを探ります。

博報堂メディア環境研究所
所長
山本 泰士
近年、特に10代の若年層を中心に、履歴ベースのレコメンドアルゴリズムをハック、つまり意図的に操作し、アルゴリズムによる提案の枠組みから自ら離脱しようとする脱アルゴリズムとでもいうべき動きが見られます。たとえば、自分が頻繁に「いいね」したり視聴している内容が自動的に推薦される仕組みについて、若年層は非常に高い理解を示しています。そのため、あえて新しいコンテンツとの出会いを求めて、おすすめ動画を視聴せずに更新し続けたり、全く異なるジャンルの動画にも「いいね」を付与して情報の幅を広げるといった行動が取られています。さらに、一部のユーザーはアカウント自体をリセットすることで、未知のコンテンツとの遭遇を意図的に増やそうとしています。

博報堂買物研究所
所長
垂水 友紀
生活者がセレンディピティを強く求めている点は非常に顕著です。セレンディピティについて重要なのは、生活者側も、受動的な姿勢では得られず、自ら行動を起こし、好奇心を持つことですね。企業が取り組むべきこととしては、こうした生活者の好奇心を刺激し、活動範囲が自ずと広がるような施策を展開することが、今後ますます重要になると考えられます。
