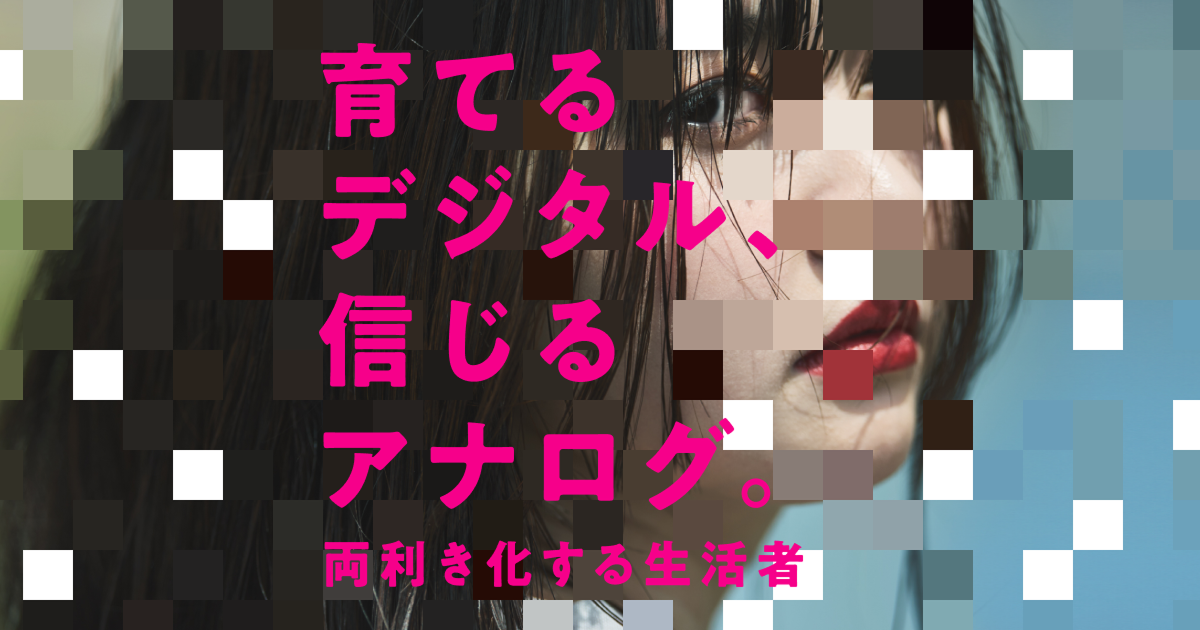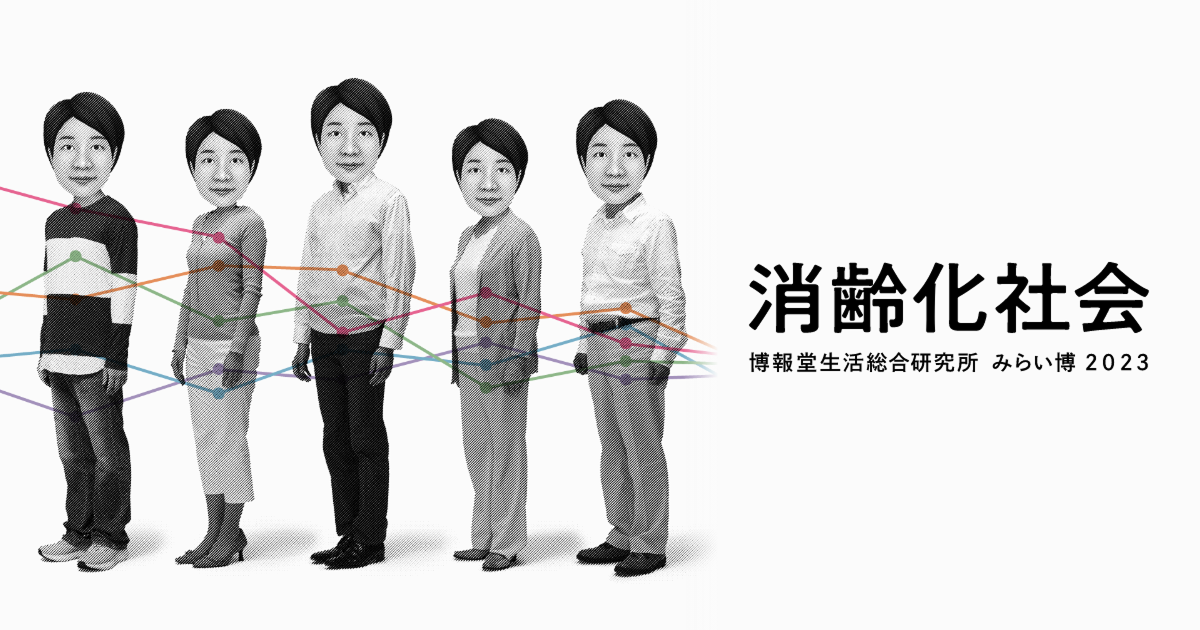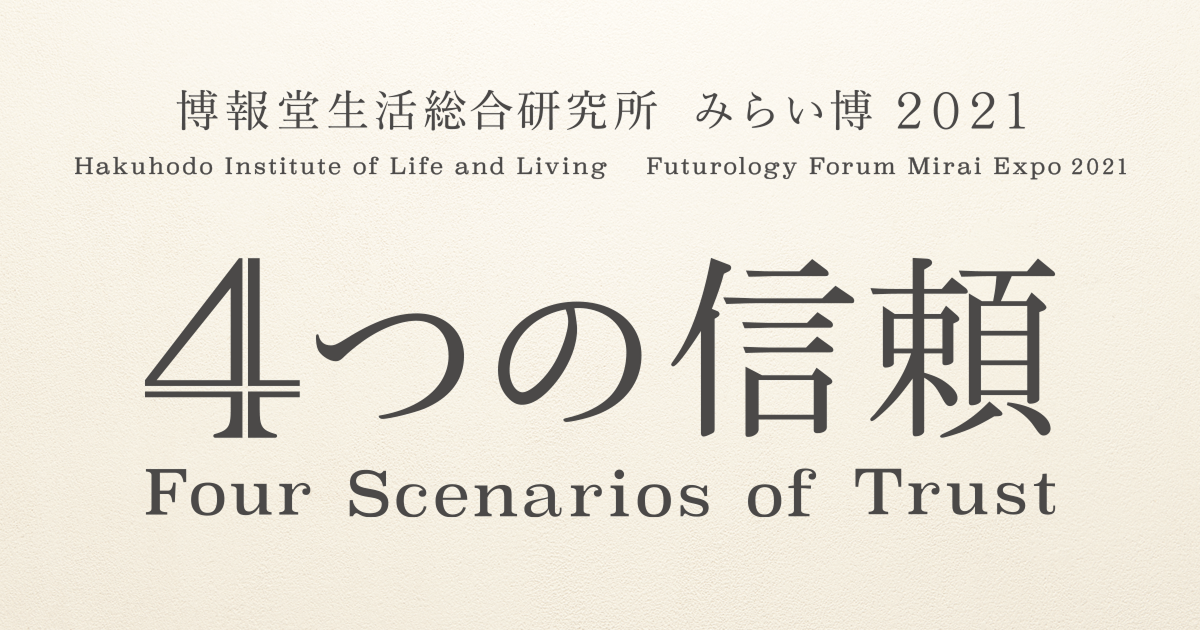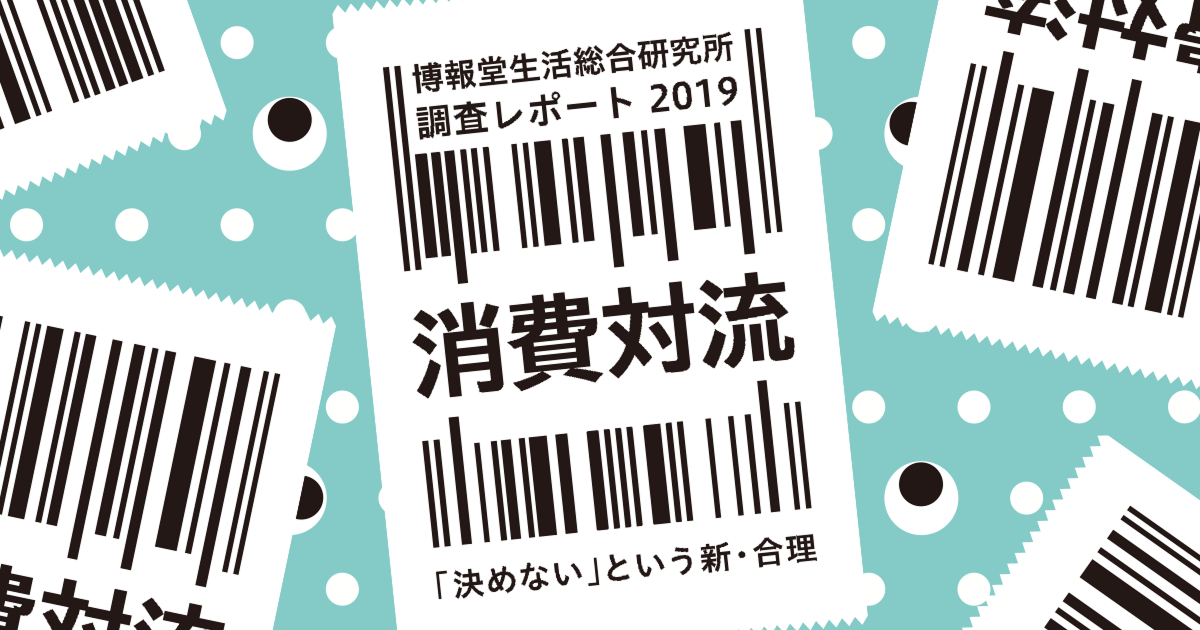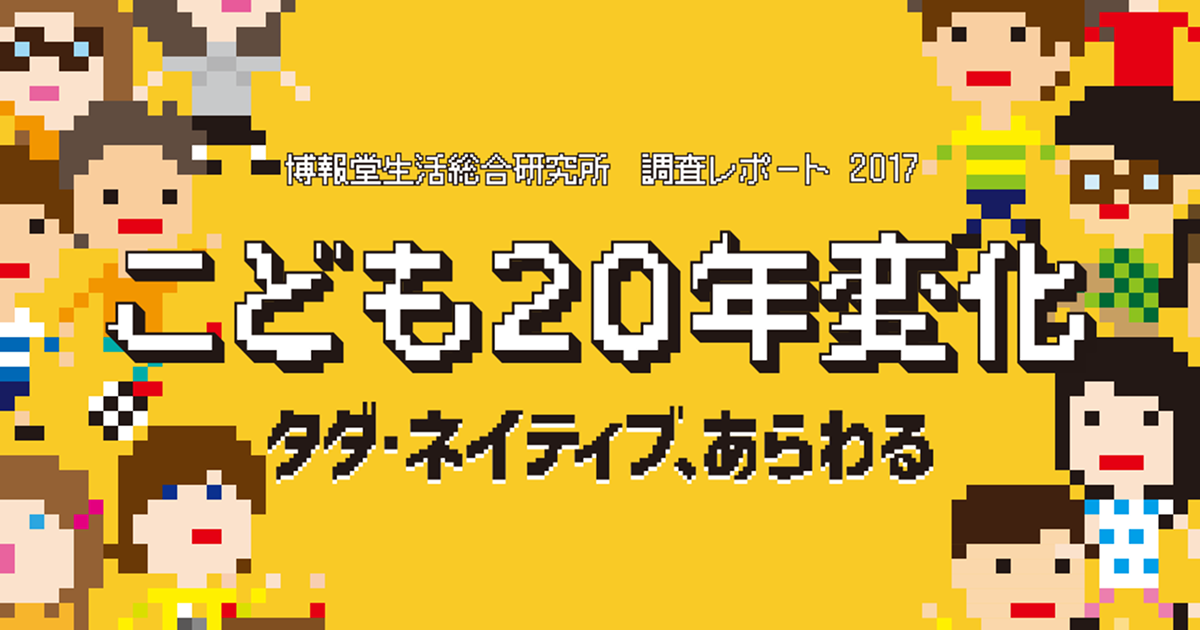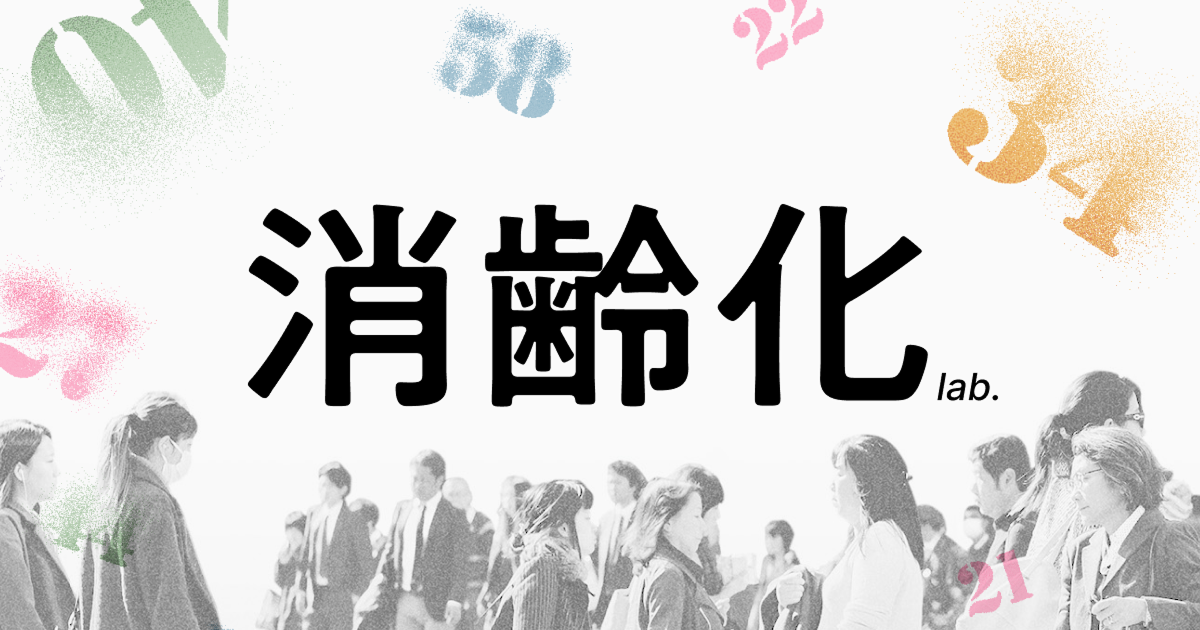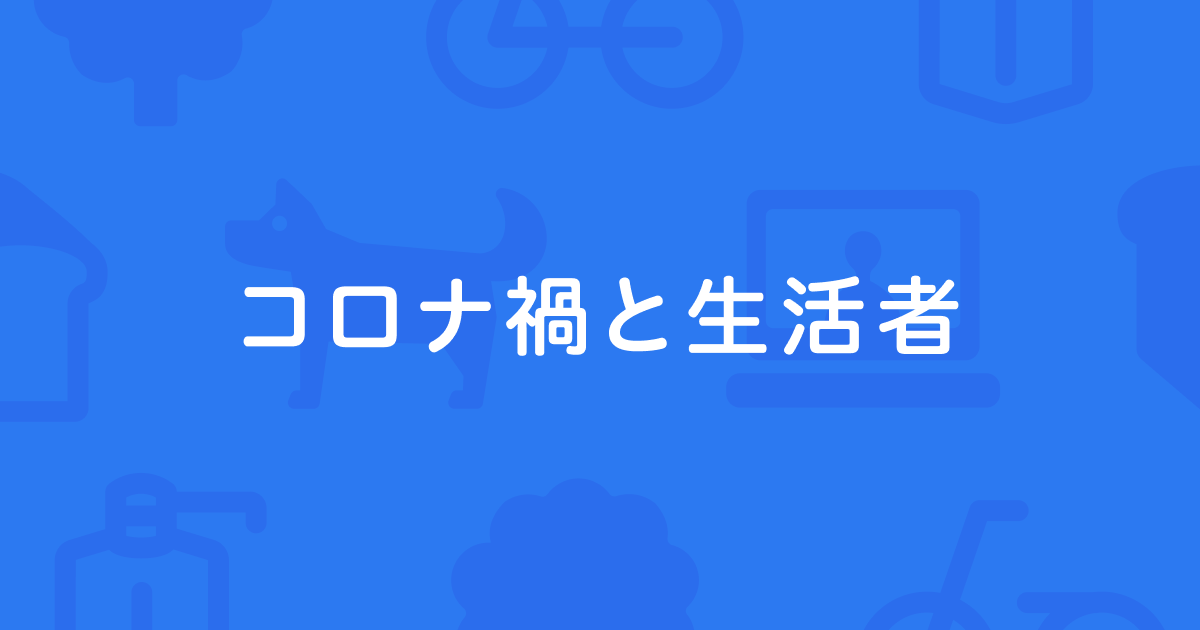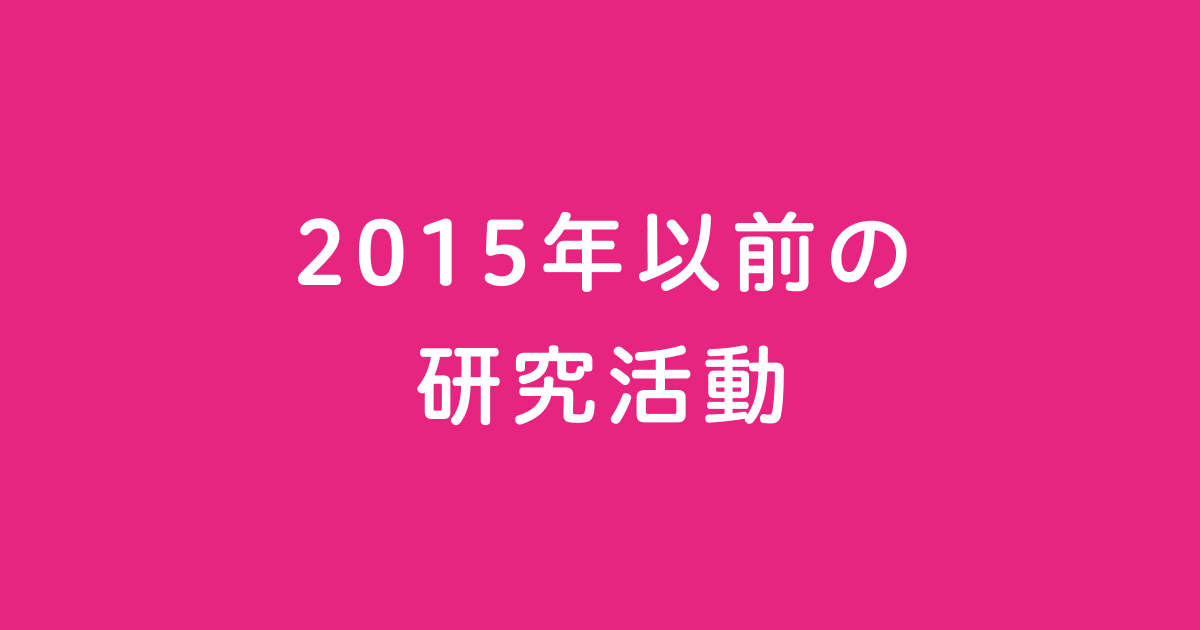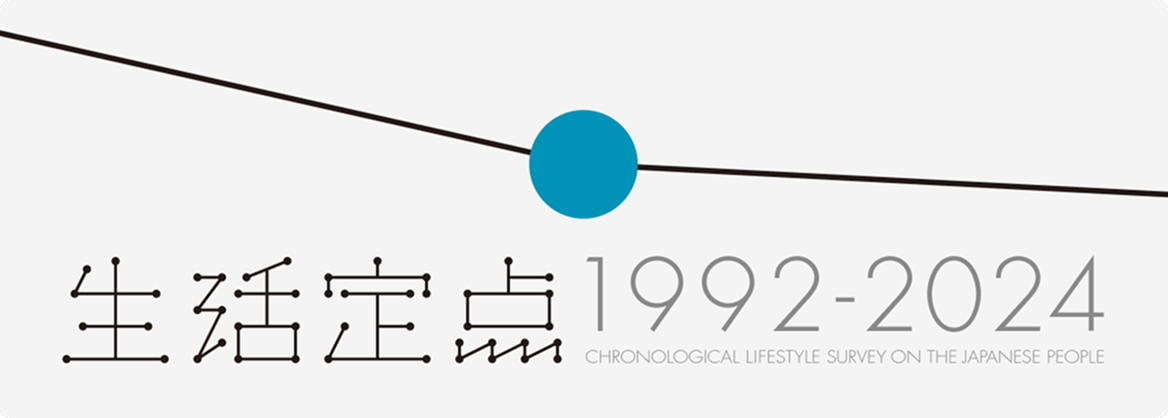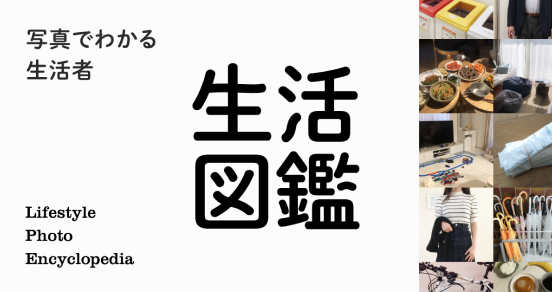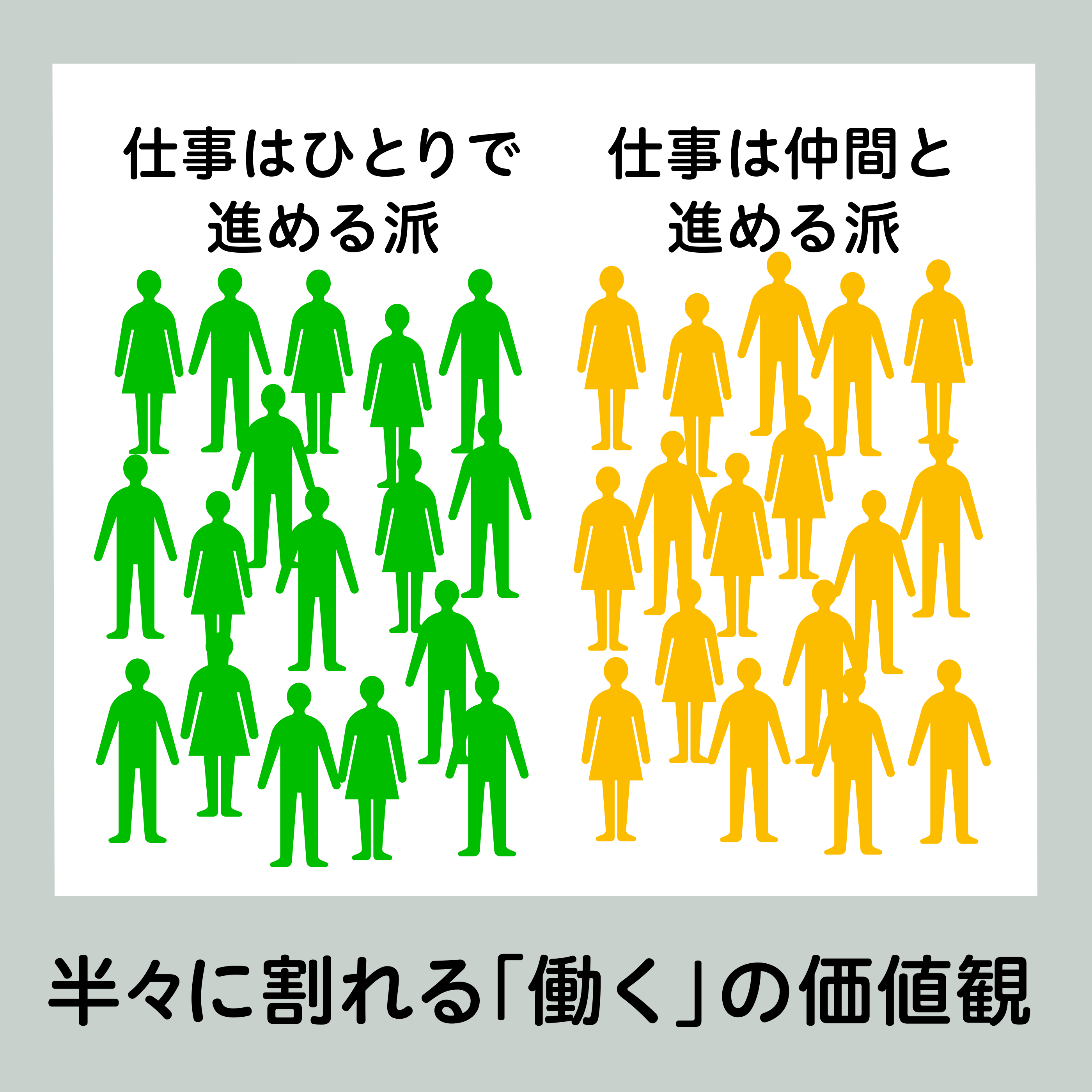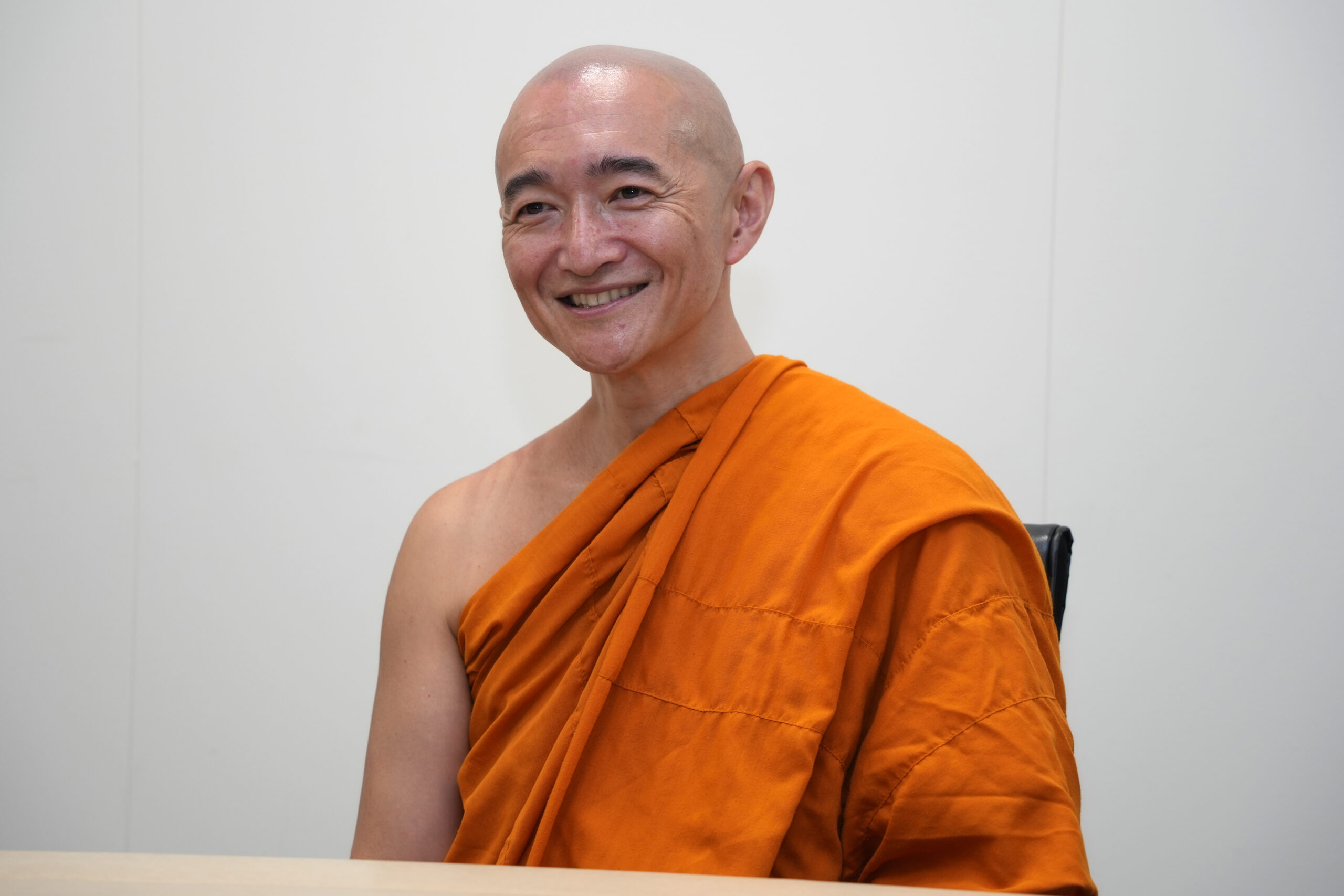自由に生きたくて


宮城から飛び出して、西日本をぐるぐるしてた頃
ウジイエさん、ざっくり自己紹介と、これまでの歩みを聞かせてください。
ウジイエ:宮城県生まれで、今は東京にいます。これまで沖縄、福岡、京都と、西日本を転々としながら、スパイスを使った料理を作ってきました。カレーをメインに、間借りとかポップアップの形でお客さんに食べてもらったり、スパイス料理のことをnoteでも発信しています。
もともとは仙台の隣町、いわゆるベッドタウンで育ちました。ちょうど就職氷河期ど真ん中で、派遣で工場のライン作業とかしてたんですけど、これが全然向いてなくて。それで、弟とふたりで沖縄に移住したんです。名護でファストフード店のバイトをしながら、ゆるく暮らしてました。21〜22歳くらいの頃ですね。
そのあと、南城市の佐敷ってところに引っ越して、教会に1ヶ月くらい住まわせてもらったんですけど、周りに民家もほとんどなくて。そんな環境だから、2階でドビュッシーを爆音で流したりして(笑)。でも、さすがにそんな生活もずっとは続かなくて、那覇に出て4〜5年働くことになりました。
最初は短期の営業の仕事だったんですけど、意外と成績がよくて、そのまま正社員にしてもらって。気づけば年間で営業成績1位になったりして、「あ、社会に認められたな」って初めて思いましたね。
その後、会社の本部から「特別販売員をやってみない?」と声をかけてもらって、数ヶ月ごとに福岡、神戸、熊本、久留米…と、西日本を転々と回っていました。
福岡の居酒屋で、“できないことをできるようにする”修行
福岡でカレー屋さんをはじめる前は、居酒屋で働いてたんですよね?
ウジイエ:そうなんです。販売員を1年くらいやって、「もういいかな」って思ってた頃に、たまたま福岡の大好きな居酒屋がバイト募集してて。27歳のときから3年くらい、ホールスタッフとして働きました。
この居酒屋、以前お客さんとして行ったときに何を食べても美味しくて、「こんな店で働けたらいいな」と思ってたんです。実際に働いてみたら、先輩たちはみんなかっこよくて、すごくいい職場でした。でも、整理整頓とか気遣い、瞬発力とか、生活力が求められる仕事で、自分にはその辺が全然なくて。しょっちゅう怒られてました(笑)。
でも、僕は「できないことをできるようにする」って気持ちで生きてきたので、怒られるのも含めてすごくいい勉強になりましたね。あと、先輩たちは人格もできてて、仕事終わりに飲みに連れていっても仕事の話は一切しないんです。ある日、店長と板前の人に自分がよく怒られる話になって、僕が「なんで僕のこと怒らないんですか?」って別のえらい先輩に聞いたんです。そしたら「ナオキは感じ入るタイプだから、あのふたりに怒られてもう十分だろ。それ以上言うことないよ」って言ってくれて。ちゃんと人を見てコミュニケーション取ってくれる、そんな職場でした。
カレーでみつけた自由と創造性
カレー屋さんをはじめたきっかけって何だったんですか?
ウジイエ:居酒屋の仕事はすごく良かったんですけど、30歳を過ぎてこのままアルバイトを続けててもいいのかなって思っていたんです。そんなとき、自分の味覚とか嗅覚がわりと良いことに気づき始めて、「これ、手仕事が追いついたら、食べていけるんじゃないか?」って思ったんです。
それと、福岡ってスパイスカレーが盛んな街で、カレー屋の先輩たちが自分の好きなように生きてる姿を見てたんですよ。例えば、福岡にスパイスカレーを流行らせた“カレーの神様”って呼ばれてる人がいて。その人、病気でお店を譲ったんですけど、手術したら思ったより回復しちゃって(笑)。で、自分が譲った店の軒先でスパイスを売って生計立ててるんですよ。その生き方を知って、「あ、そんなのもアリなんだ」って衝撃でした。
カレーって、そういう自由な空気があるんですよね。しかも、他の料理だと修行が必要だけど、カレー屋は突然はじめてもそこまで違和感がない。僕も調理が全然できない状態からスタートしたんですけど、受け入れてもらえたのはカレーだったからかもしれません。
EMERADAを始めたら、SNSもカレーも楽しくなってきた
ウジイエさんが開いたEMERADAは、福岡でもすぐに話題になりましたよね。
ウジイエ:「やる!」って決めてから1ヶ月半くらいで、スナックを間借りしてオープンしました。最初はやっぱりそんなにうまくカレー作れなかったんですけど、やっていくうちに少しずつ美味しくなっていって。SNSでの告知も楽しみながらやってたら、だんだん注目してもらえるようになりました。
ただ、途中で「アイツ、SNSの使い方が上手いだけじゃん」みたいに言われて、けっこう落ち込んだこともありました。料理人の先輩たちは、黙々と料理だけ作ってるのに、自分は素人なのにいろいろ発信してていいのかな…って、ちょっと後ろめたかったんですよね。
でも、今振り返るとSNSで発信するのもひとつの才能だし、そもそも昔はSNSがなかったから先輩たちはやってなかっただけだなって。あのとき無理に萎縮しなくてもよかったんだなと思います。
カレーで発見した自分の“職人性”と感性
その後、福岡から京都、東京へと拠点を移していきました。その理由は?
ウジイエ:それまでずっと「才能ない」「ダサい」って言われて生きてきたんですけど、カレーを始めたことで、自分の中に“職人性”とか“創造性”があるんだなって気づけたんですよ。でも、福岡ではそういう“感性”と“飲食”が組み合わさった仕事って、あんまり評価されにくいところがあって。存在感は上がったけど、売り上げがついてこなかったんですよね。
カレーって、みんな「今日は○○のカレー食べた」みたいなスタンプラリー的な食べ方をするところがあって。自分がやっている事とそういう空気が、なんか融合できませんでした。
それで、ちょっと場所を変えてみようとと思って、京都に行きました。文化的な事への極端な憧れがあったのかもしれません。ちょうどコロナの緊急事態宣言中だったので、結局あまり大きな活動はできなかったんですけど……。
あと、京都ではアイスクリーム作りの天才と出会ったんですよ。その人とは、これまで自分がいた場所では経験できなかったような感性や物の見方を共有できて、お互いに理解し合えてすごく楽しかったです。
で、その後、東京に出店しないかって話をもらって、京都から東京に移りました。お店は評判をもらえたんですけど、契約の問題で短期間で閉めることになって。けっこうストレスも多かったけど、その間にアーティストの方と熱海で食とアートのイベントをやったり、いろいろ実験的なことができたのは良かったですね。メディアにも結構取り上げてもらえましたし。
noteでスパイス料理の情報を売る理由
カレー屋さんのほかに、noteでスパイス料理の情報も販売してますよね。それはどうして?
ウジイエ:スパイス料理って、みんなが思ってるよりずっと深くて幅広いんですけど、日本ではけっこうステレオタイプな話ばかりされがちなんですよね。本当はもっと油を使うレシピなのに、日本のレシピでは控えめに書かれてたり。「なんで美味しくなるのか」って根本的なところまで突っ込んだ情報って、あんまり出回ってない。
僕もカレーを学び始めたときに「え、こんなに情報がないの?」って驚いたんです。だから、逆に自分で得た知識をnoteで発信するようになりました。コアな内容なので、そんなに多くは売れないけど、ちょっと高めの値段設定にして、そのぶんほかでは絶対に手に入らない情報を載せてます。
これからも、インドとか現地に行ってガンガン情報集めて、スパイス料理の「知られていないこと」や「誤解されていること」を発信していくつもりです。技術や料理の構想なんかも含めて、全部まとめて公開していきたいですね。
不労所得より「ちゃんと汗かく仕事」が好き
noteでの情報発信は、収入源としても考えてるんですか?
ウジイエ:そうですね。料理を作ってお金をもらう以外にも、収入源を作りたいって気持ちはあって。でも、株で稼ぐとか、そういうのは自分には合わないんですよ。汗をかかずにお金を稼ぐのが気持ち悪くて。働かないと、風呂も気持ちよくないし、ビールも美味しくない。
原価100円のものを10万円で売るのとか、一歩も動かずに毎日100万円入ってくるみたいなのは、やっぱり異常だと思ってるんですよね。労働からどんどん離れていく気がして。それに、僕はコロナ禍以降ちゃんと働けてないから、今はむしろ働きたくてしょうがない。社会に貢献できたって実感がないと、罪悪感で眠れないこともあります。
情報発信も、その“社会貢献”の一環ってことですか?
ウジイエ:そうですね。もともと、すごく好奇心が強いんですよ。でも、東北の田舎出身だから、インターネットが広まる前は情報がなくて。知りたいことを知れないストレスがすごかったんですよ。カレーのことを調べ始めてからも「こんなに情報がないのか…」って何度も思ったし。だから、同じ思いを他の人にしてほしくなくて、noteで発信してるところはあります。
「遊び」と「好き」が、次のアイデアを生む
ウジイエさんの“働き方”についても聞きたいです。カレー屋さんをはじめてから、労働観は変わりましたか?
ウジイエ:変わりましたね。雇われてた頃は、「できないことをできるようにする」ために働いてて、だいたい怒られてました(笑)。得意なことも特になかったけど、新しいことを知るのは好きだったから、そこが自分の根っこにあるんだと思います。
EMERADAをはじめてからは、「働いてる」「遊んでる」っていう境界線がなくなってきました。間借りしてた頃は週5で働いてたけど、今は「この日は働かなきゃ」みたいなのはなくて。気が乗らなければ働かないし、やりたいことをやってるから精神的にはすごく楽です。
それに、働いてない間、つまり「遊び」の時間に得た着想が、次の料理のアイデアになったりしてます。たとえば、京都にいたときに「振動」って考え方を手に入れたんですけど、それを料理に取り入れるって誰もやってなかった。そういうのが評価されて、アーティストの方達と一緒にイベントをする事も増えてきました。
でも、仕事ってどうしても“義務”的な部分もありますよね。そこはどうしてますか?
ウジイエ:僕が一番怖いのは、料理が義務になって、飽きちゃうことなんです。だから、仕事を「やらなきゃいけない」って思うときは、楽しめる理由をちゃんと作るようにしてます。無理に力んじゃうと、どんどんつまらなくなっちゃうから。
カレー屋の“働き方”をもっと良くしたい
最後に、これからの目標を教えてください。
ウジイエ:カレー屋って、単価が低いんですよ。だから、ランチタイムに何杯売れるかが勝負になりがちで。でも、僕が今まで関わってきたカレー屋さんって、繊細な人が多いんです。そういう人たちにとって、たくさん作ってたくさんの人と会う働き方って、メンタル的に合わないことも多いんじゃないかって思ってます。
だから、もっと無理なく続けられる、新しいカレー屋の働き方を打ち出したいんですよね。カレー屋がもっと良くなる方法、考えていきたいです。