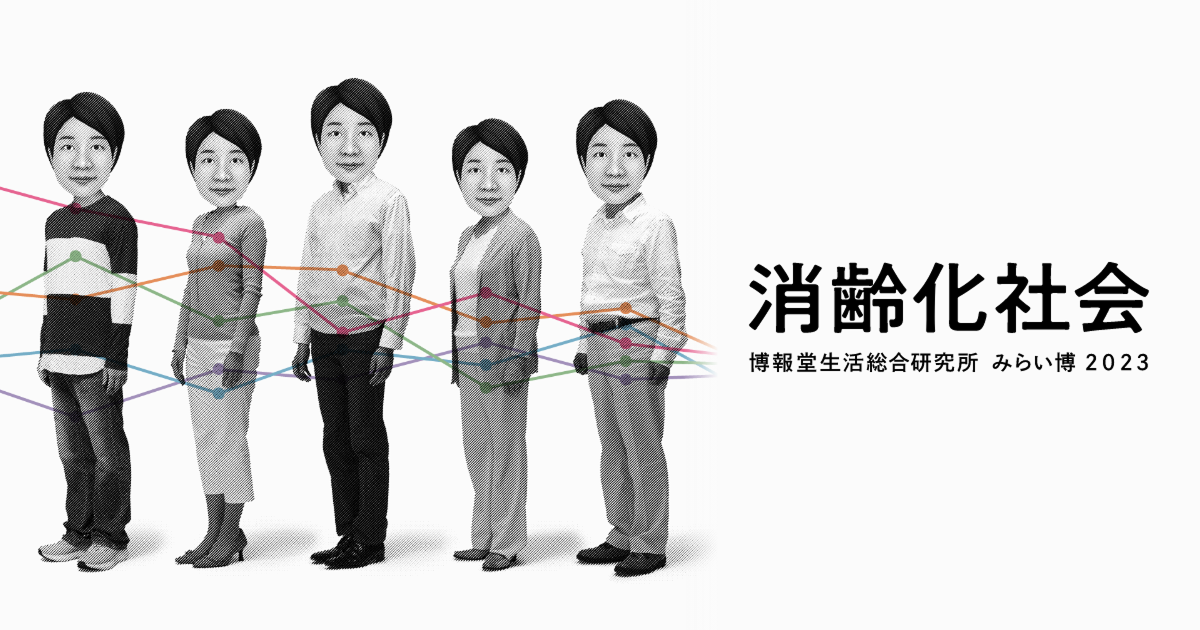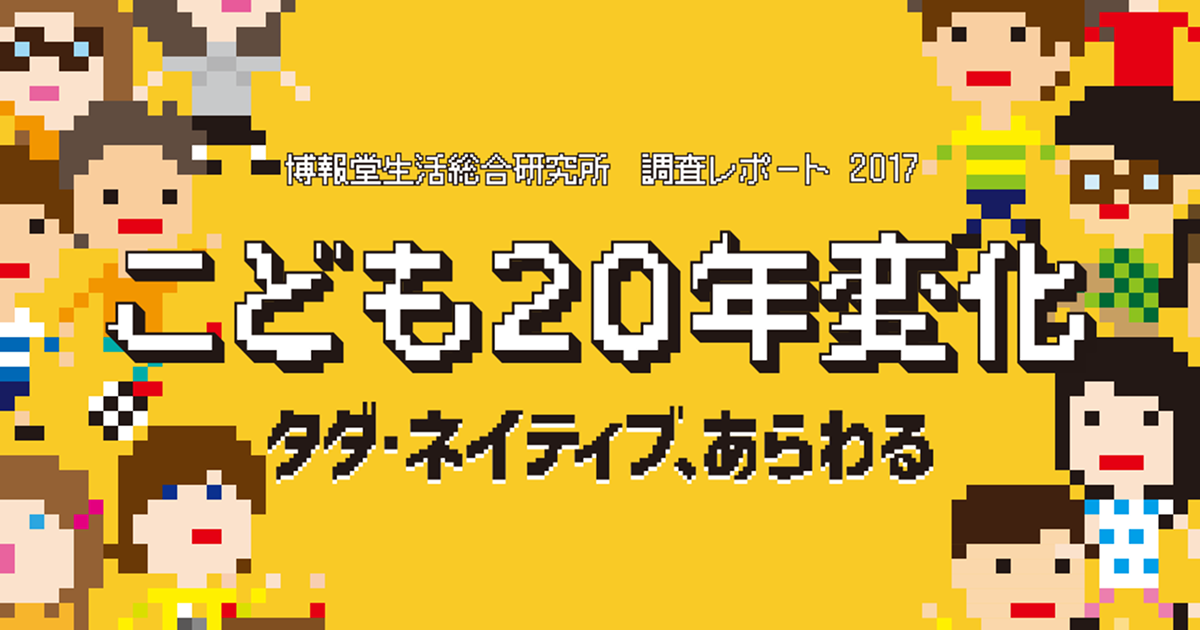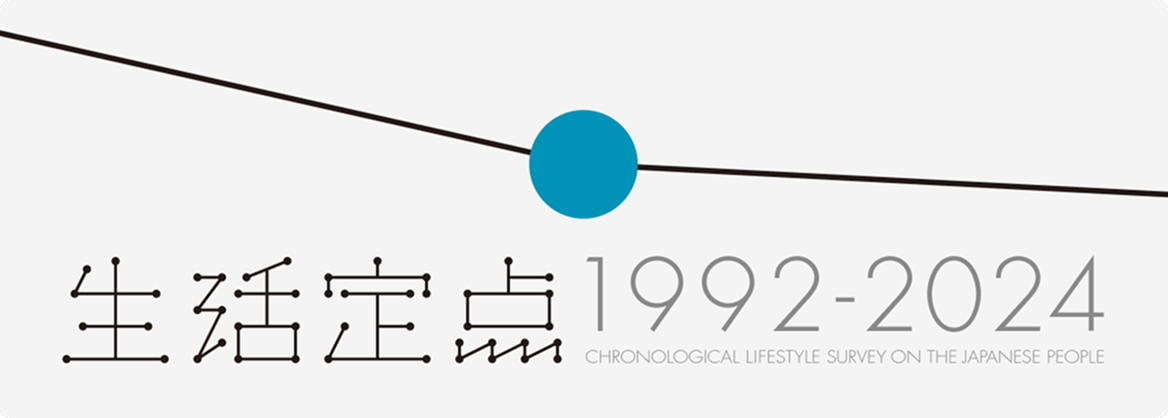「生活圏2050プロジェクト」 #06
パワー・オブ・メイキング〜「ともに創る」ことで社会を修復する~(前編)
アート、デザイン、建築の領域を越境しながら、都市空間やコミュニティが抱える社会的課題を修復する様々なプロジェクトに取り組んでいる、英国の建築家チーム「ASSEMBLE(アッセンブル)」。 2015年にリバプールの荒廃した住宅街の再生に地域住民との協働で取り組んだ「グランビー・フォー・ストリーツ」プロジェクトによって、英国の現代美術アーティストに授与される「ターナー賞」を建築家チームとして初めて受賞し、その存在は日本でも知られることとなりました。「アートが日常を変える」をテーマに、彼らが実践してきたワークショップ手法が体験できる展覧会を開催するため来日したアッセンブルのメンバー、アダム・ウィリスさんに、アート・建築・デザインを通して生活圏を再生させていくためのアプローチについて、お話をお伺いしました。
人口減少社会における新たな生活文化と経済(エコノミー)の創出を構想する「生活圏2050プロジェクト」。プロジェクトリーダーを務める鷲尾研究員が、既に今各地で始まっている新しい生活圏づくりの取り組みを伝えます。


“Folly For a Flyover (2011)” © ASSEMBLE
「本当は、私たちは何を始めるべきなのか」
資生堂ギャラリー(東京・銀座)での展覧会のために来日した英国の建築家チームASSEMBLE(アッセンブル)。その展示作品の制作のために滞在している栃木県・益子町を訪ねました。
鷲尾:
「グランビー・フォー・ストリーツ(Granby Four Streets)」プロジェクト(※1)を始め、あなた方が手掛けられてきたプロジェクトでは、地域コミュニティに入り込み、住民の人たちと一緒に、その場所が持っている可能性を拾い上げながら、住居、道路、公園、生活環境を「ともに創りなおす」というアプローチが一貫しています。
2年前に東京・表参道で行われた展覧会ではそのプロジェクトの様子が、1/1スケールのような等身大の感覚で体験でき、修復された「ケアンズストリート」の部屋の中や、木漏れ日のさすウインターガーデンの中に、まるで立っているような感覚を覚えました。親密さや懐かしさ。そこに軽やかなデザインが溶け合っていて、とても新鮮で明るい気分にさえなりました。親密感とは、その場所が持っている「記憶」とも言い換えられるかもしれません。あの明るい陽差しのような感覚はなんだろう、どうしてあのように感じたのだろう。それ以来、よく思い返しています。プロジェクトは今も続いているのですか?
アダム・ウィリス氏(「アッセンブル」メンバー、以下アダム):
はい、今も。ここ益子にも、「グランビー・ワークショップ」(※2)のメンバーと一緒に来ているんです。
鷲尾:
2015年にターナー賞(※3)を受賞されたことで、私もあなた方の存在を知ったのですが、こうした領域を超えていくような創造性をどのように捉え、評価し、育てようとするか、その文化やアートの捉え方についての違いについて、日本人としてとても考えさせられました。
アダム:
アートやデザインがどのように社会の再生につながっていくのか、そうしたテーマがアジェンダとしてあったとも聞いています。私たち自身も驚きました。


“10 Houses on Cairns Street (2013-2017)” © ASSEMBLE
鷲尾:
「アッセンブル」は、大学の同級生たちが集まって生まれたチームだとお伺いしています。現在は何人のメンバーがいるのですか?
アダム:
チームは16名です。私もそうですが、ケンブリッジ大学の建築学科で共に学んだ仲間たちが12人、13人。それから別の建築事務所で働いていた仲間たちが、初期のプロジェクトを通して、こちらに参加するようになったりして。そんな風に「アッセンブル」は緩やかに生まれていきました。ただ結成当初から人数はあまり変わっていません。
鷲尾:
「アッセンブル」としての活動が始まった当初、何か具体的な目標やテーマなどはあったのでしょうか?
アダム:
紙に書き留めたようなヴィジョンや哲学、あるいはマニフェストのようなものはありませんでした。私たちらしいアプローチがあるとすれば、それは仲間たちと一緒にプロジェクトを行っていった過程を通し、何年にもわたって徐々に進化し発展していったものだと思います。

“Art on the Underground (2015-2017)” © ASSEMBLE
鷲尾:
自然発生的に形成されていったチームだからこそ、逆に16名の中にどこか共有し合う価値観が流れているのでは?とも思いますが。
アダム:
確かに、それはあると思います。例えば、大学で建築を学んでいた時、どこかで現在の建築やデザインのあり方やその作法というものに、不満を感じていたように思います。コンピュータ・スクリーンの中でデザインをしていくこと、そのスクリーンの背後で仕事を続けていくようなことについて。都市や、人々の生活の現場にどのようにして今デザイナーや建築家たちが関わっていけばいいのか。その問いは私たちの中では共有されていた感覚だったかもしれません。そして「本当は自分たちが何を始めるべきか」を考える推進力になったように思います。
「場所の感覚(センス・オブ・プレイス)」
鷲尾:
最初のプロジェクトは、操業されなくなったガソリンスタンドを映画館に変えたプロジェクトでしたね?
アダム:
はい、「シネロリウム(The Cineroleum)」(2010)です。その当時、既に英国中で数千ものガソリンスタンドが廃業になっていました。安価な工業用の材料や廃材を利用したり、設計図や説明書も用意して、ボランティアの人たちが手作りできる状況にしたりして、多くの人たちと一緒に創っていきました。とにかくこれも費用が全くない中でどうやって実現するかということから考え出したアプローチです。
鷲尾:
自動車という極めて私的な空間を動かすためのエネルギー供給所が、多くの人たちの力が合わさることで公共空間として生まれ変わる。しかも映画館です。とても象徴的な転向ですよね。
アダム:
目的を実現していくために、多くの人々を招き入れ、そして一緒につくっていくという精神は、こうしたプロジェクトを通して、とても自然発生的に深まっていったのだと思います。
鷲尾:
とても自然に。
アダム:
はい、そう思います。その結果、建築やデザインのプロジェクトの実施と、そのプロジェクト自体を構築していくということが一体になっていくアプローチが私たちのスタイルとなっていきました。そして、その方法自体が、私たちを結びつけ、そして前進させていく共通の価値観、積極的な共同体の形成になっていったのだと思います。


“The Cineroleum (2010)” ( © ASSEMBLE)
鷲尾:
「シネロリウム」や「グランビー・フォー・ストリーツ」といったプロジェクトも、また他のあなた方の取り組みを見ていて、思い浮かんだキーワードは、「場所の感覚(Sense of Place)」という言葉です。
アダム:
ええ、私はそれが良いプロジェクトを作るために絶対的に必要になる基本的なことだと思います。特に今、都市は多くの同質性で満ちていることを私たちは知っています。グローバル化による極めて類似した場所や都市の広がりの中で、どのようにしてその場所の持つ固有の特性を保つことができるのか。それは本当に重要なテーマだと思っています。
鷲尾:
どのようなやり方で、私たちはその場所にある「場所の感覚」を捉えることができるでしょうか?
アダム:
それは確かにとても重要なことですが、同時にとても難しいことだとも自覚しています。特に部外者(アウトサイダー)にとっては。よく知らない場所、慣れていない場所に入っていって、本当にその場所にとって重要なことを感じたり、その価値を見つけ出すことは難しいプロセスです。だからこそ、私たちはそこで生きている人たちやコミュニティとともに働くこと、一緒に何かを創り出すということを通して、長い時間をかけて経験を共にしていくことしかないと思っています。そのことでやっと私たちは近づいていくことができる。そして、コミュニティの人々から「学ぶ」という姿勢を大切にすることです。

“Yardhouse (2012–14)” © ASSEMBLE
鷲尾:
中には、自分の「烙印」を押したがる人たちもいます。
アダム:
私たちは逆ですね。実際に「グランビー・フォー・ストリーツ」の場合も、リバプールにあるその地区に、2人のメンバーが引っ越し、一緒に住むことになりました。時々出掛けるというのではなくて、まさにその地域に「埋め込まれていく(embedded)」ようにして、膨大な時間を共に過ごしました。そうすることで、地元の人々と話をし、その地域の歴史や文化を学ぶことができるようになるのです。その場所についての、より深い理解をやっと得ることができるようになる。
ロンドンのような大都会から時々やってきて、意見を言ってはまた帰っていくような部外者ではなく、本当にこのプロジェクトに注力し捧げる人間として受け入れられる存在になること。つまりはデザイナーとして、クライアントである彼らの間に本当の信頼をつくることができるのかが大切だと思っています。
「その場所にとって必要なことは何か。」
鷲尾:
あなたたちのプロジェクトステイトメントの中に、「文化的生産(cultural production)」という言葉を見つけました。その言葉にとても興味を持ちました。
アダム:
私たちはデザインや建築を手がけるのだけれど、「建物」をつくることが必ずしもプロジェクトが抱える問題の解決策であるとは限らない。実際に必要なことは、そのプロジェクトを可能にするための「文化的生産の基盤(Cultural Infrastructure)」を構築することにある。私たちが「文化的生産」という言葉を使っているとしたら、そんなことを伝えたかったのだと思います。
例えば、グラスゴーで行った子供たちの遊び場をつくるプロジェクト、「バルティック・ストリート(Baltic Street Adventure Playground)」はその好例だと思います。物理的なデザインや遊び場の設計に膨大な時間をかけることはありませんでした。その代わりに、私たちはこの遊び場を運営できるグラスゴーの人々を見つけるのにとても長い時間を費やしたのです。この地域が持っている歴史や文化との関係を保ち、それを子供たちにつなげていくこと。それがこの場所にとって必要なことでした。

“Granby Workshop ” © ASSEMBLE
鷲尾:
ヨーロッパの都市、例えば、フランス、英国、またドイツ語圏の国は、建築や都市計画のマスタープランとともに、地域や都市の「文化的発展計画」という、いわば「文化版のマスタープラン」を持っている都市が多くあります。しかし、日本では、都市や生活圏の再生における「文化」の役割や機能についてはなかなか共有がされていない。文化政策の果たす役割についても、その捉え方が限定的であるようにさえ感じています。

“Baltic Street Adventure Playground (2014–) ” © ASSEMBLE
アダム:
「文化」については簡単な定義があるわけではありませんし、多くの解釈で使われ、それに時には不正確に使われてもいます。私自身は、「文化」とはある場所に特有の、その場所で共有されている価値観であると思っています。
鷲尾:
「バルティック・ストリート」はいくつかの財団からの支援も受けていますよね。「文化」を経済指標で換算するというやり方は、新自由主義経済的な潮流が広がって以降、20世紀後半の英国で進められた方向だったように思いますが、日本ではその側面ばかりが取り上げられているのかもしれません。今お話を聞きながらそのように感じました。
“私たちごと” という感覚を育てる

“Granby Winter Garden (2015–) ” © ASSEMBLE
鷲尾:
デザイナー、建築家、都市計画プランナー、あるいはコンサルタントでも、私たちは常に「部外者」(アウトサイダー)です。だからこそ私たちは、やはりコミュニティの人々が自ら価値を生み出すことに寄り添っていく立場であり続けるしかない。私たちが創るのではなく、「彼ら」が創ることを励ましていくしかできないのだと思っています。
アダム:
コミュニティの再生がなければ、やはりその環境は持続していかないと思います。だから大切なことは、周囲の人々に対してお互いをケアしあおうという感覚を育てていくこと、そして地域コミュニティの一人ひとりが、その場所やコミュニティに対して「私たちごとという感覚(authorship and ownership)」(※4)を持ち、地域に直接影響を与えることができるのだ、というメンタリティを育てていく姿勢が大切だと感じています。
そして、もしも部外者がそこに入ってきて何かを変えようとするならば、それを拒否することもできるのだという感覚も。
だからこそ、デザイナーや建築家の仕事は、その作成過程においてコミュニティを巻き込こんでいくことは極めて大切なのだと思います。
例えば「グランビー・フォー・ストリーツ」プロジェクトでは、私たちが加わる前から、住民たちが自ら土地所有管理を行うための組合組織「グランビー・フォー・ストリーツ・コミュニティ・ランド・トラスト(CLT)」というとても強力なコミュニティが存在していました。すでに彼らはストリートの改善をその手で行ってきていたのです。路上に植栽すること、放棄された家の塗装をすることなど、そうした自分たちでできることに取り組んでいました。
だから、私たちが行ったのは、彼らのアプローチのいくつかを共に試し、それを整理し、増幅させたりすることだったのだと思います。
新しい戦略を取り入れるよりも、既にその場所で起きていることを認識し、それの可能性を試し、それらをより恒常的な取り組みに育て、その可能性により多くのスペースを与えていくこと。「ウインター・ガーデン」のプロジェクトもそのようにして生まれました。それは彼らの路上の植栽の取り組みをスケールアップしたものなのです。
「グランビー・ワークショップ」というプロダクツ販売のオンラインショップも、住宅を修繕するためにセラミック製のハンドルやドアノブ、壁紙などのプロダクツを手作りする仕組みを恒常化させ、またそのプロダクツの販売資金によって、コミュニティ自体が持続的な再生を実現していくための仕組みの提案です。
鷲尾:
その場所が持つ資源、その場所で暮らす人たちが持つ創造性を引き出していくこと。
アダム:
全くその通りです。コミュニティの人々の中に「種」があるのです。まったく新しいアイデアではありません。また同時に、それぞれのプロジェクトには、さまざまな状況や異なる課題があり、そしてそれらは避けられないわけです。いつでもその状況を捉えて可能性を見出すこと。自分たちのやり方に固執することなく、過去に学んできたことを超えていこうとする姿勢も必要だと感じています。

“Turner Prize Exhibition (2015) ” © ASSEMBLE
鷲尾:
デザインや建築、あるいはアーツ&クラフト。こうした人の手が生み出す創造性が、私たち自身が暮らしている社会そのもののあり方を再生させていくために活かされていく。新たな自己表現のカタチとしてでも、あるいは創造産業を誘発するアイデアとしてでもない、それはもうひとつの方向性であり、可能性なのだと思います。
私があなた方の展覧会で感じた「明るい陽差しのような感覚」というものがどこから来ているのか、少しわかってきたように感じています。
Information
資生堂ギャラリー100周年記念展
「アートが日常を変える 福原信三の美学 Granby Workshop : The Rules of Production Shinzo Fukuhara/ASSEMBLE, THE EUGENE Studio Ⅱ」
会期:2018年10月19日~12月26日、2019年1月16日~3月17日
会場:資生堂ギャラリー (東京都中央区銀座 8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階)
詳細: https://www.shiseidogroup.jp/gallery/
注釈
(※1) グランビー・フォー・ストリーツ(Granby Four Streets)
(※2) グランビー・ワークショップ(Granby Worksop)
英国リバプール市のグランビー地区を再建するためのコミュニティ主導プロジェクト。グランビー・フォー・ストリーツは、かつてはリバプールの最も活気のあるハイストリートであったが、1970年代における地場産業(造船業)の衰退と経済不況、その後の失業や人種問題をきっかけとした暴動、再建のめどがつかないまま放置された廃屋など、深刻な地区の荒廃が進んでいた。
2011年に、グランビーの住民たちは自ら廃屋となった家を手頃な価格の住宅として再生されることを意図してコミュニティ土地信託「グランビー・フォー・ストリーツCLT (Granby 4 Streets Community Land Trust)」を創設。アッセンブルは、このCLTと協力して地域住民が行ってきた取り組みに参加し、継続的に地区再生を主導していった。そのアプローチは「コミュニティ主導」を基本とするもので、現場にある廃材や瓦礫を利用して、ドアノブ、タイル、マントルピース、椅子、壁紙、カーテンなど新たな内装のパーツを作り出すワークショップを考案し、廃屋の改装を地区住民が自ら取り組むことを可能にするというものであった。その後2015年には、この「Granby Workshop」は建築用セラミックス製造会社として事業化され、デザイナー主導でつくられた様々な住宅用プロダクツを販売し資金を調達することで継続的な地区の再生を可能にする仕組みへと成長している。また、同じく2015年からは、ケアンズストリートにある2つの遺棄された家から作られたパブリックガーデンを創りだす「グランビー・ウィンター・ガーデン」(Granby Winter Garden)も始まっている。

“Granby Workshop Products” © ASSEMBLE and Granby Workshop
(※3)ターナー賞
1984年に創設されたターナー賞は、イギリスを拠点に活動する現代アーティストに対して贈られる賞。英国はもとより、世界的にも注目されるこの賞を、建築家であり、グループとして受賞したのはアッセンブルが初めて。
(※4)「私たちごとという感覚(authorship and ownership)」
アダムさんは「authorship and ownership」という言葉を用いていた。「authorship」とは「原作者が誰か」を、「ownership」とは「所有者が誰か」を指す。ここでは意訳ではあるが「私たちごと」とさせていただいた。
プロフィール

ASSEMBLE(アッセンブル)
https://assemblestudio.co.uk/アート、デザイン、建築、社会学、哲学など多様なバックグラウンドを持ったメンバー16人によって、ロンドンをベースに2010年に結成された英国の建築家チーム。2015年に、リバプールの荒廃した住宅街の再生を地域コミュニティとの協働によって果たしたプロジェクト「クランビー・フォー・ストリーツ」によって、イギリスの現代美術のアーティストに授与される「ターナー賞」を建築家チームとして初めて受賞した。最近の主なプロジェクトに、ゴールドスミス現代美術センターの改築「Goldsmiths CCA」(2014〜)、アートの実践と教育のためのスペース「Art Academy」(2017〜)などがある。今回、インタビューに答えていただいたアダム・ウィリス(Adam Willis)さんはケンブリッジ大学の建築学科出身。建築、家具のデザインなどを主に手がけている。