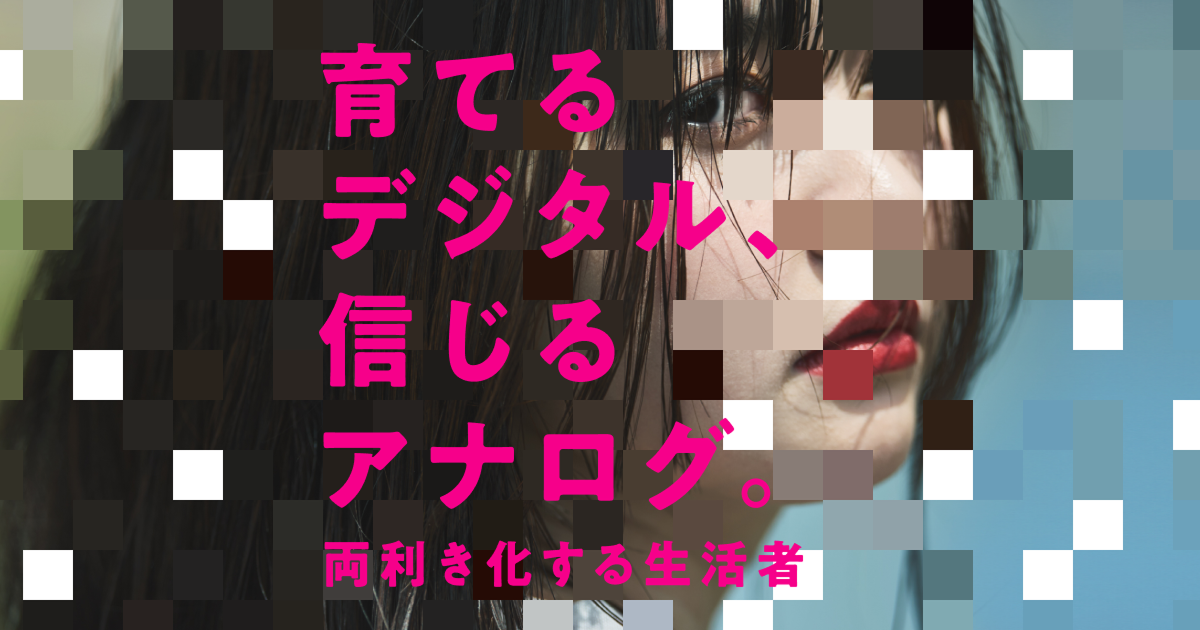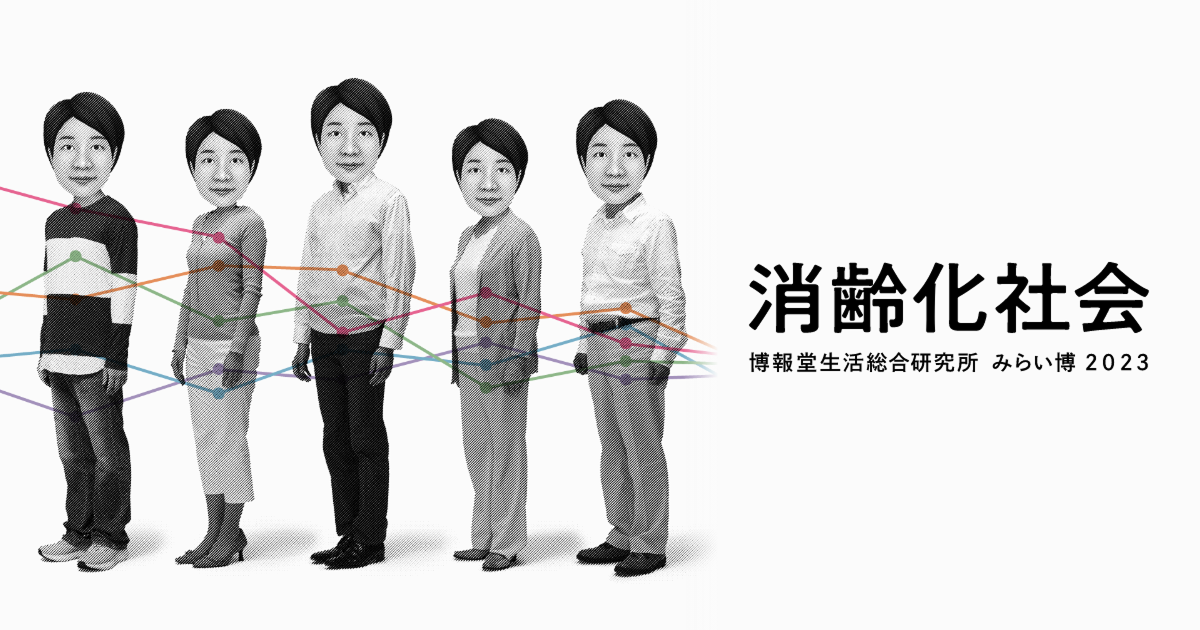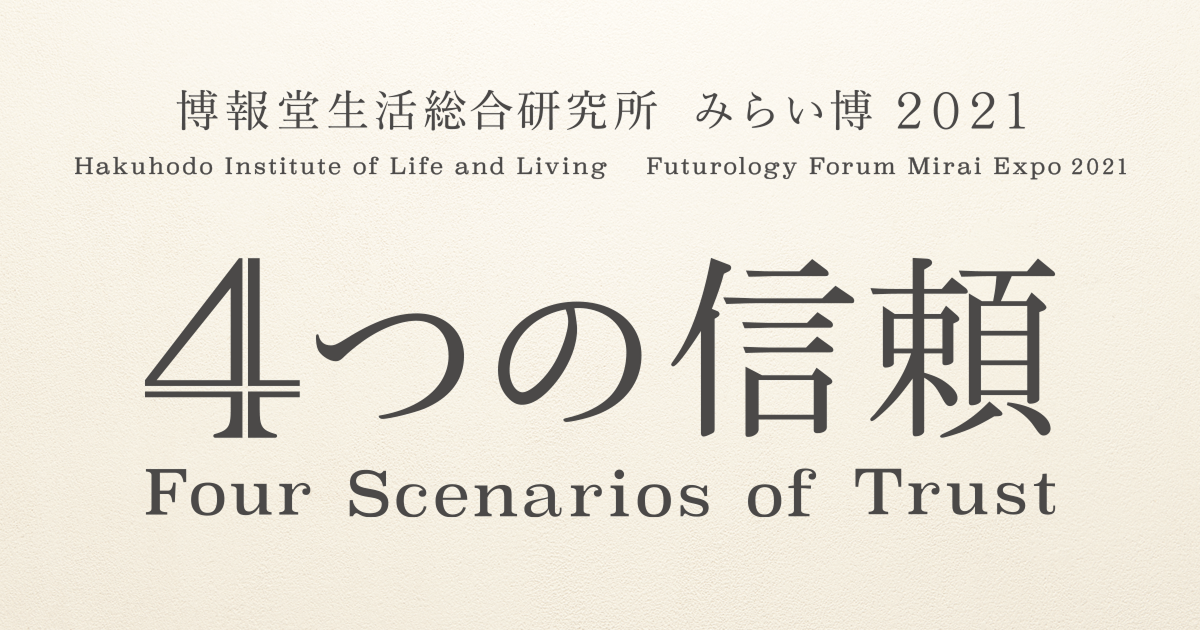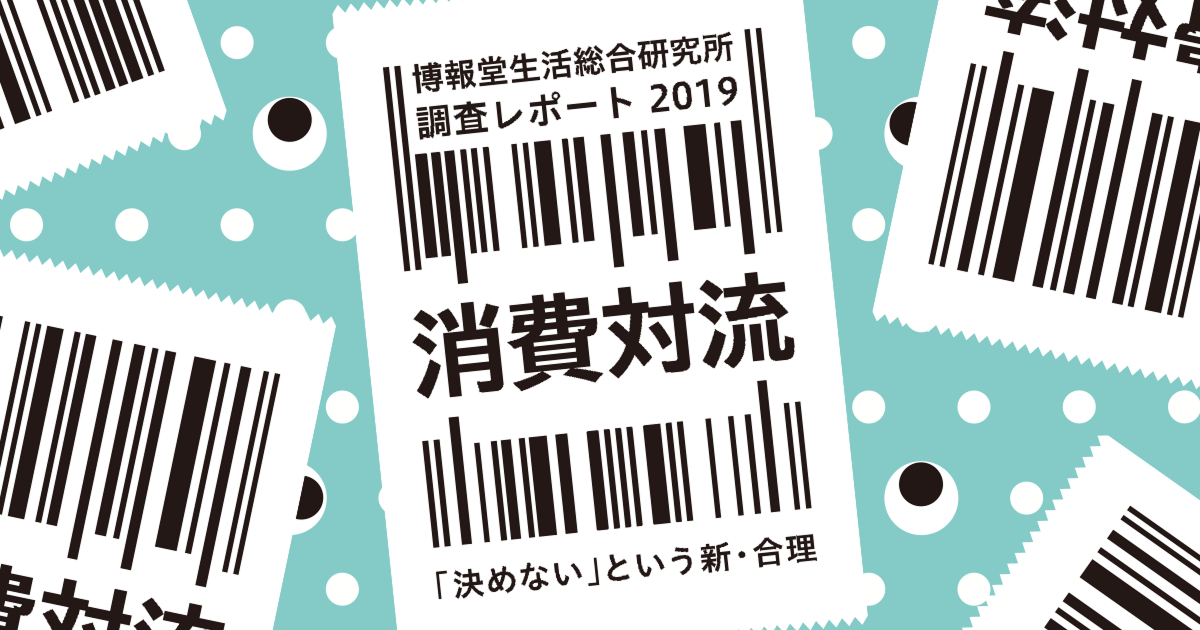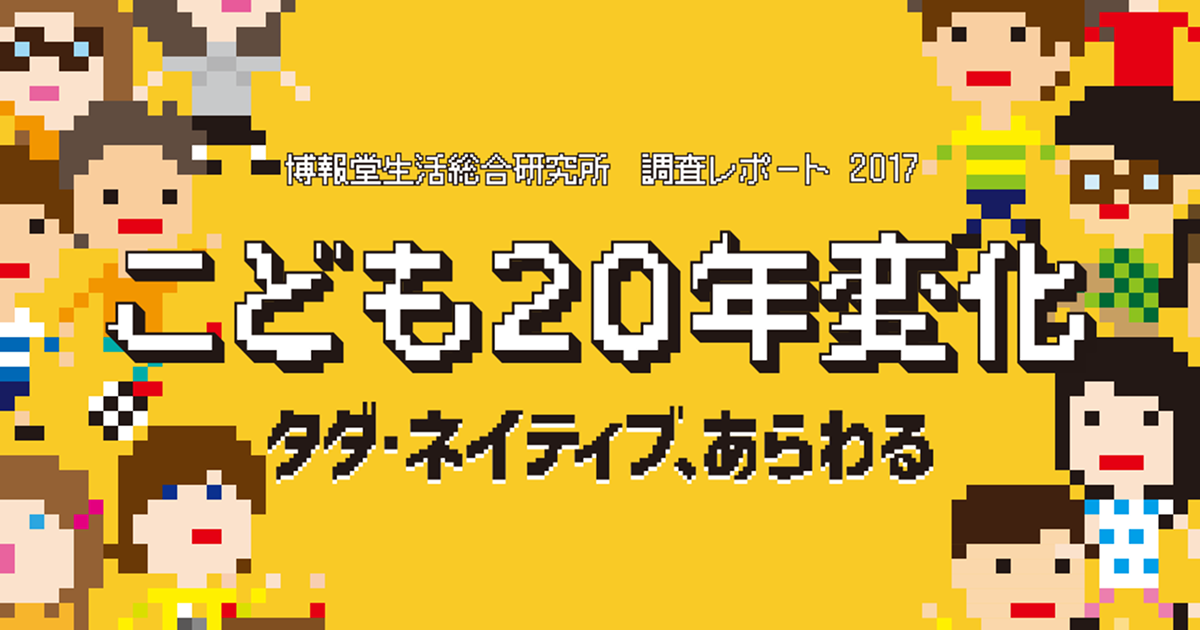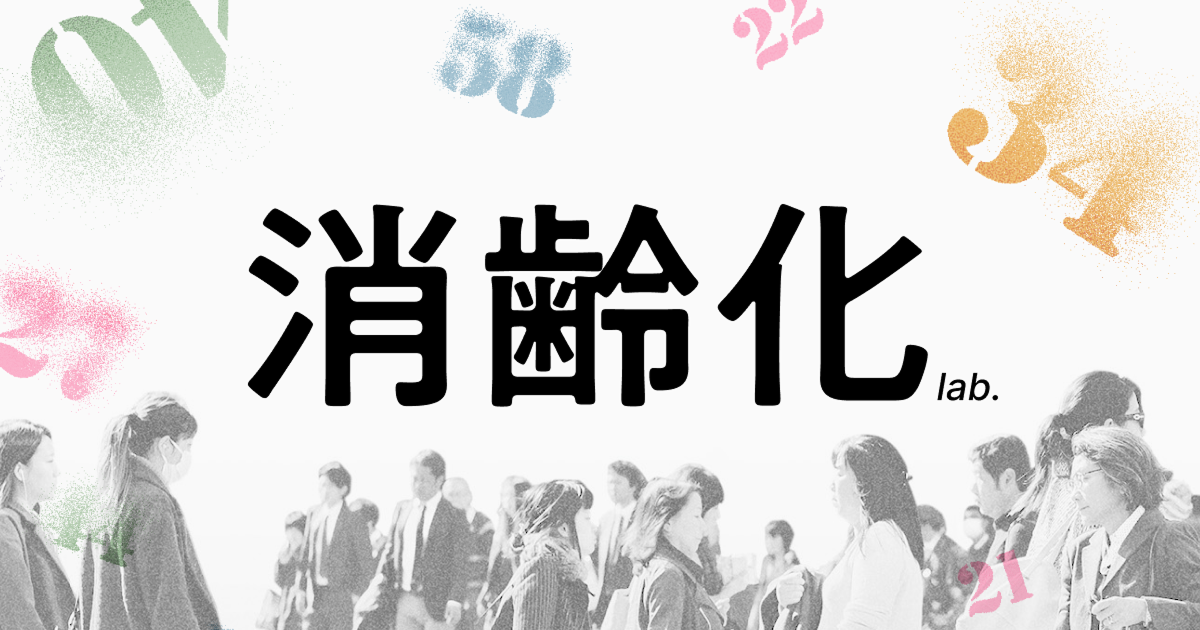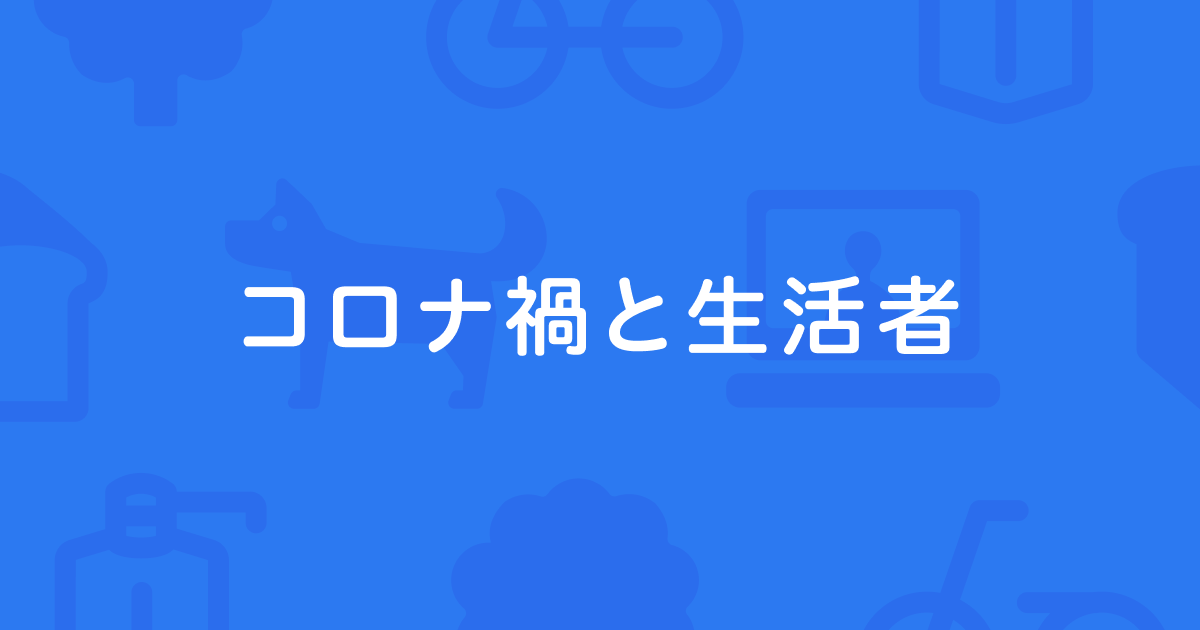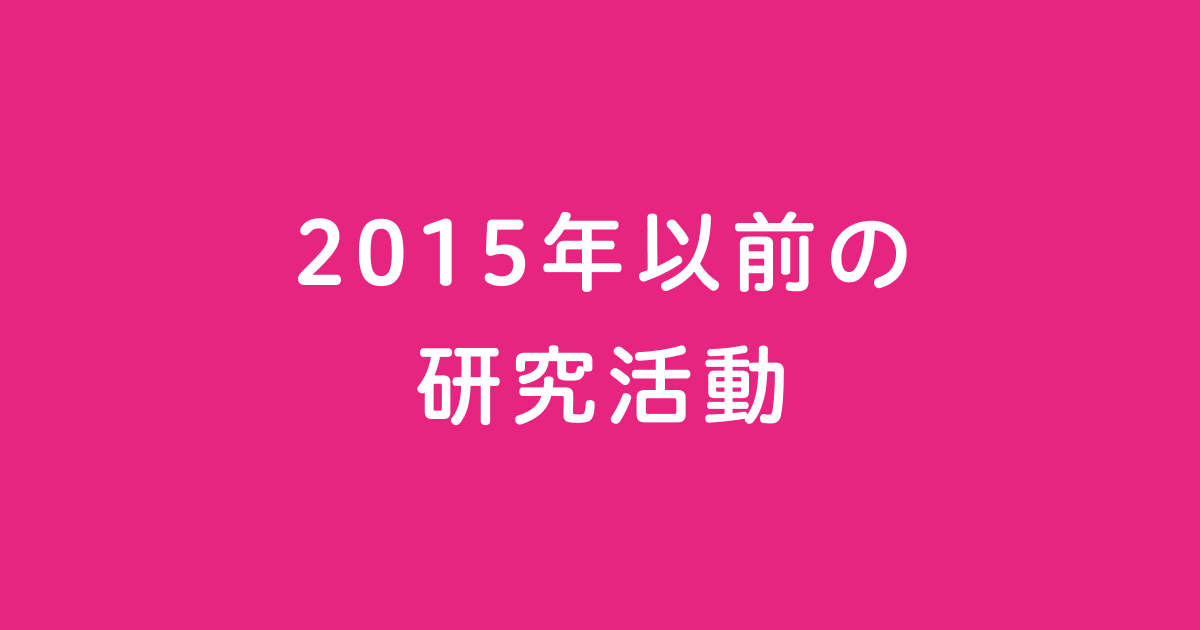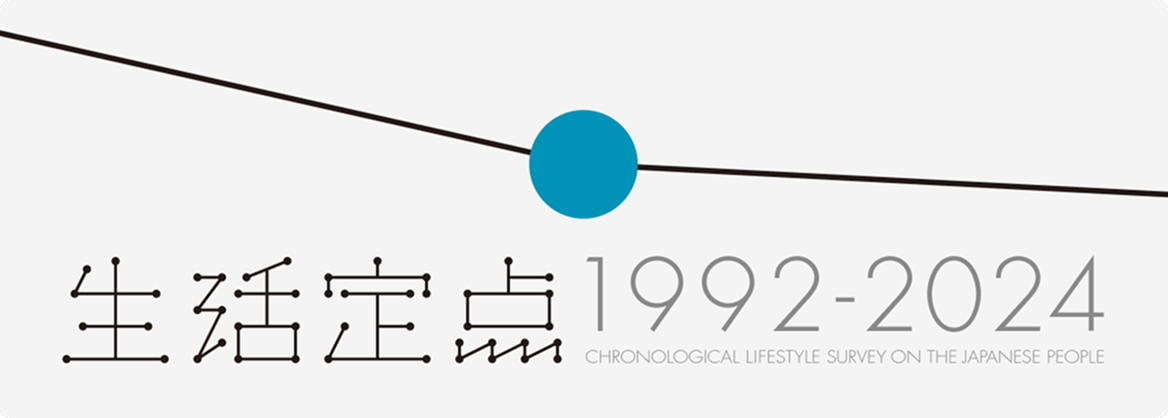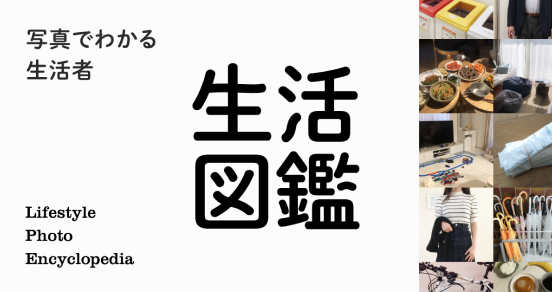生活総研刊行物
-
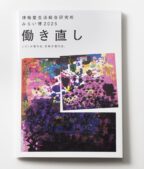
みらい博2025
働き直し回復しない経済、解消しない人手不足、上がらない賃金… 生活者の「働く」意欲が下がり続けています。 その一方で、 転職市場の活況、副業の解禁、リモートワークの浸透… 生活者の「働く」自由度は増しています。 そんな追い風と向かい風が交差…
2025/01/28 -

みらい博2024
ひとりマグマ「ひとり」と聞いて、最初に思い浮かぶことは何でしょうか? おそらく「孤独」「少子化」などの社会問題と絡めて、ネガティブに捉える方も多いことでしょう。 しかし、例えばコロナ禍で「ひとり」でいることを余儀なくされた人がいる一方、 実は「ひ…
2024/02/01 -

みらい博2023
消齢化社会「大衆」から「分衆」、そして「個」の時代へと続く流れのなか、生活者の嗜好や価値観は多様化し、まとまりを捉えることが難しくなっています。ところが、生活総研の長期時系列調査「生活定点」の30年間のデータを分析したところ、従来、年代によって大きく…
2023/02/01 -

みらい博2022
2040年 私の「ふつう」今回の『みらい博』では、「生活者1万人への未来調査」をもとに、2040年に訪れるかもしれない「ふつう」の行方を考えてみました。 みえてきたのは、生活者自身のアイデンティティや五感のリアリティ、関係するコミュニティ……といった暮らしの前提が…
2022/02/10 -
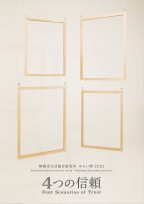
みらい博2021
4つの信頼新型コロナウイルスの感染拡大は、世界のありようを大きく変えてしまいました。しかも、未だ終息の気配は見えず、未来を考える前提は日々刻々と変化しています。そこで今回、我々は不確定性の高い環境下での予測手法であるシナリオプラニングを調査研究に取り…
2021/03/05 -
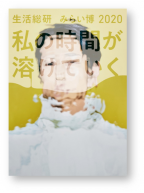
みらい博2020
私の時間が溶けていく超高齢社会、100年人生……と、 生活者が向きあう時間が長くなりました。 一方で、働き方改革、時短商品……と、 時間の無駄を減らす流れが強まっています。 そして、時間の使い方が問われはじめている今、 これまでのルールには縛られない…
2020/01/29 -
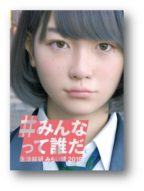
みらい博2019
#みんなって誰だ大衆や分衆、マス、クラスタ、層……。 マーケティングの世界では、 生活者のまとまりを表す言葉がたくさん生み出されてきました。 しかし、かつてのようにほとんどの人が同じような商品を買い、 同じ番組を見るということはなくなっています。 …
2019/01/30 -

みらい博2018
進貨論 ―生活者通貨の誕生―お金に対する生活者の価値観が変わりはじめています。 これまで、人々の多くはお金をたくさん持つことが幸せにつながると考えてきました。 しかし、いっこうに経済の回復を実感できないなか、この価値観が大きく揺らいでいます。 お金で自由を得るつ…
2018/01/24 -

みらい博2017
好きの未来 ―わたしの熱が、世界をまわす―2016年に実施した「生活定点1992-2016」によると、生活者のあいだに「この先、良くも悪くもならない」という認識が広がるとともに、この状況を悲観することなく身近な幸せを感じて暮らしていることがわかりました。つまり、現在の日本は、ありの…
2017/01/25 -
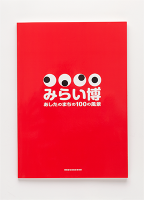
みらい博
あしたのまちの100の風景いつの時代も、街の風景には社会や経済のありようが凝縮され、生活者の欲求が反映されます。そんなマクロとミクロが交差する街のゆくえを考えることは、日本の未来を考えることにほかなりません。 2020年以降、超高齢化と人口減少が街の存続を危う…
2016/01/27 -

BIG PRESENTATION 2015
デュアル・マス戦後70年、戦後レジーム(55年体制)成立から60年を迎える2015年。生活者はますます見えにくくなっています。情報は爆発し、趣味嗜好は多様化。スマートフォンの普及と共に生活者自身がソーシャルメディアで情報発…
2015/02/20 -

生活動力2014
インフラ友達SNSの浸透やNPO活動の隆盛など、これまでにない新たな場でのつながりが、友達の数を急速に拡大させています。一方、私たちの長期時系列調査『生活定点』の「友人は多ければ多いほどよい」の回答率は10年以上にわたり大きく下降。人間関係が自然に拡大…
2013/12/20 -

生活動力2013
総子化止められない少子高齢化。未成年の子供は減り続けています。その一方で、親の高齢化とその長期にわたる健在は、大人でも「子供としての自分」を持つ人々を増加させているのです。未成年人口に、親が健在の成人人口を加えた現在の日本の総「子供」数は8,70…
2012/12/13 -

生活動力2012
圏づくり −私が生きる場 私を活かす場−生活総合研究所では、生活者の価値観変化を探るべく、様々な調査、取材を続けています。震災後に見えてきたのは、自分のため、家族のため、社会のため、「自分のできることはなんだろう」と自問自答し行動する生活者の姿でした。人々は個として自律した上で、…
2011/12/15 -

生活動力2011
動の成熟 —楽しさ先進国をめざして—成熟社会に入ったといわれて久しい日本。国民の平均年齢は世界最年長の45歳を超え、経済的にもバブル崩壊以降は「失われた20年」が続いています。しかし、いつまでも「失われ」続けるわけにはいきません。いま、求められているのは、過去からの「成長」に…
2010/12/15 -

生活動力2010
態度表明社会 —賛成の連鎖が流れを変える—世界同時不況から1年余。激変する社会環境の中、様々な課題が人々の暮らしに降りかかっています。「変わらなければ続かない」、そんな危機意識が企業や政府、自治体だけでなく、生活者にも着実に広がっています。こうした時代環境は、人々を新しい行動へと導…
2010/01/01 -

生活動力2009
第三の安心 —社会を修理する生活者—2008年、世界が大きく揺れました。不安が日本を覆う中、生活者の安心づくりが進化しています。自己防衛力の強化や、家族、地域との関係強化といった身のまわりの安心づくりから、世の中全体の安心づくりへ。人々は、暮らしの揺らぎを止めるべく、みずから…
2009/01/01 -

生活動力2008
手ごたえ経済 —実感をつかまえる幸福へ—長い不況のトンネルを抜け出した日本。その一方で、多くの人が効率や利便性を追求する暮らしに疲弊し、生きている実感を失い、漠然とした不安を抱いています。 しかし、その奥底では、新しい幸福を求め、価値観の転換が始まっています。人々が目指している…
2008/01/18 -

生活動力2007
多世帯社会—世帯が変わる 世界が変わるこれからの日本は、「世帯の変革期」にあります。世帯の総数、1世帯あたりの人員、世帯の形態と分布、全てが大きく変化しています。国勢調査の推計によれば、2007年、標準世帯と呼ばれる[夫婦+子]の世帯数を[単独世帯]が抜くことになります。また[…
2007/01/01