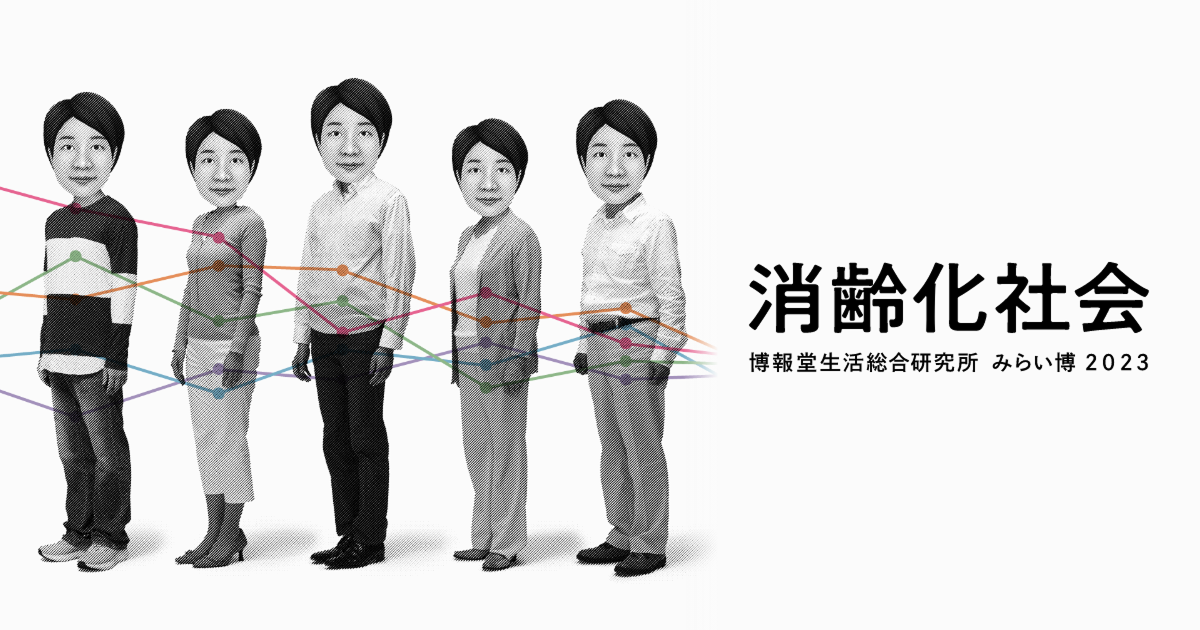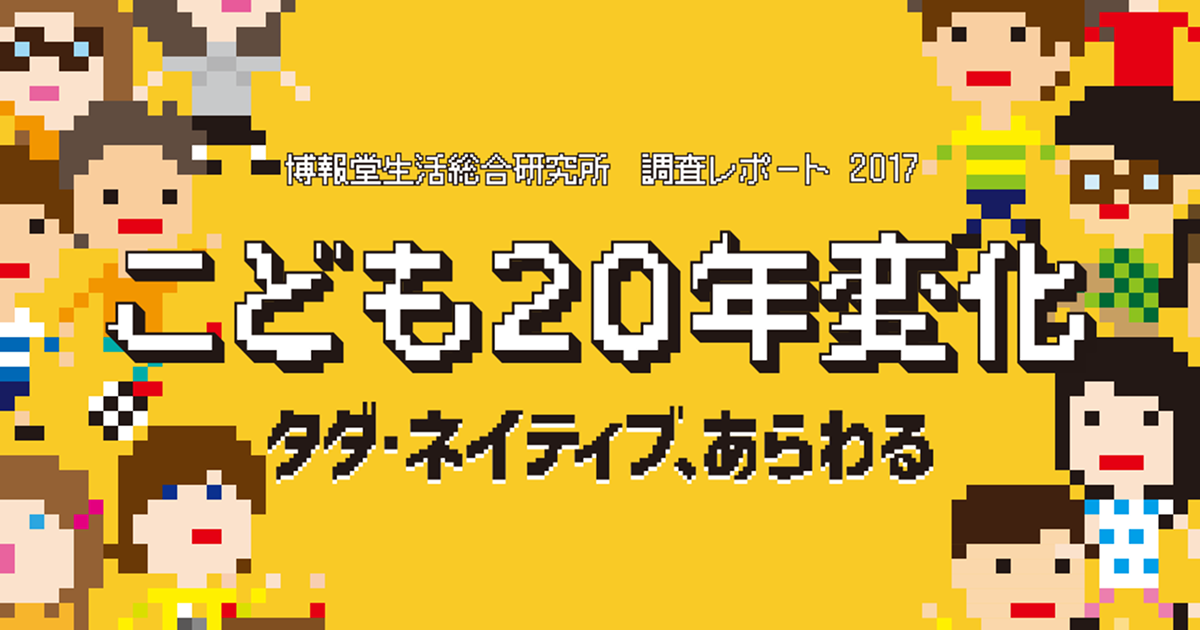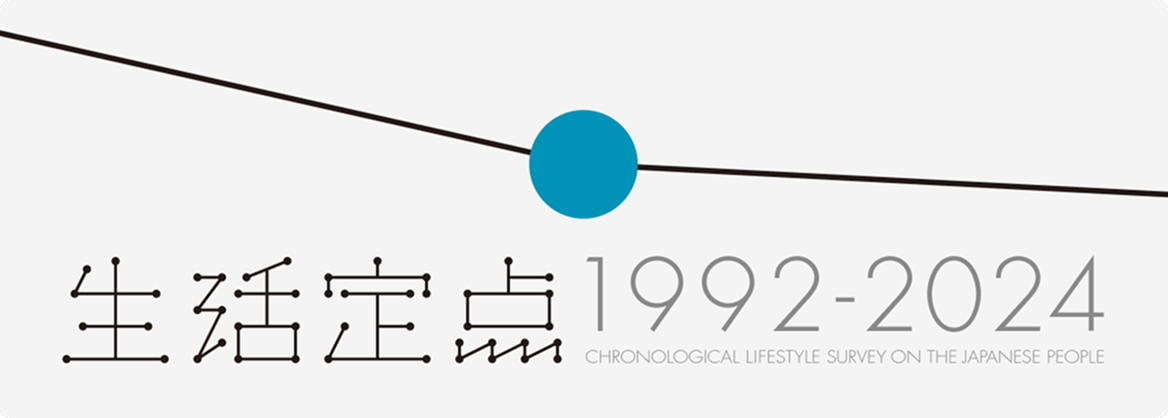「死の在り方」に着目したきっかけ
私が編著を務めた書籍『RE-END 死から問うテクノロジーと未来』(以下『RE-END』)は「HITE-Media」という研究プロジェクトから生まれた書籍です。
現在、AIやロボティクスなどの情報技術が社会に浸透しており、その中ではもちろんAI自体の研究開発を進めていこうとする研究プロジェクトがたくさんあります。一方で、「それらが本当に社会に浸透したときに人間や社会がどう変化するのか」という問いから生まれた研究領域がHITE(日本語で「人と情報のエコシステム」)です。
例えば法制度や公共政策、「ウェルビーイング」と言われるような生き方の問題、さらには哲学的な問題までかかわってくるときには、いわゆる理系の分野だけではなく、人文社会学の視点からも考えていく必要があります。テクノロジーの発展によって既存の社会に新たな光が当たると、「人間とは何か」といった根源的な問いが改めて振り返られやすくなるのです。
HITEはそのような研究を促進するプロジェクトで、その一環として専門領域を超えて様々な人びととメディアを通じて活発な議論の場を創出するのがHITE-Mediaです。
その中で「死」というテーマを扱った理由ですが、「テクノロジーが進展した未来社会」を考えようすると、「AI」という言葉がひとり歩きして、あまり実感のない空論になり、「人類は今後どうなるのか」といった主語の大きい話になりがちです。
そうではなく、「絶対に誰でも自分ごととして捉えられるテーマ」は何かと考えたときに、「死生観」という切り口なら誰にとっても考えやすいのではないか、と思ったのが『RE-END』という本の着想のきっかけです。関連して、同じテーマの展覧会「END展 死×テクノロジー×未来=?」も開催しています。

テクノロジーによって
「死ねなくなる」という問題
情報技術の発展によって、死後もデジタルデータが簡単に残ってしまうようになりました。デジタル上では、その人が生きているのか死んでいるのかに関係なくデータが残ってしまいます。日常のレベルでも、SNSでつながっている人が亡くなった後も、その人の誕生日を通知してくるようなことは起きていますね。
2020年には、亡くなった少女とその母親がVR上で再会する、『Meeting You』というドキュメンタリー番組が韓国でつくられて、賛否両論が生まれました。今はVRで故人のアバターをつくろうとすると技術的にコストがかかるので、まだテレビ番組になるぐらい稀な例ですけど、亡くなった人のいろいろな写真や声などのデータをもとにVRのアバターを制作することは、もう10年ぐらい経ったら一般向けのサービスになるだろうと思います。
このように、デジタルテクノロジーによって「死ねなくなる」という状況が起きつつあります。
そうなると、これまでの死ぬときの主題は「お墓をどう残すか」でしたが、これからは「どうやったらデータを残さずに死ねるか」というニーズも出てくると思います。
「END展」でも行ったアンケートの中で「SNSのデータを消したいですか?」という質問に対して、半数以上の人は「消したい」と答えています。
この結果に関して、『RE-END』を読んでくださった遠野郷八幡宮の禰宜である多田さんという方は、「すごく面白い。日本人って死後を信じているんですね」と仰っていました。
亡くなった瞬間に天国ないしは地獄に行って、この世界からはいなくなると考えられている宗教観では、死んだらそこで終わりなのでそもそも死後なんか気にしないはずだけれど、日本人が「死後のデータを消したい」と希望しているのは、「死んだ後も自分が見ている感覚」が根強くあるからんじゃないか……と多田さんは言うのです。
データが残るかどうか以外にも、「死後労働」の問題もあります。少し前に「AI美空ひばり」が話題になりましたし、現在世界の中でも死後労働で最も稼いでいるのはマイケル・ジャクソンだという話もあります。亡くなったアーティストの著作権・原盤権が守られるのはこれまでにもあった話ですが、今後はそれだけでなく「AIが新作をつくる」みたいなことも起こるようになりました。
死後もその故人の肖像を使い続けることで金銭が発生するなど、肖像権・パブリシティー権の問題もありますね。『RE-END』の中でも弁護士の水野祐さんに執筆していただいていますが、これらの問題には今後法制度の整備が求められてくるだろうと思います。
死と、変容する人の意思
「安楽死」に関しては、一般に想像される以上に難しい問題だと感じています。
『RE-END』で内科医の尾藤誠司先生にインタビューしていて、先生は「みんなが考えるような安楽死はファンタジーだ」と仰っていました。
「ここで人工呼吸器を付け続けるか、否か」といった場面で人工呼吸器を抜くことも安楽死のひとつといえるけれど、患者が「安らかに死なせてくれ」と言ったところで、その家族が「わかった、おばあちゃん」みたいに応える、みたいなことは実際はそう起きていない。
現場ではもっと切迫した状況の中で、医者がどう説明したか、家族はどう判断したのかなど、誰がその人の生と死にまつわる決定をしたのかといった意思決定の所在が曖昧なまま決まっていくことの方が多いんだそうです。私はとてもリアルだと感じましたね。
また尾藤先生がよくお話しされることですが、人間の意思はずっと変容していくものですよね。今日の私が安楽死のサインをしたとしても、明後日の私がそれを良しとするかは、一概にいえない。
尾藤先生は、そうした前提に立ったうえで「本当に本人が適切な意思決定をできたのか?」ということをちゃんと問いかけていきたいと、そして、きっと一個人がそう簡単に死を決められるものではないという前提について、まず考えた方がいいと仰っていました。
それに日本の場合は、社会的な同調圧力が強い文化であることは間違いありません。
ですから、例えば最悪のケースとして「社会の役に立たない人間はみんな安楽死しろ」みたいなことを誰かがTwitterなどで言いはじめたとして、直接言われていない人も「この社会はみんなそう思っている」と考え、自ら死を選んでしまうようなことだって十分あり得ると私は危惧しています。
そうような方向ではなく、もっと健やかな選択肢があってもいいですよね。最近は自宅で亡くなる方も増えているそうです。それは在宅医療にも国家予算がつけられるようになったという背景があると聞きましたが、そうした社会制度の面から後押ししていって、丁寧なケアのもとで死を迎える選択肢が増えていく方が良い在り方だと思います。
テクノロジーの力で、死と出会い直す
死に際してのテクノロジーが多様化する一方で、自然回帰的な欲求もすごく高まっていくように感じています。
例えば日本でも海への散骨や樹木葬のニーズも増えていますし、さらにアメリカでは最近「堆肥葬」というものがはじまっています。2019年にワシントン州が遺体の堆肥化を合法にした後、「Recompose」というスタートアップなどがサービスをはじめて、予約が殺到しているそうです。棺桶を有機物のシートでつくって、周りにも落ち葉などの養分になるものを詰めると、およそ30日程度で土に還るそうです。
「テクノロジーを使う」というとディストピア的な方向に考えがちですが、私自身は、テクノロジーと人間のより良い在り方を考えていきたいです。例えば、身近な人の死を受け入れるグリーフケアの場面において、死者と対話していくためのテクノロジーの新しい使い方を見出していくような方向があってもいいですよね。
END展で「誰かの死に関して印象的な夢や出来事はありましたか?」というアンケートをとったら、信じられないくらい印象的なエピソードがたくさん集まりました。死に関することって普段語られないですし、ある種タブー視されている分、実はそれぞれの中に秘めたものが蓄積されているんですね。

END展の作品(Photo: Asato Sakamoto)
それだけに、死を考えることは、どう生きるかを考えることに直結すると思います。シンプルな話ですけれど、死は絶対に避けられず、誰にでも平等に来るということを踏まえた方が、生きやすくなる。
もしもこれからのテクノロジーが、死と向き合うことの多様性をサポートしてくれるような未来になったら、きっと素敵だなと思います。
塚田有那(つかだ・ありな) 一般社団法人Whole Universe代表理事。編集者、キュレーター。世界のアートサイエンスを伝えるメディア「Bound Baw」編集長。2016年よりJST/RISTEX「人と情報のエコシステム(HITE)」のメディア戦略を担当し、「HITE-Media」のメディアリーダーを務める。同プロジェクトの一環で編著を務めた書籍『RE-END 死から問うテクノロジーと未来』(ビー・エヌ・エヌ、2021年)が話題に。