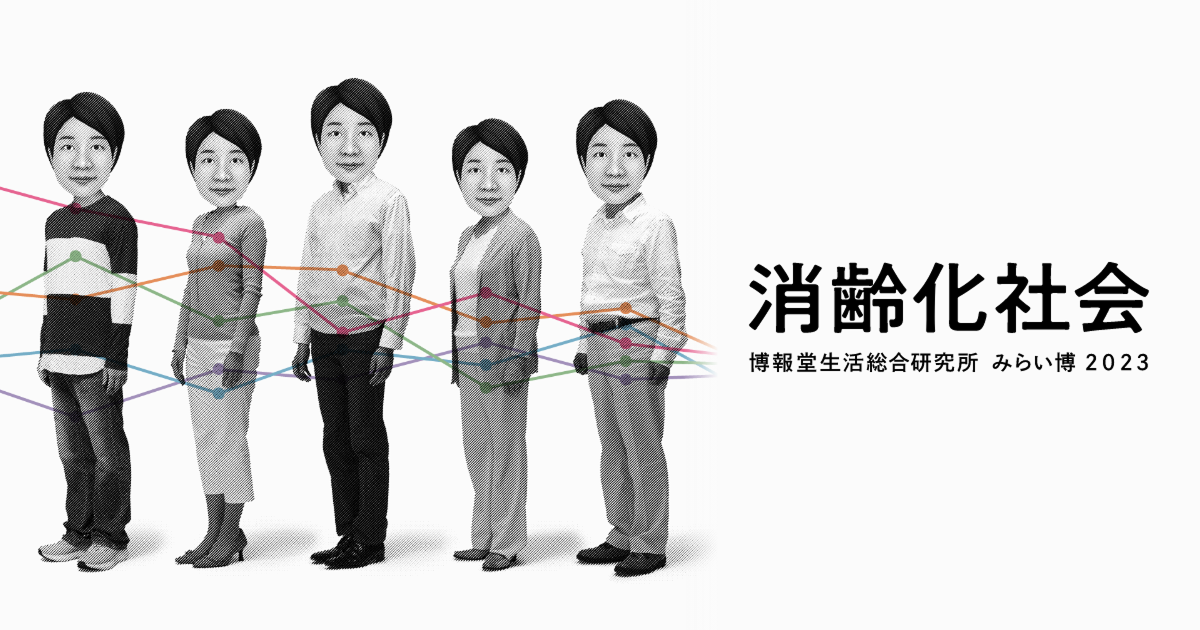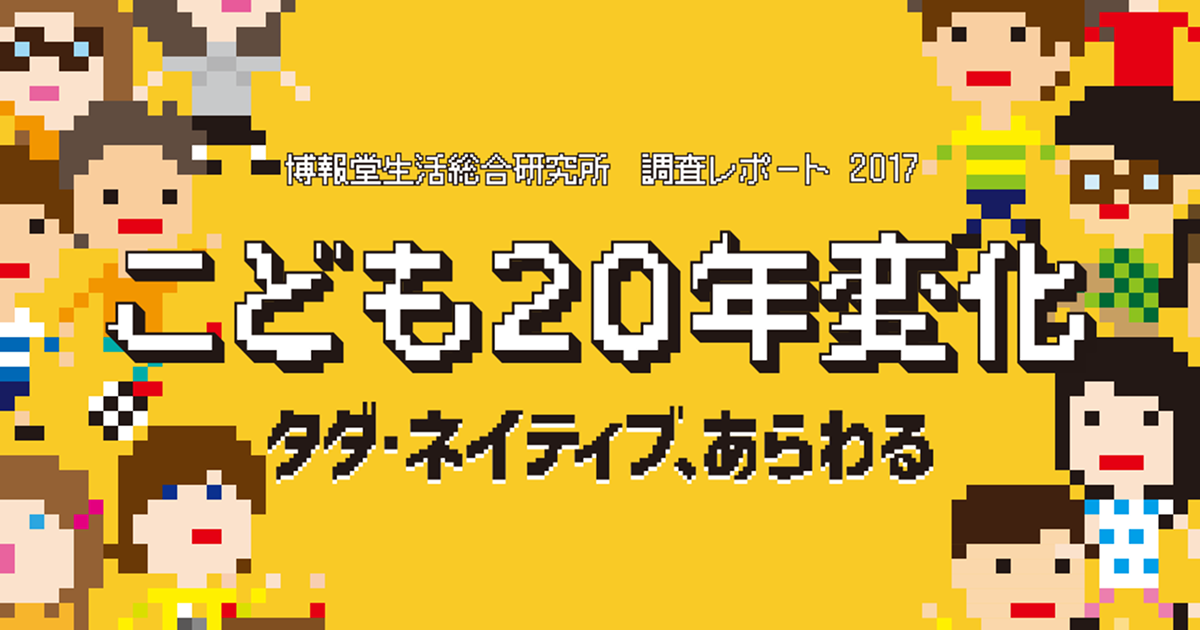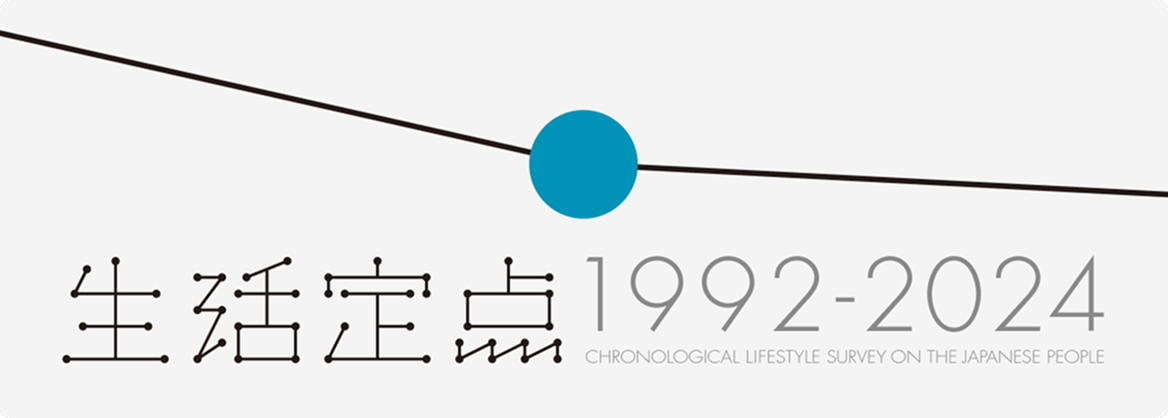「生活圏2050プロジェクト」 #06
パワー・オブ・メイキング〜「ともに創る」ことで社会を修復する~(後編)
英国の建築家チーム「ASSEMBLE」。メンバーのアダム・ウィリスさんとの対話、その後編です。場所は栃木県・益子町。陶芸家・鈴木稔さんのもとで展覧会のための作品制作を行っている現場でお話をお伺いしました。人口減少社会における新たな生活文化と経済(エコノミー)の創出を構想する「生活圏2050プロジェクト」。プロジェクトリーダーを務める鷲尾研究員が、既に今各地で始まっている新しい生活圏づくりの取り組みを伝えます。
※前編はこちら


栃木県・益子町
チェンジ(変更)ではなく、アップデート(更新)。
鷲尾:
アダムさんは、日本は初めてですか?
日本の街に対する率直な印象を聞かせてもらえますか。
アダム・ウィリス(「アッセンブル」メンバー、以下アダム):
日本には何度か来たことはあります。兄弟が日本に住んでいるんです。日本は信じられないほどエキサイティングな場所ですね。特に東京は。東京が持っている密度やバラエティは本当に面白い。特に建築的には非常に多くの自由度がありますから。個人的には好きですが、実際にはそれは上手く機能するときも、同時に機能しないこともあるでしょうね。薄汚くなることも、素晴らしいものになることも。とにかく、ロンドンとは対照的です。
鷲尾:
常に新しい何かを求めて変化していこうとすることは、行き過ぎれば、歴史や記憶の喪失にもつながっていくことにもなります。作るのは時間がかかりますが、消し去るのは一瞬です。さきほど「私たちごとという感覚(Ownership)」という言葉を使われましたが、その意味では、特に大都市では「ここは私のものでもない」「誰のものでもない」という場所の感覚が広がっているのかもしれないと思っています。

ワークショップで参加者とつくった陶器が登り窯に詰め込まれた
アダム:
とても難しい問題です。「グランビー」のプロジェクトを例にすると、あの家々は英国における暮らしの基本になったような歴史的なテラスハウス(長屋)を維持しようとする取り組みでした。英国の生活様式、労働者文化、そして全国に広まった極めてシンプルで働きやすい住宅の類型です。それはいわば英国の人々が手にしてきた歴史性や、ロマンチックとさえ言える価値を体現してきたものだったのです。その家々を保持することは、その場所に対する「私たちごとという感覚(Ownership)」を育み、その場所を大切にしようとする意識を育てていくことそのものでした。それらがただ綺麗にされて、単に新しいものに取り替えられているならば、それは歴史を、文化をも消し去ってしまうことなのだと思います。みんなで共有しあってきた記憶そのものを消すことです。
鷲尾:
過去を過去として封印するのではなく、過去と現在、そして未来をつなぐような計画(プランニング)がとても大切になってくるのだと思います。「グランビー」のプロジェクトにある軽やかさや明るさは、そんな過去と未来とがつながっていく感覚なのだと思います。場所を「変える」(changing)のではなく、「更新する」(Up-dating)することです。

火入れの準備を指導する鈴木稔さん
鷲尾:
昨夜は、東京で行ったワークショップの成果である陶器を入れた登り窯にみんなで一緒に火入れを行いました。
昨晩、この登り窯の持ち主である陶芸家の鈴木稔さんとお話ししながら、あなた方が英国で行ってきた活動との共通点を感じざるを得ませんでした。鈴木稔さんはこの益子町の出身ではありません。しかし、彼は益子の風土が長い時間をかけて育ててきた土、色・技法を発見し、そしてそれを選びました。この場所に工房をつくり、そして、そこに自身の技と感性を込め新たな作品を作られています。そのことで、益子の風土をまた新たにアップデートされようとしている。この土地と風土が育ててきたことを変えるのではなく、それを更新していこうとされています。
アダム:
私たちはとても共通していますね。益子に来て、この場所でしか生まれなかったであろう特別な方法で働いている人たちに出会えるという素晴らしい経験を得ました。私たちはいつでも、とても長い時間をかけて、その場所が育ててきた非常に特別なスキルを学ぶことに非常に興味を持っているんです。
鷲尾:
濱田庄司さんの記念館(※「濱田庄司記念益子参考館」)も行かれましたか? 彼はバーナード・リーチやルーシー・リーといった英国で活動していた陶芸家や美術家との交流を大切にしてきた陶芸家でした。彼も鈴木さんと同じく、益子の土地と風土を選び、この場所を中心に日本各地、世界各地とのつながりを豊かにしていった方でした。アダムさんと鈴木さんとの出会いは、この益子が育ててきた文化の上で、新しく生まれたものではないでしょうか。
アダム:
はい。濱田さんたちの世代のことも知り、今私が日本を訪ね、こうして益子の陶芸家と協働していることに、素晴らしいつながりがあると感じています。

登り窯にまもなく火が入れられる
人々はもっと自由に移動し、もっといろいろな場所に移り住んでいくでしょう。
鷲尾:
しかし、日本ではこの半世紀に渡り、多くの地方の都市が、まるで東京のようになろうとしてきました。特に小規模の町や村よりも、中規模サイズの都市ほどそのような傾向が多かったかもしれません。
しかし、これからは「文化的生産(cultural production)」ということに意識的であることが、町や地域や生活圏の持続可能性のためにもとても大切だと思うのです。技術や情報はユニバーサルなものです。コピーも簡単にできますから。コピーできないものは何か、それを見つけ出すには、あなたが言うように、その場所にとどまること、その場所に深く関わっていくこと、その場所の記憶を見出すことが必要だと思います。
アダム:
イギリスにも同様の問題がありました。中規模の都市ではあらゆる分野の人々が依然としてロンドンの次の都市になるという意識で欲望を高めてきました。しかし、もしかすると技術革新がこうした状況を変えていくかもしれないとも思っています。今後はさらにデジタル技術による生産プロセスが進化していくことによって、逆に労働のアウトソーシングが減っていき、お互いにもっと近いところでモノは計画・設計され、そして生産されていくのではないかと思うのです。そしてそれは結果的に、人と人とをお互いにより近づけていくのではないでしょうか。
これからは、人々はもっと自由に移動して、もっといろいろな場所に移り住んでいくでしょう。もっと田舎に、もっと小さな町に。それでも最新の技術や生産手段によってお互いにつながっているのです。将来的には、小さな町こそがこうした技術革新から恩恵を受けるだろうと思っています。
鷲尾:
とても共感します。テクノロジーの進化がどのように生活圏のあり方を変えていくのか。僕もそのことをさらに探求していきたいと思っています。
アッセンブルとして、これから取り組んでみたいことをお伺いできますか?

これから1週間、昼夜火を燃やし続ける
「ともに創る」ことを通じて。
アダム:
私たちにとって最大の課題の1つは、どのようにして私たちのアプローチをより大きな規模のプロジェクトでも生かすことができるのかということです。例えば巨大な住宅計画を作り出すようなプロジェクトを提供することに慣れている建築家とコラボレーションするとしたら、私たちのアプローチはそこでどのように機能するでしょうか。 それはとても面白いチャレンジでしょう。他のやり方をする人々と、どのようにして協力していくことができるのか、今そのことについてよく仲間たちと話をしています。
鷲尾:
規模(スケール)は本当に重要な問題です。
アダム:
ええ もしかすると不可能かもしれません。 多くの人と同じように働く必要があるのかもしれません(笑)。
鷲尾:
今回の資生堂ギャラリーでの展示では、どのようなことにトライされていますか? テーマは「アートが日常を変える」、でしたね?

窯出し。出来上がった作品はこのあとギャラリーに運ばれる。
アダム:
「プロセスの伝達」が私たちのコンセプトです。今回私たちは、グランビー・ワークショップのアプローチを持ち込みました。通常はギャラリーでは完成品の展示が目的でしょう。そうではなくて、展示の一部となるオブジェクトを実際にワークショップの参加者と一緒に作り、そのプロセスを共有し、そして最後に完成したものをギャラリーで共有しあうというものです。ギャラリーがモノをつくりだすことについてのコミュニケーションや教育の現場に変わる。とても重要なテーマだと思っています。
鷲尾:
益子という風土が育ててきた文化がそこに加わることで、またその場所がうみだす価値が広がりますね。今回の展示は、小さな町と町とが「ともに創る」ことを通じて結びついていく、そんな新しい関係がうまれる大切なきっかけになっていくように感じます。
アダム:
ええ、本当にその通りだと思います。「ともに創る」ことを通じて。

アダム・ウィリスさん
これからの生活圏に必要なのは、「共同作業場」だ。
※今回「グランビー・ワークショップ」の制作パートナーとして、アッセンブルのメンバーを支えてきた陶芸家・鈴木稔さんにも、お話をお伺いしました。鈴木稔さんは陶芸家としてのお仕事とともに、地域の仲間たちと「ヒジノワ」というコミュニティスペースを運営されている方でもあるのです。
鷲尾:
アダムさんたちはきっとたくさんのことを鈴木さんから学ばれていると思いますが、逆に、鈴木さんにとってはどんな発見はありましたか?
鈴木:
僕も彼らも轆轤(ろくろ)ではなくて、型を使って制作するのですが、僕の場合は、粘土の薄板を石膏に貼りつけ組み立てるんですね。彼らのやり方は、泥漿(でいしょう)をつくって、型に流し込んでから零してつくる「鋳込み」という方法。口径の違う4種類の石膏の型を組み合わせることでいろいろな形ができる。たぶん建築的な発想かな。同じ型を使うといっても、全然違う手法なんです。陶芸家としては驚いたし、いい刺激を貰いました。まだまだ新しい発想があるんだなって。ここに僕住んでもう30年だけど、実は、登り窯を人に貸したのは今回が初めてだったんです。
鷲尾:
アダムさんと話していて、とてもいいなと思ったのは、「オーナーシップ」という言葉でした。私はその言葉を「私たちごと」という風に解釈しました。そこの街に暮らしている人とか住んでいる人が、これは自分たちの街だということを感じる、そのフィーリングをどうやって育てていくか。コミュニティの再生のためにそれが一番大切だと。そのために「ともに創る」というプロセスが重要なのだと思います。「ともに創る」という経験が、そのコミュニティの「オーナーシップ」を育てるように思う。それは町でも、都市でも、あるいはビジネスのコミュニティであっても通じることなんじゃないかなと思います。

窯出しされた作品を手に。鈴木稔さんと。
鈴木:
実は10年ほど前から、益子の町中に「ヒジノワ」というコミュニティスペースを仲間たちと運営しているんですね。いろいろなことがあったし、意見が合わないこともあったけれど、でもやっぱり良かったなって思う。一緒に何かを創り上げていくというときに、初めて人は強く結びついていくということを実感してきました。創っていく上で、どうしてもうまくいかない時もあるし、逆に、うまくいって、ああ、よかったって共感できたりとか。そういう体験を通じて初めて仲良くなれる気がする。ただ一緒にごはん食べただけとか、長く話をしただけでは分からないことがたくさんあるけど、何か一緒に作業をすると距離がギューッと近くなる。今回、彼らと長い時間を過ごして、一緒に窯を焚いて、また窯出ししてという、つくり上げていくプロセスを一緒にともに過ごしたという経験は忘れないと思うんですよね。
鷲尾:
いわば「共同作業場」ですよね。「ともに創る」ための場所。そういう場所が開かれていることが、コミュニティを支える力になっていく。アプローチも、発想も、技術も、お互いに違うものを持っているから、やって面白いですものね。
鈴木:
それはすごく重要だと思います。「ヒジノワ」の場合は、陶芸家は僕を含めて数名。その他に、大工さん、彫刻家、カメラマンがいたり、デザインをできる人がいたり、料理を作る人がいたり。あと、役場の人もいて、補助金の申請の仕方を教えてくれたりとかね。いろいろな能力のある人たちが雑多に集まって、それぞれができることをやっていくというのがよかったと思うんですよ。最初は会議とか、自分たちの存在意義とは話し合ってたんだけど、止めちゃいました。来ている人たちがみんな居心地よくて楽しんでいるのが一番長く続く。そしたら、今度はこの町で働こうって人たちもここに場所を持つことになりました。
鷲尾:
それも、「ともに創る」ことの楽しさが導いてきた風景なんでしょうね。
(撮影:柴 美幸、 鷲尾 和彦)
プロフィール

ASSEMBLE(アッセンブル)
アート、デザイン、建築、社会学、哲学など多様なバックグラウンドを持ったメンバー16人によって、ロンドンをベースに2010年に結成された英国の建築家チーム。2015年に、リバプールの荒廃した住宅街の再生を地域コミュニティとの協働によって果たしたプロジェクト「クランビー・フォー・ストリーツ」によって、イギリスの現代美術のアーティストに授与される「ターナー賞」を建築家チームとして初めて受賞した。最近の主なプロジェクトに、ゴールドスミス現代美術センターの改築「Goldsmiths CCA」(2014〜)、アートの実践と教育のためのスペース「Art Academy」(2017〜)などがある。今回、インタビューに答えていただいたアダム・ウィリス(Adam Willis)さんはケンブリッジ大学の建築学科出身。建築、家具のデザインなどを主に手がけている。
https://assemblestudio.co.uk/

鈴木 稔 (すずき みのる)
1962年埼玉県生まれ。1986年早稲田大学卒業。1991年高内秀剛氏に師事。1996年益子町芦沼に工房を構える。
2004年第5回益子陶芸展入選。
2006年益子陶芸展審査員特別賞受賞。
2007年登り窯を築く。